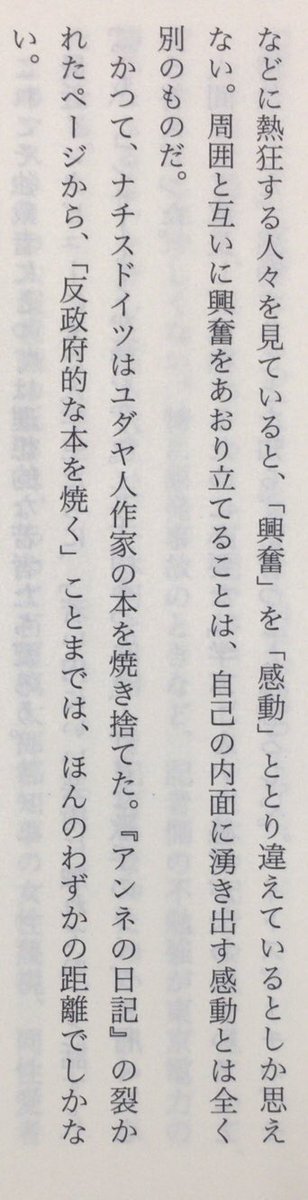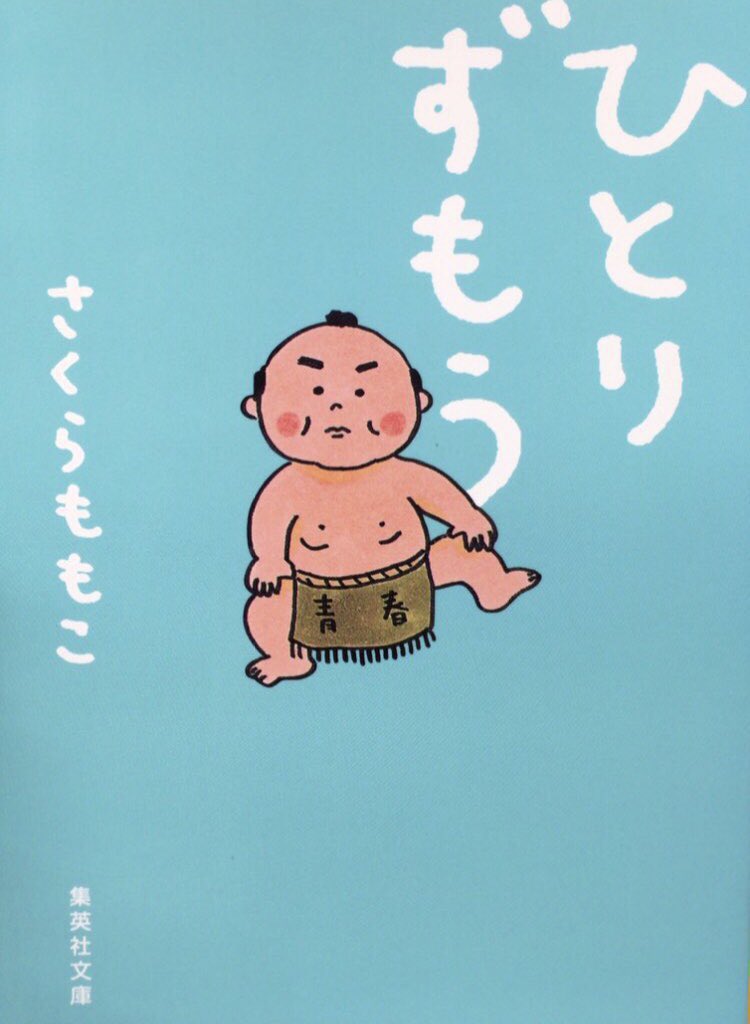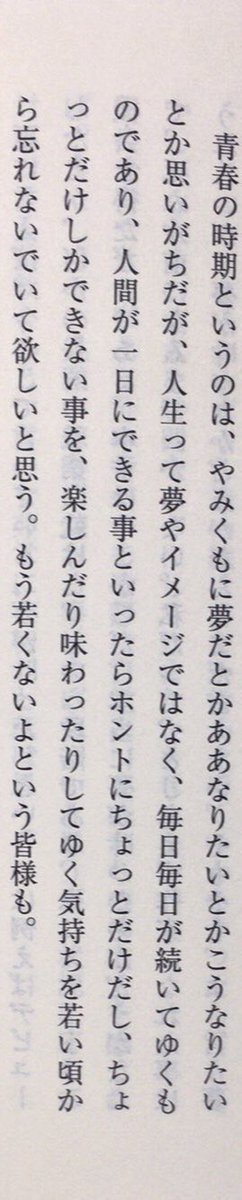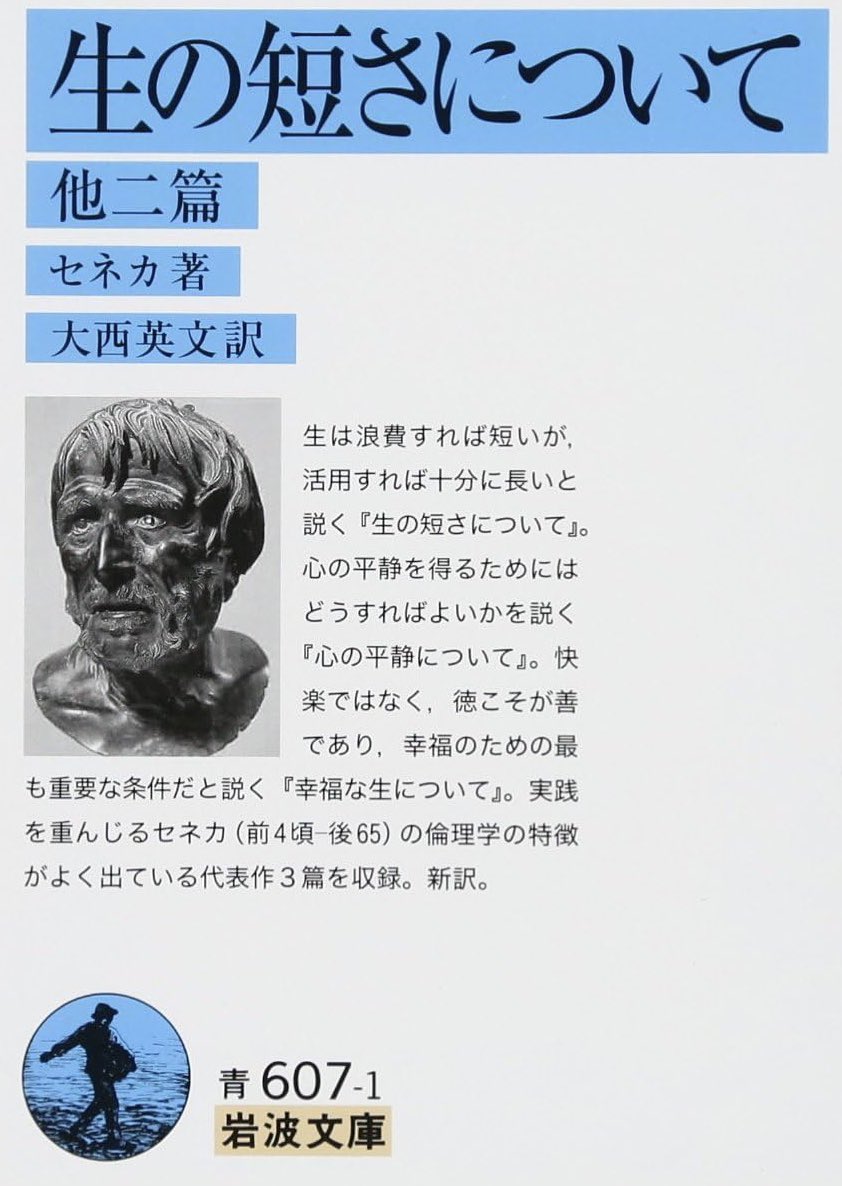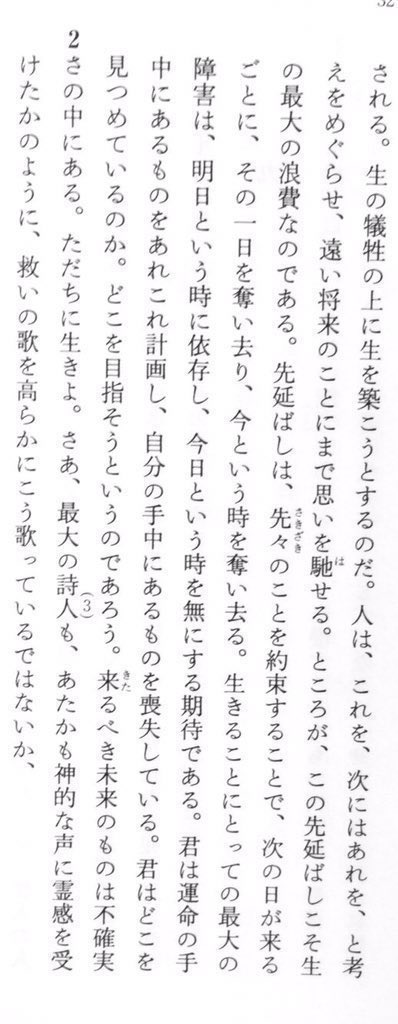751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
「世界の猫の呼び方」
「猫(イエネコ)の世界共通の呼び方(学名)は「Felis silvestris catus(フェリス・シルヴェストリス・カトゥス)」です。」
(参照:服部幸監修『ニャンでかな?』P114)
#猫の日
762
763
図書館に行くときの服装は、個人の自由。それよりも、雨の日に図書館を訪ねる際は、水濡れ対策に袋を持参した方がいい、とか、結露で濡れる危険性があるので、ペットボトルや水筒を本の上に置いたりしない、とか、そういう注意を呼びかけたい。
765
8月10日は、スヌーピーの誕生日。
「私たちは子供のころから人と自分とを比較することに慣れているため、自分が幸せかどうかさえも、人と比べて判断しがちです。しかし、幸せの尺度はひとりひとり違うもの。」(『スヌーピー こんな生き方探してみよう』朝日文庫、P93)
#スヌーピーの日
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775