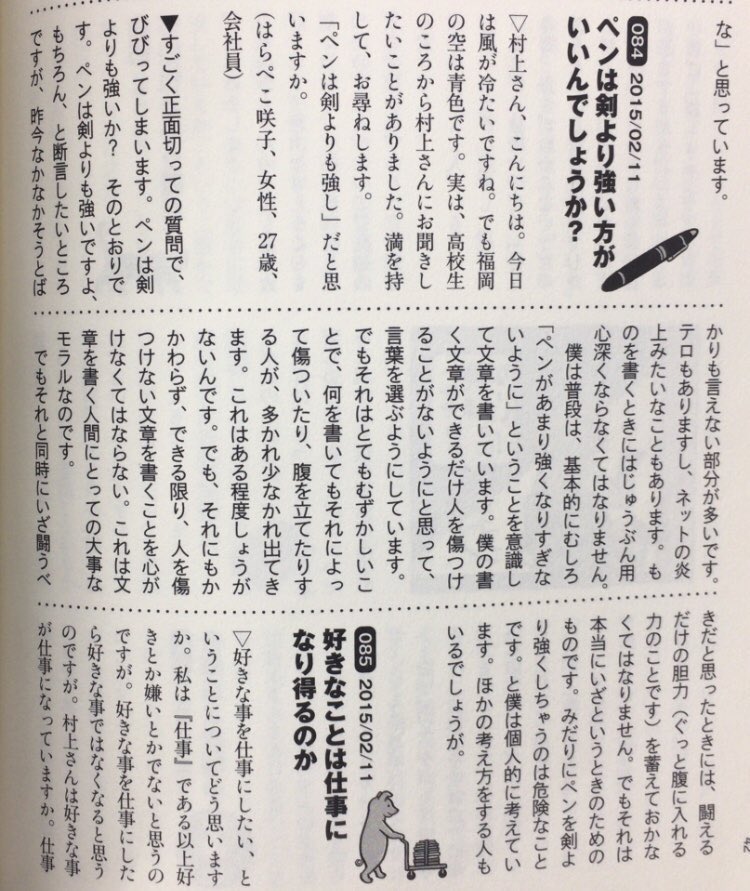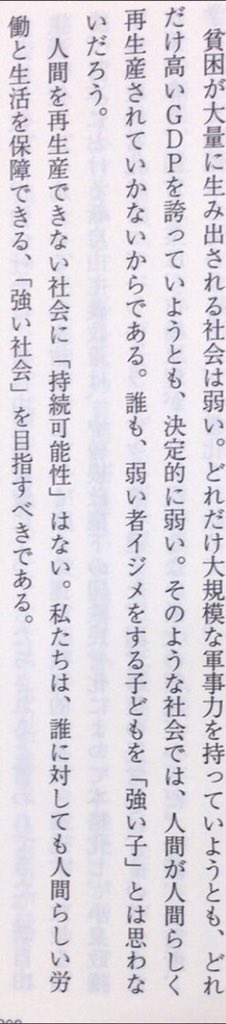726
書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。
727
728
729
730
731
732
733
734
736
【10万円で購入できる本の冊数③】
(単行本)
・吉川弘文館の人物叢書(平均価格約1998円)⇨50冊
・吉川弘文館の歴史文化ライブラリー(約1750円)⇨57冊
・ミネルヴァ書房の日本評伝選(約3174円)⇨31冊
737
738
739
小学校時代、よく担任の先生が言っていた言葉。「怒り(いかり)」と「理解(りかい)」は裏表。小学生時代は「逆さに読んだだけじゃん」と思っていたが、今ではなんとなく腑に落ちている。
740
741
742
743
745
746
747
748
749
750