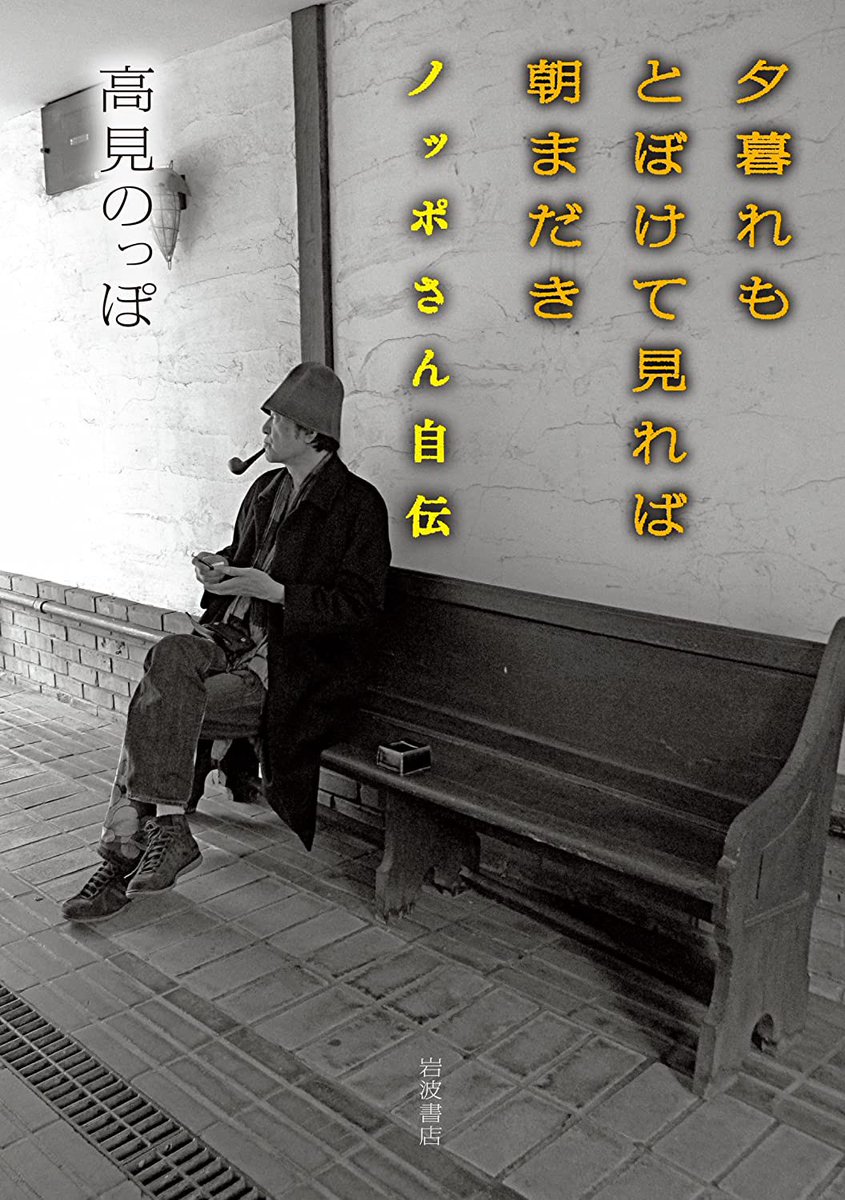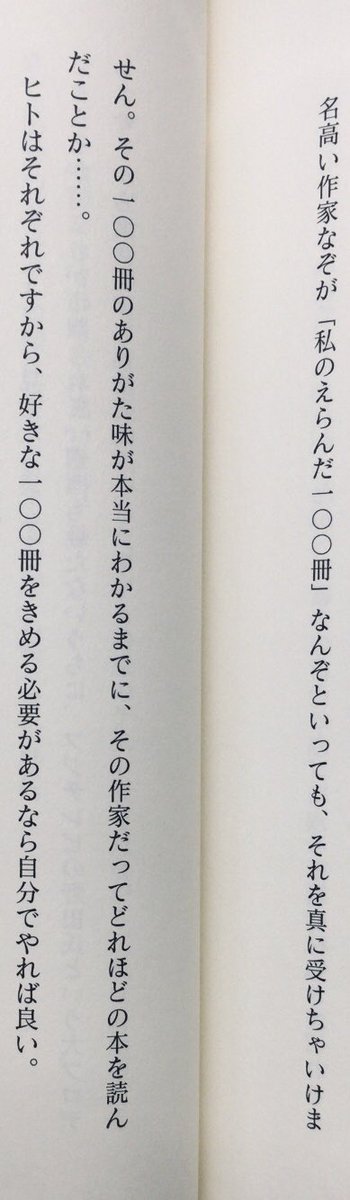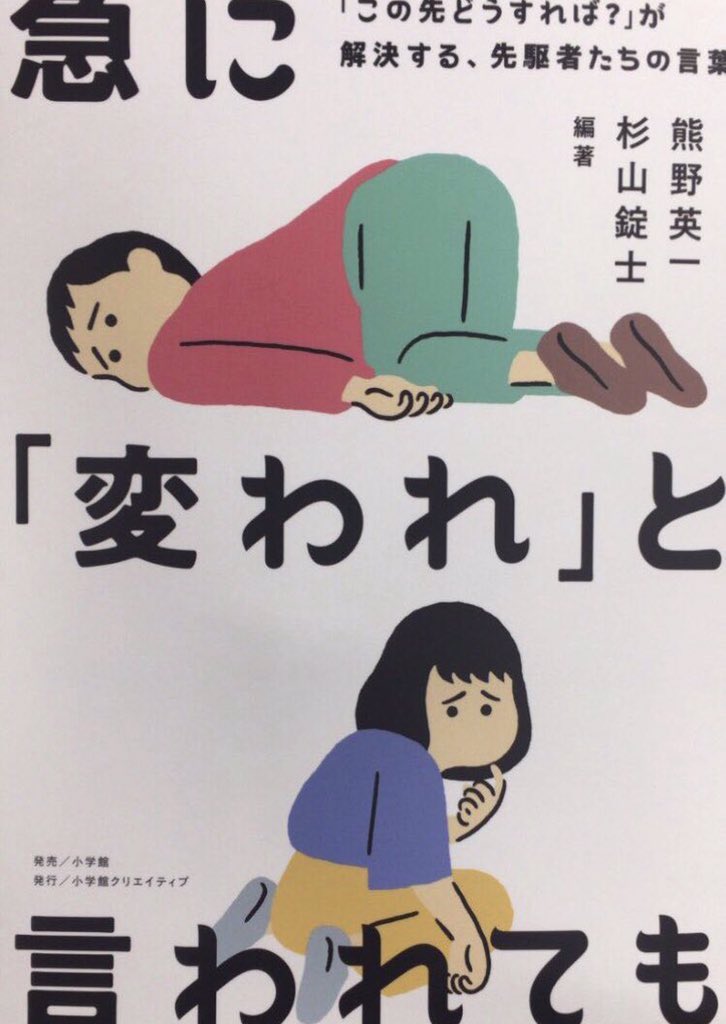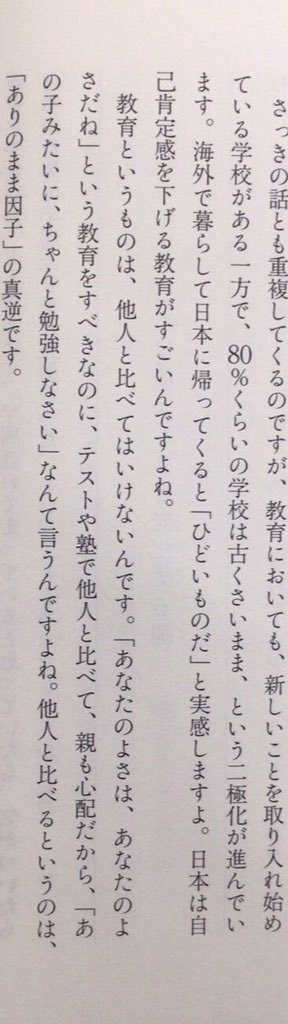701
702
以前家庭教師で教えていた生徒さんが、国語の教科書に掲載されている魯迅「故郷」を読んで、「魯迅の文章はすごく好き」と言っていた。確かに「故郷」には感動を覚える。たださらに一歩を進めると、本当に評価すべきは、魯迅の文章と一中学生を媒介する日本語訳を生みだした、訳者の竹内好ではないか。
703
704
705
706
障害者の生きづらさの要因を、個々人の「身心の障害」に帰するのではなく、「所謂「健常者」用につくられた社会」に求める視点は重要である。つまり障害者は、他者によって「障害者にされた人たち」という一面を持っているということである。(この視点を社会学では「障害の社会モデル」と呼ぶ。)
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724