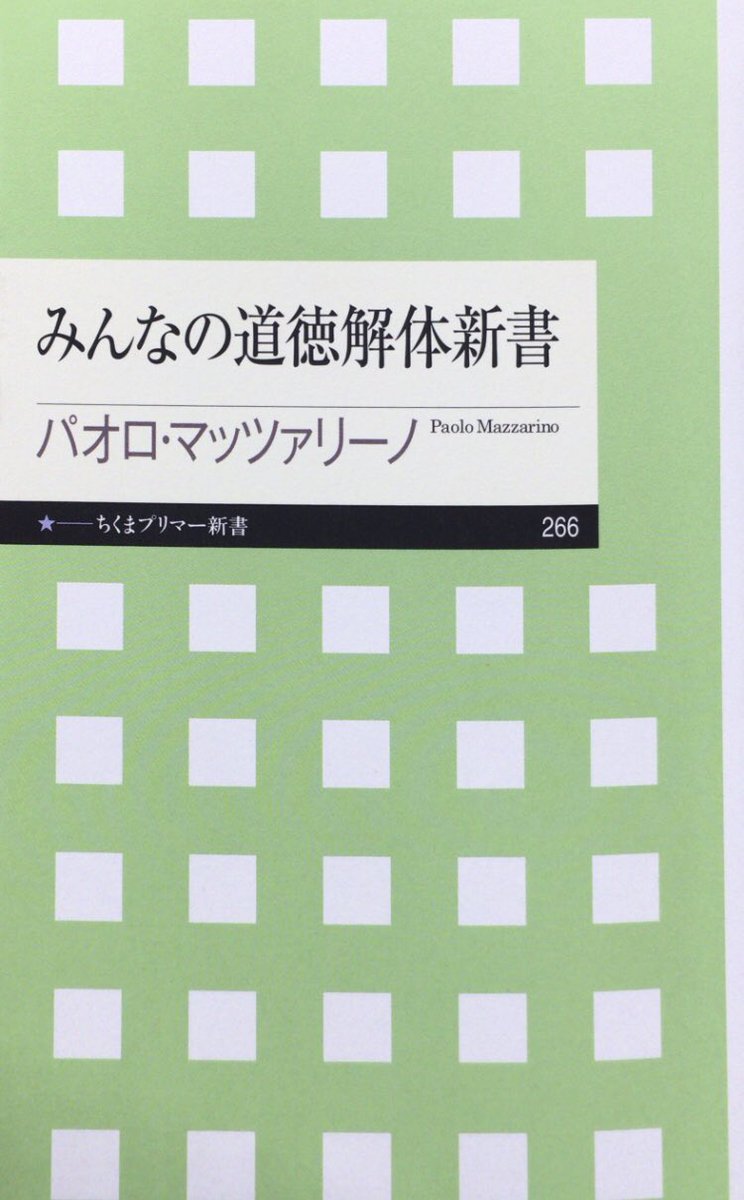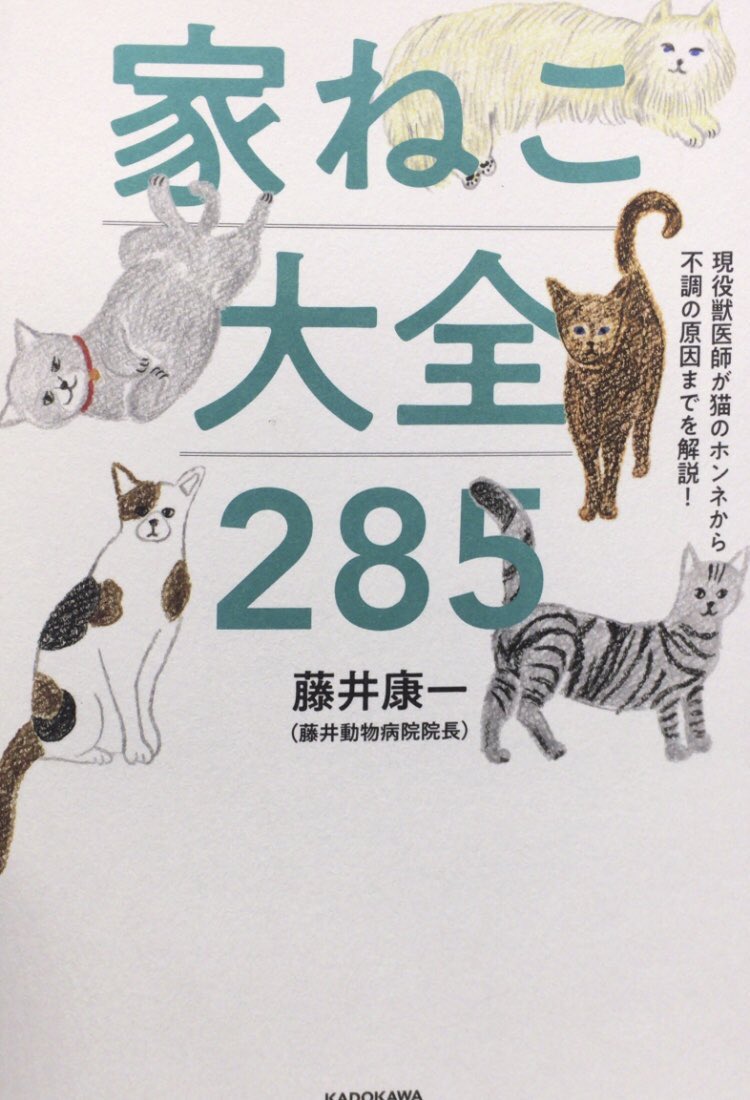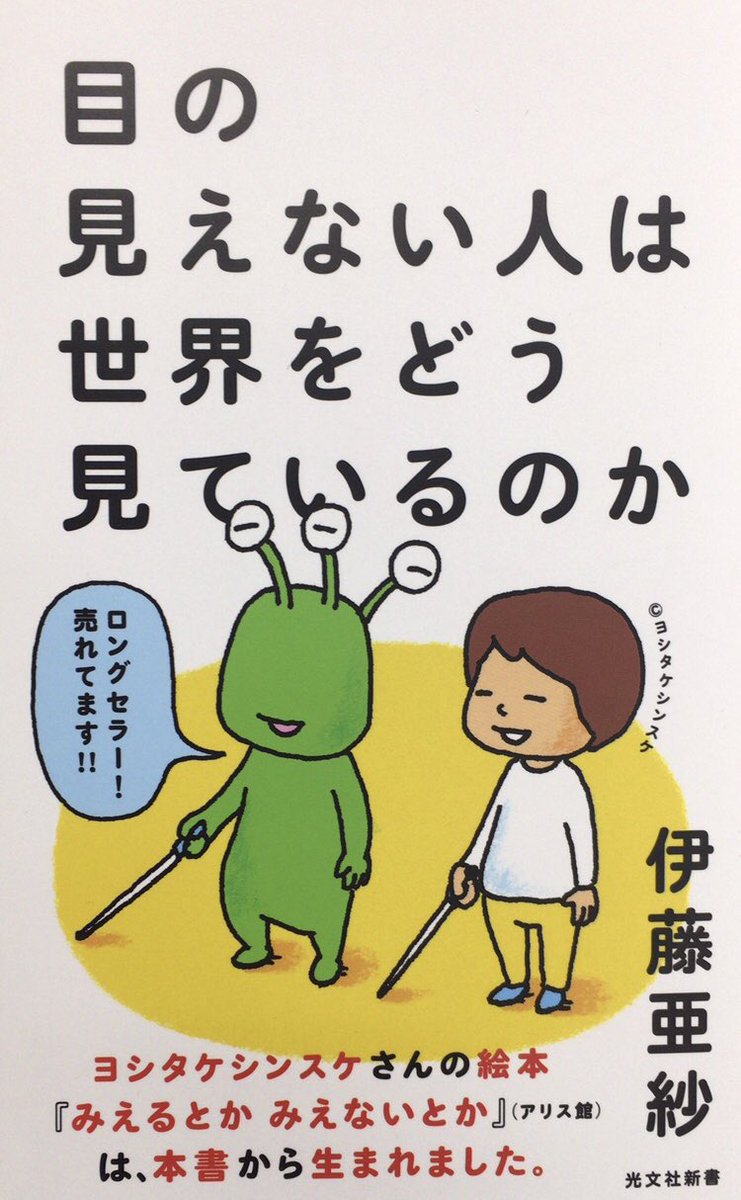676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
政府や社会問題に対して批判を行ったときに、「なにもそこまで言わなくても。大袈裟だねー」と水を差してくる人がいる。だが、「大袈裟」とは言えなくなった段階で批判をはじめても、それはもう手遅れである。
699
700
「ひどい理不尽に対してされるがままでいるしかない、無力でみじめな者は、この耐えがたい、生きがたい体験の意味を、それでも「生きうる」、さらには「生きるに値する」ものへと変造しがちである。」(内藤朝雄『いじめの構造』講談社現代新書、P115)
amzn.to/3NagilL