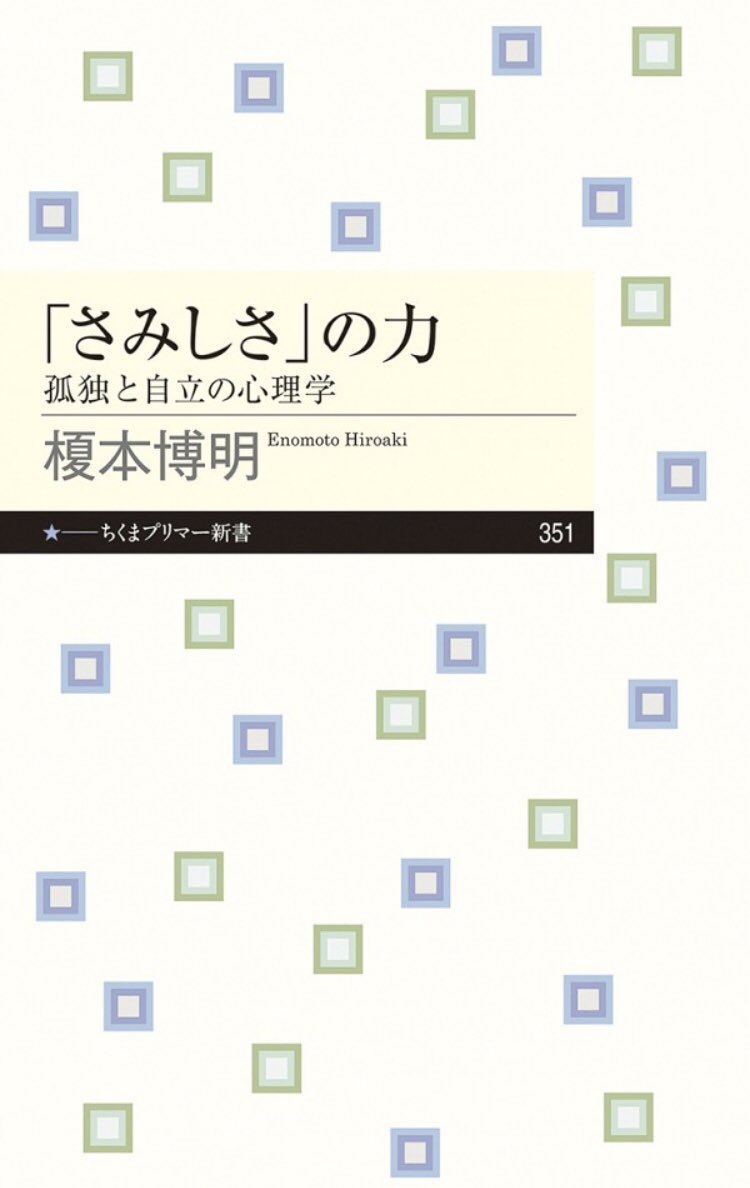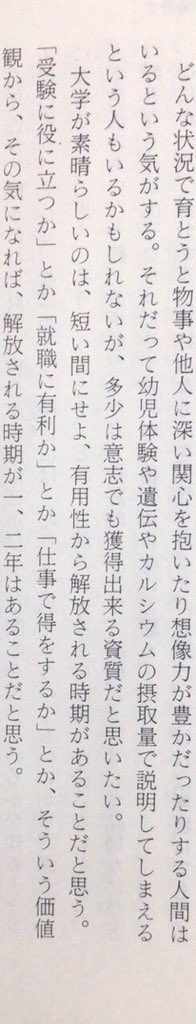426
427
428
「国からの支援などに頼らず、学問は自力ですればいい」のような発言は、経済的な余裕はないものの何とかして学問を続けていきたいと考えている大学(院)生の意志・行動を萎縮させてしまうものだと思う。「産まれたときから立派な研究者だった人間などいない」という前提が、無視されている。
429
431
432
433
434
435
436
437
438
441
442
443
444
445
446
448
449
450