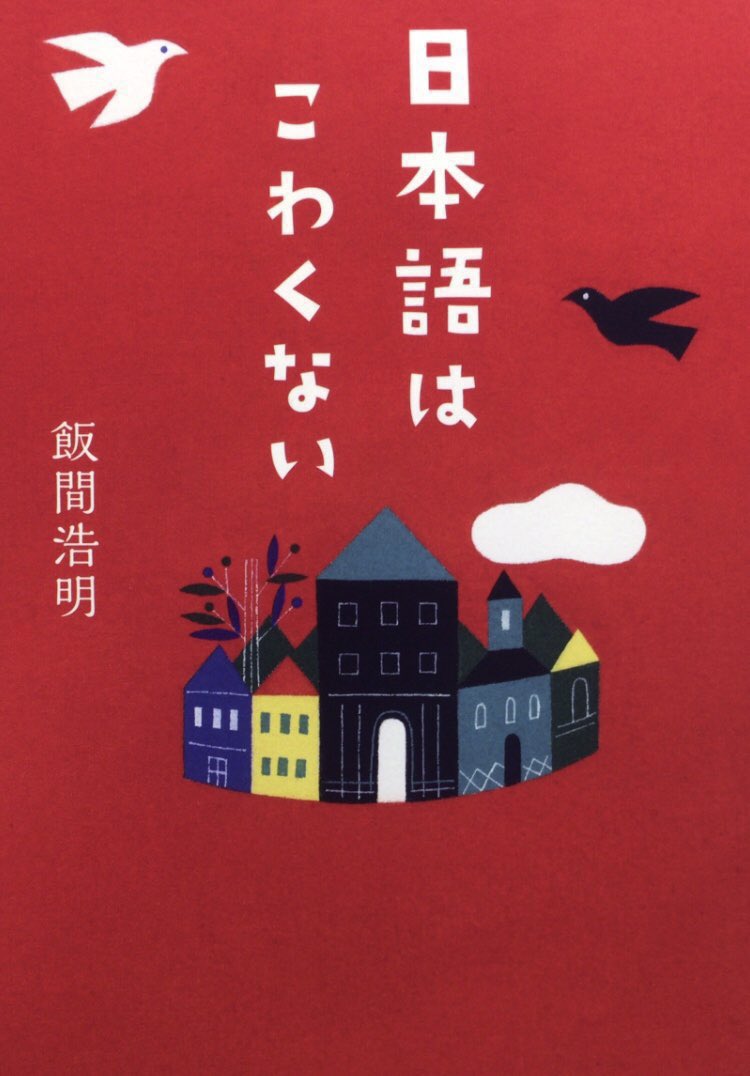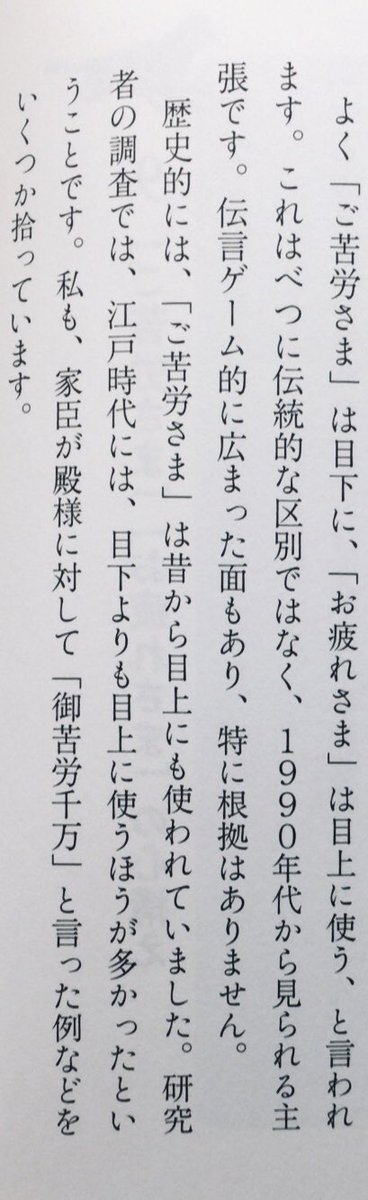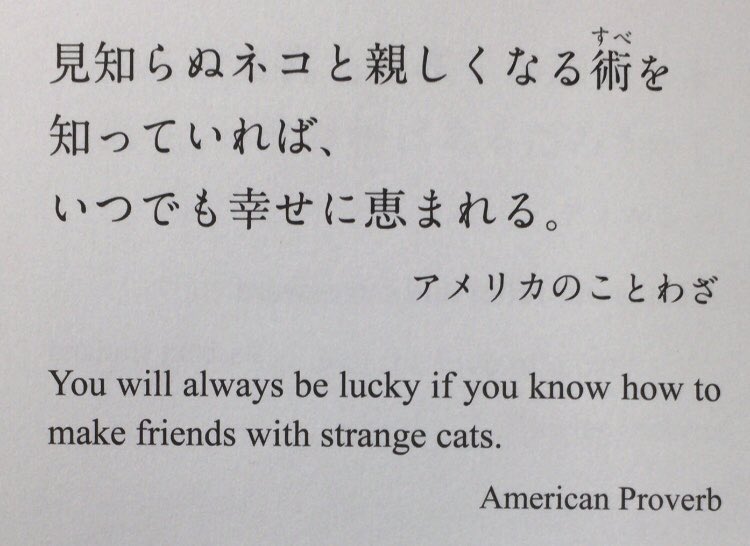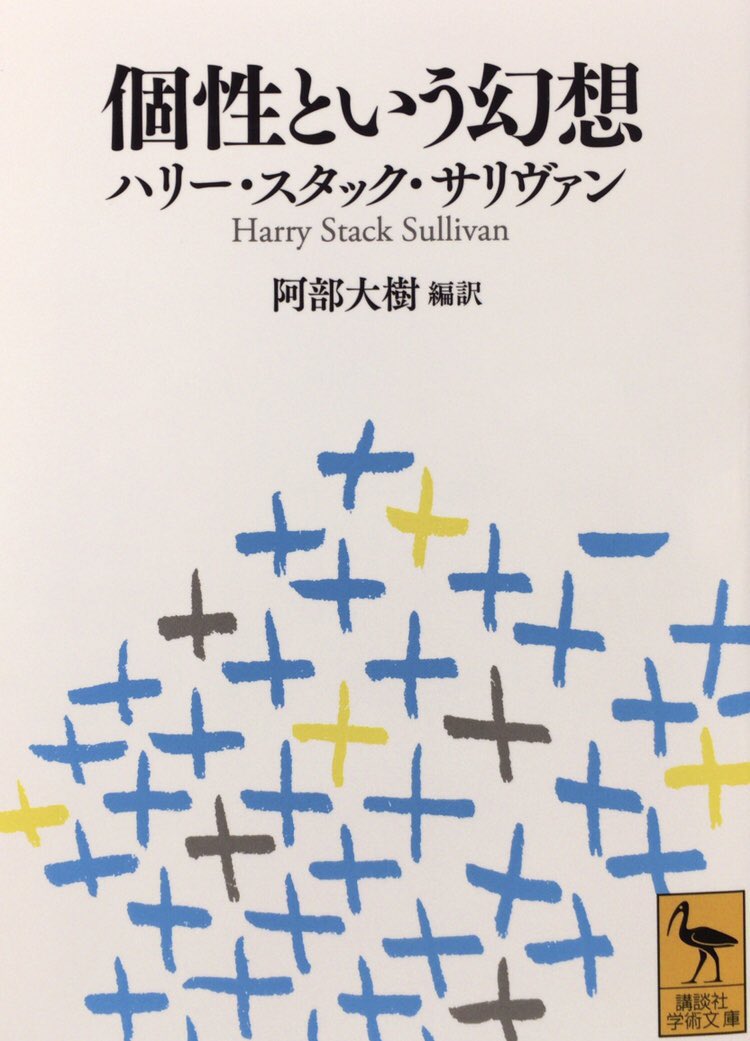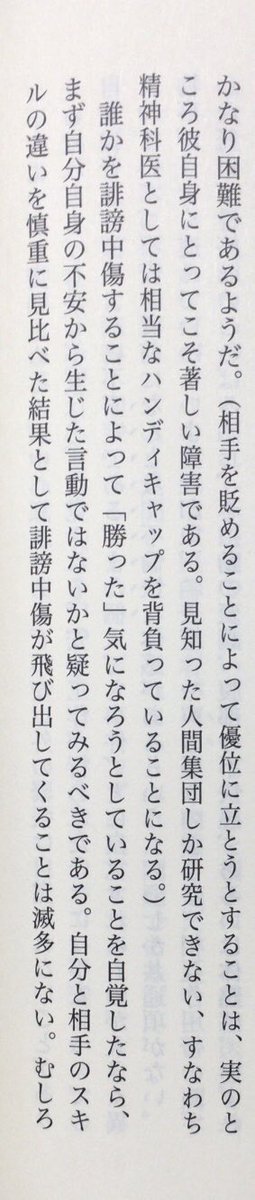377
378
379
書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。
380
381
「フェミニストの敵はセクシスト(性差別主義者)だ。フェミニストが憎んでいるのは「男性」ではなく「性差別や性暴力」であり、その構造やそれに加担する人々だ。」(アルテイシア『自分も傷つきたくないけど、他人も傷つけたくないあなたへ』P24)
amzn.to/3jNfjPl
382
383
384
385
386
387
389
【10万円で購入できる本の冊数②】
(新書)
・岩波新書(平均価格約792円)⇨126冊
・中公新書(約845円)⇨118冊
・講談社現代新書(約791円)⇨126冊
(選書)
・筑摩選書(約1672円)⇨59冊
・講談社選書メチエ(約1751円)⇨57冊
390
391
393
394
395
396
397
398
400