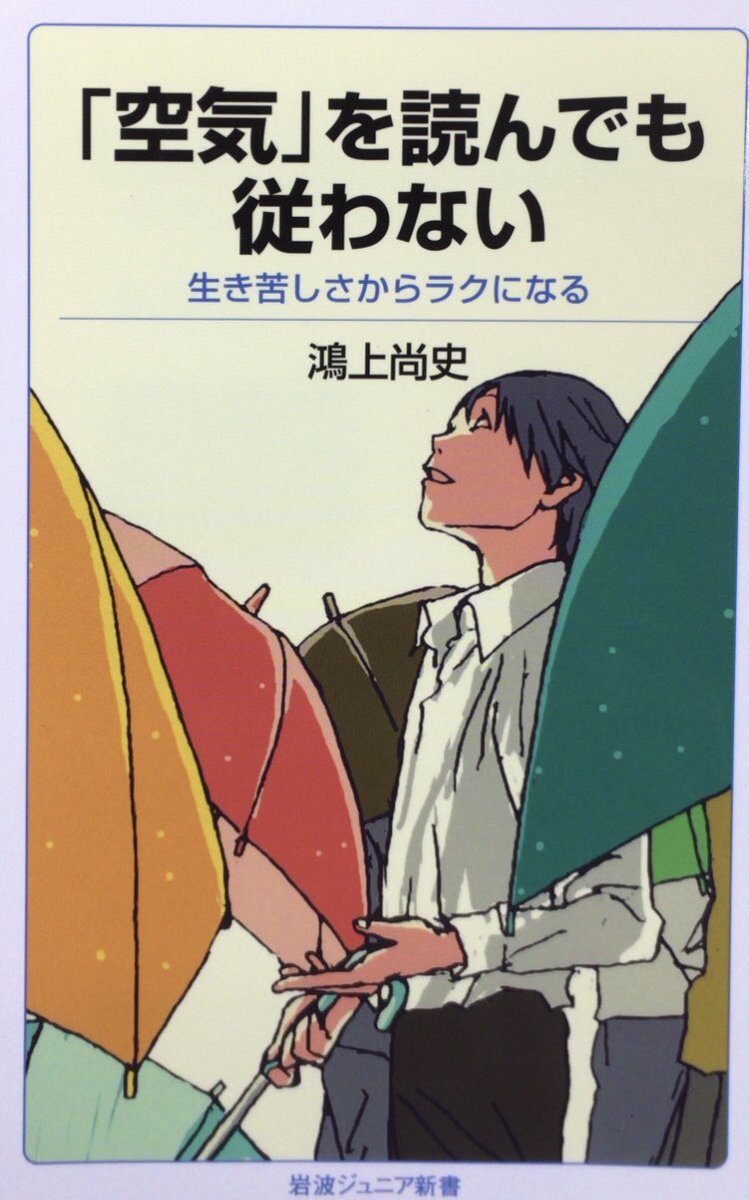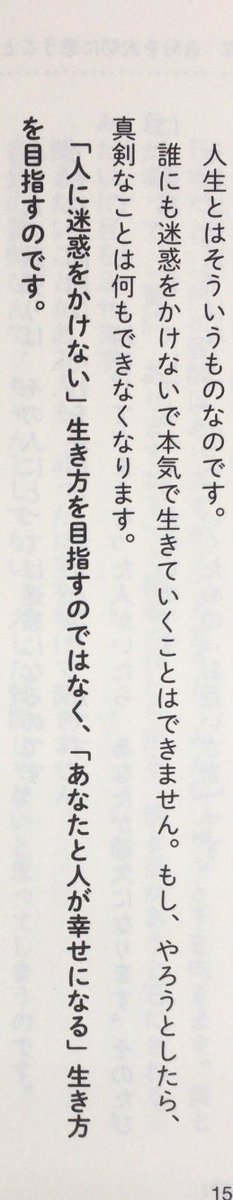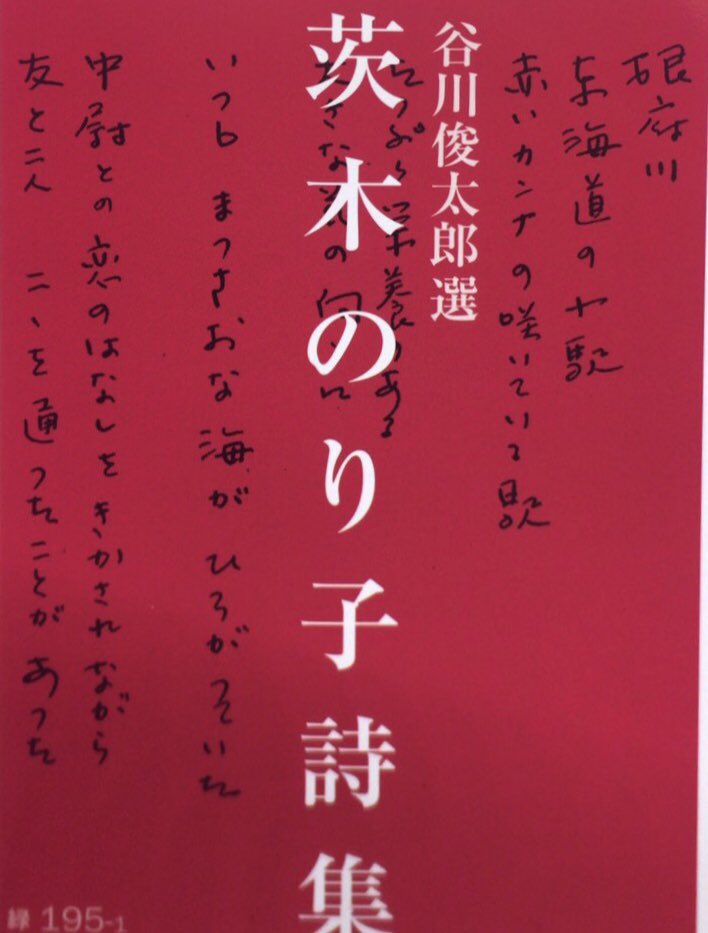476
477
478
479
480
481
482
483
多くの「弱者」が自分のことを「弱者」であると気づいていない状況ほど、政府にとって都合のいい状況はない。
484
485
486
487
488
489
490
492
493
494
495
古本まつりからの帰りにブックオフに立ち寄ることを、友人たちは「別腹」と呼んでいる。
496
497
498
499
500