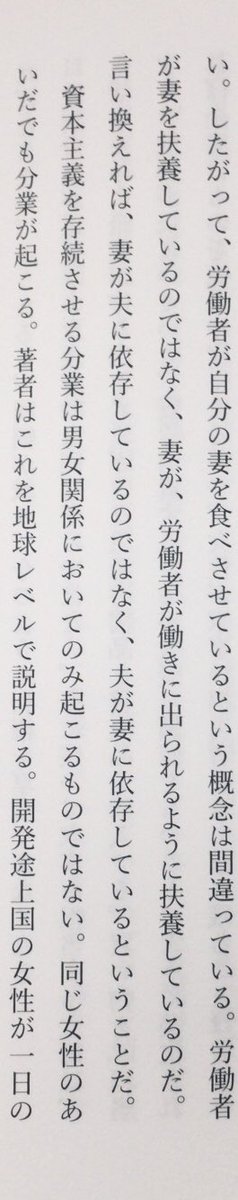401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
413
「本好き」と言っても色んな形がある。
友人の一人は、ある一つの作品を文庫本がぼろぼろになるまで再読し、「買いなおして、これで三代目」と教えてくれた。
夢中になって何度でも再読できる作品に出会えた友人を、羨ましく思う。
414
415
416
417
419
「歴史の流れ、社会の動き、政治経済の問題、そういうものを知ろうともしないで、全部失った後でしまった、こんなはずじゃなかったと言っても、もう遅い。あとの祭りです。」(かこさとし『未来のだるまちゃんへ』文春文庫、P18)
#わたしも投票します
420
421
422
424