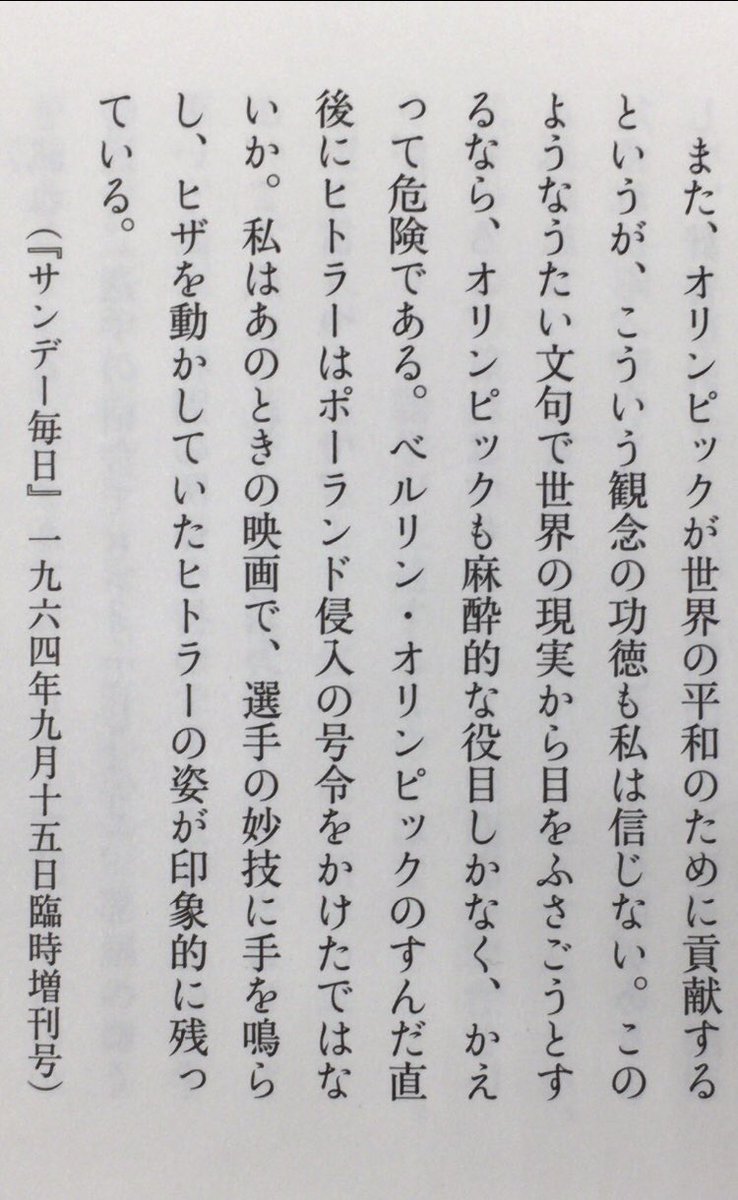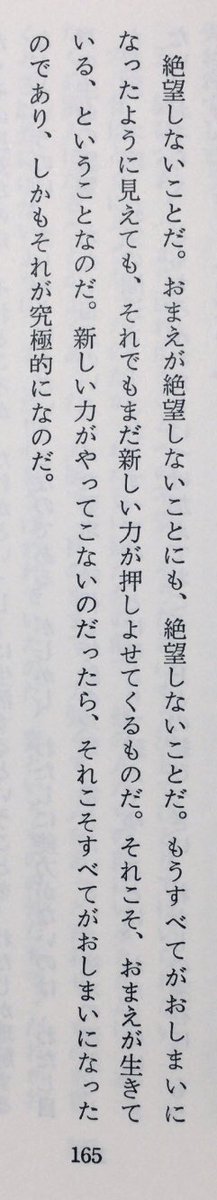351
352
354
355
356
357
358
「オリンピックが世界の平和のために貢献するというが、こういう観念の功徳も私は信じない。このようなうたい文句で世界の現実から目をふさごうとするなら、オリンピックも麻酔的な役目しかなく、かえって危険である」(松本清張・文、『1964年の東京オリンピック』P47)
#日本政府は五輪中止の決断を
359
360
361
362
363
364
「国会でつくる法律も、内閣が出す命令も、都道府県や市町村でつくる地域の決まりである条例も、すべて日本国憲法の下にあり、憲法に違反したら、成り立たないんだよ。」(『憲法って何だろう』小学館、P180)
amzn.to/3ycW4Uj
365
366
367
368
370
371
372
373
374
選挙において「棄権」が有効なのは、「適切な候補者がいない」という意思表示を、政治家側がきちんと危機感をもって受けとめる姿勢がある場合に限られる。「できるだけ投票に行ってほしくない」などと躊躇なく公言する政治家が存在する時点で、「棄権」はただの権利の放棄となって終わる。
375