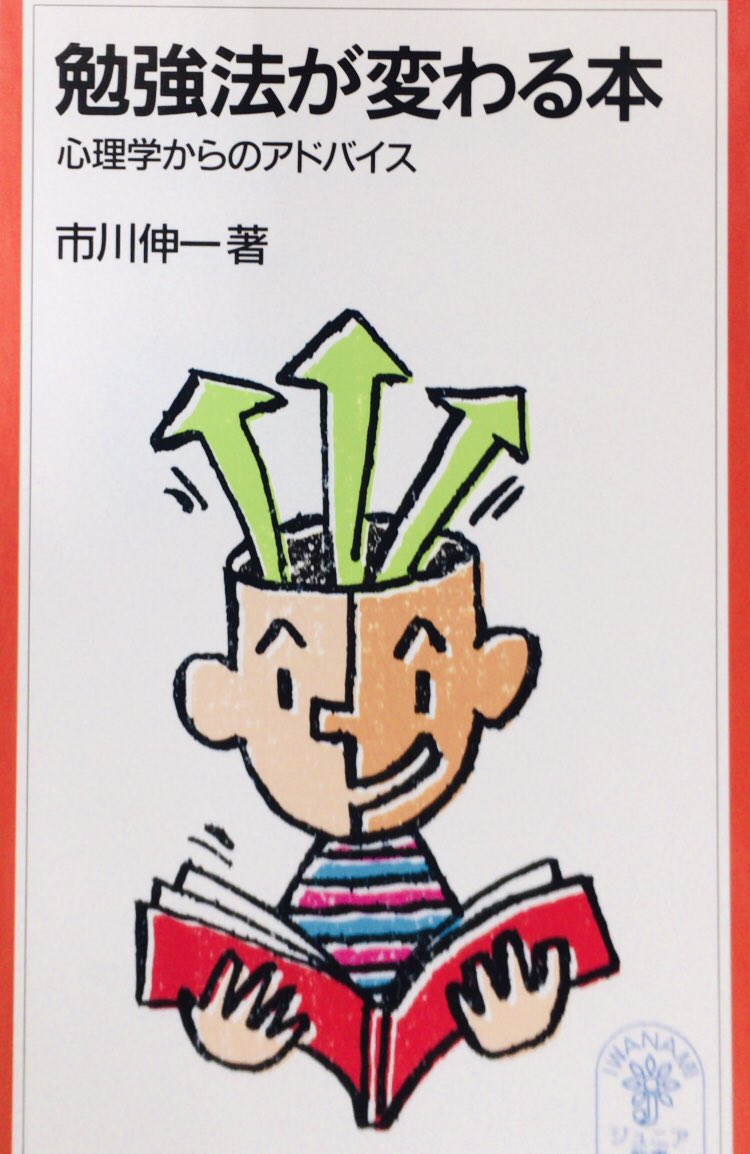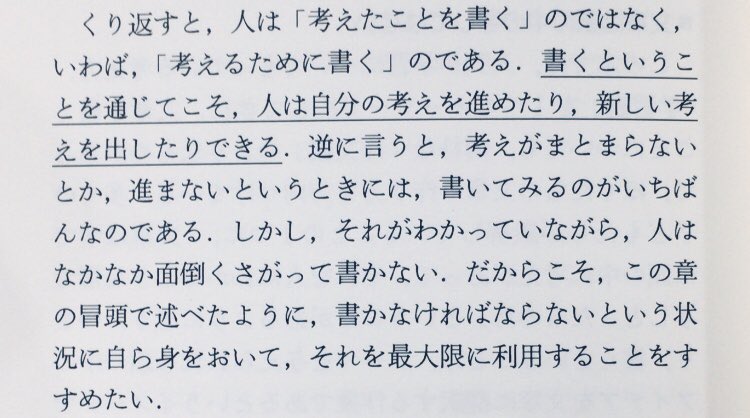326
327
328
329
330
331
332
333
褌一丁で執筆に励む稲垣足穂と移動中の猫。
(参照:『作家の猫』平凡社、P68~69)
#世界猫の日
334
「朝鮮人あまた殺され
その血百里の間に連なれり
われ怒りて視る、何の惨虐ぞ」
(萩原朔太郎:述)
#都知事は追悼文出しましょう
335
336
337
339
340
341
342
343
344
346
347
348
349
350