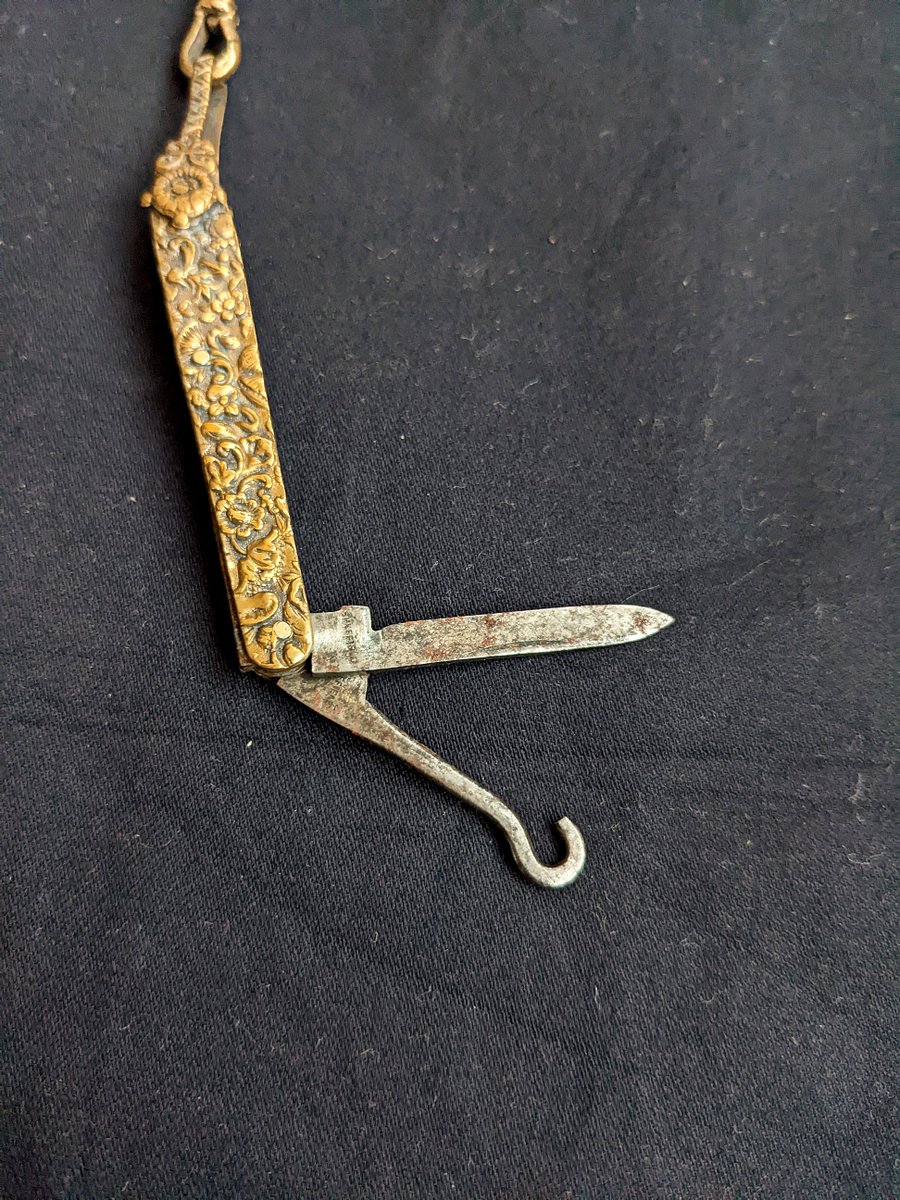501
サイドサドルの型紙は21日(月)まで販売しております
つくるぞ!という方は参考されてください
しかし、このスカートをつくろうとすると「生地を半分ちかく捨てる」ことになります
複雑なカーブと贅沢な布使いは、限られた階級の人にのみ許された嗜みなのでしょうね
rrr129annex.blogspot.com/2020/03/sidesa…
502
2021年2月
3年振りの【 半・分解展 東京 】を渋谷で開催します
今年、叶わなかった大阪展と東京展
コロナ禍で見出した、私が表現すべき感動をかたちにします
開催まで残り4ヶ月弱
万全の準備で挑みます
sites.google.com/view/demi-deco…
503
504
型紙の販売は、今週の金曜日 21日までです
この機会に、150年前の洋服をご自身の手でおつくりください
なかなか面白いですよ
【半・分解展の型紙】↓
d-d-pattern.myshopify.com
506
「半・分解展の型紙」は5月1日(日)までの販売となります
鑑賞し、体感し、創造する
ここまでが半・分解展の提供するクリエイティブです
インプットした分、たくさんアウトプットにご活用ください
今年の冬服は、ご自身で仕立てみてはいかがでしょうか
型紙詳細↓
d-d-pattern.myshopify.com
507
508
510
511
こちらも使用人のお仕着せである燕尾服です
基本設計は同じですので、お尻のデザインを変更すれば、貴族の燕尾服にもなります
こちら全く需要がないようで、型紙はぜんぜん売れません
ただ個人的には思い入れの強い1着です
美しい造形をご堪能いただけます
↓
rrr129annex.blogspot.com/2020/03/countr…
512
513
515
516
初の大阪展です🙂
私、長谷川が個人所蔵する1750年から1940年までの洋服を展示します
私は造形の専門家です
なので展示方法がユニークです
洋服を分解して「内部構造」を可視化し、実際に試着できるサンプルを用意しました
半・分解展で、200年前の「着心地」を味わってみませんか🙂? twitter.com/fashionsnap/st…
517
518
519
521
522
523
524
525