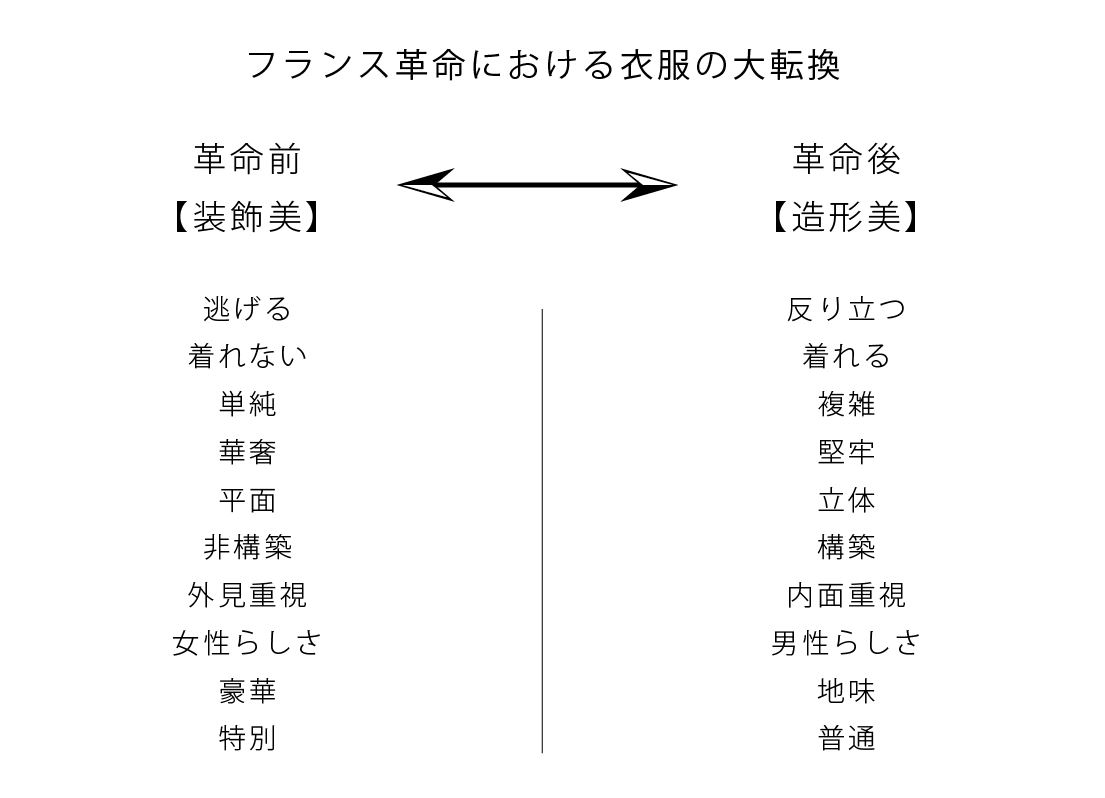327
328
329
私がおこなう【半・分解展】では、海外美術館から買い取ったコレクションを0距離で展示しています
実物に「触れる」ことも可能です
今年は2年振りに東京と大阪で展示をします
東京は10月18日から
大阪は11月26日から開催します
忘れないうちにカレンダーにもメモをお願いします🙂
330
331
332
さすが郵便屋さんの鞄なだけあって、小さくても容量バツグンです
お散歩に必要最低限のものはスッポリと入ります
そして、側面に「ペン挿し」が付いているのが、書留鞄らしいですよね
かわいいディテールです
型紙はHPよりお求めください↓
d-d-pattern.myshopify.com
333
334
335
【アビ・ア・ラ・フランセーズ】に関しては、動画でも解説しております
「なぜ、当時の肖像画は皆、同じポーズなのか」
「なぜ、フランス革命頃の服は着辛いのに動きやすいのか」
構造に着目し、廃れた美意識を探っています
ご興味ある方は、ご視聴ください
youtube.com/watch?v=VXS4Rd…
336
337
338
339
340
341
342
コーチマンズのコートは、型紙を販売しています
ピーコートでもトレンチコートでもない独自のデザインは、100年以上経った現在でも褪せることなく美しいです
型紙販売は今週末の金曜日21日までとなります
ぜひご自身の手でおつくりください
コーチマンズの詳細↓
rrr129annex.blogspot.com/2022/01/co.html
343
344
345
346
347
【初めての服装史!】
この春、ファッションから読み解く 美術史 を学んでみませんか?
半・分解展を主宰する私と巡る、ガイドツアーのご案内です
初心者でも楽しく学べるツアーです
日時は4月14~16日
渋谷でおこないます
参加チケットはHPよりお求めください↓
sites.google.com/view/dd--ateli…
348
350