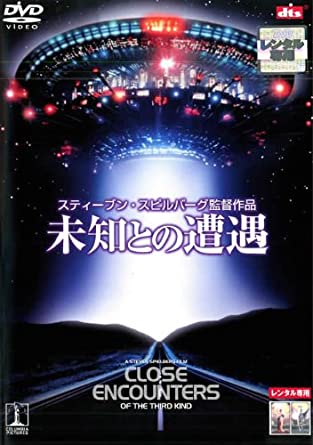76
シンマンってもっとオリジナルを神棚に上げて「元々そういうもんだから」で思考停止する感じになると予想してたんだけど。好き過ぎる人が作るとそうなるじゃん。それが「そこ真面目に突っ込むの?」くらい変えてた。だから元のウルトラマンと大体同じみたいな感想が新鮮で。あんなに変えてもそうなの?と
77
毎回そうなんだけど観客からの視点のそらし方がめちゃ上手いんですよね。これも上にこれみよがしなピアノ線が張ってなかったら多分仕組みに気付けたと思うんだよ。手品と一緒でさ。仕組みの種明かしを見るとなーんだと思うんだけど普通に見るとわからない。そこがすごいよな。
78
樋口さん庵野さん辺りが手がけるウルトラマンだともう見る前に「スプーン掲げて変身する中途半端なパロディとかドヤ顔でやりだしたらどうしよう」みたいな余計な心配する必要なくていいよな。そういう心配しちゃうんだよ我々ウルトラファンは。大変なんだよ(大変じゃない)
79
つまりスネ吉兄さんだけはドラえもんを「不思議なロボット」としてちゃんと認識してるのね。不条理な存在としてではなくちゃんと不思議なテクノロジーとして。またこのコマがディテール細かくて特に万力があるのが効いてるんですよ。このコマを境にリアルな世界側からドラの世界側に橋渡しされるわけで
80
83
普通はボタンやゲージを大量に描いちゃうと思うんですよね。F先生もわりとそういう機械描くし。多分これはテーマがジオラマだから普段から夢想してたんだと思うの。「こういう機械があって操作はこうでこういうオプションがあって…」みたいな。F先生ジオラマが絡むと急におかしな入れ込み方になる(笑
84
86
今週の仮面ライダーV3、正体不明のライダーマンにナレーションで「結城丈二はこのマスクをつけることによってライダーマンとなり手術した腕が連動しアタッチメントを操ることができるのである」と言ったら風見志郎が「そうだったのか!」と納得してた。ナレーションが登場人物に聞こえてる世界!斬新!
87
うる星やつらって内容は相当ドギツイんだけどあまり粘着質に後を引かないというかカラッとしてんすよね。いかにも高度成長期の漫画というか。タフじゃないと生きていけなかった時代。皆てんで勝手な事してる。その代わり相手をしつこく責めないのね。ドライなの。だからたまにウェットな話が効くわけで
88
ライダーバイクを呼ぶとマシンが無人で走ってくる(という体の)スタント、V3あたりからどんどんすごくなるなあ。ほとんど人が見えないよ。
#仮面ライダーX
89
この漫画は当時読んだときより時代が経ってからの方が驚いたな。なんせPhotoshopにレイヤーが導入されたのが1994年だし。端子が共通でアタッチメントになるとかUIも必要なときに必要最小限のものだけ表示される方が視認性がいいとかさ。後から「そういやF先生のあの漫画で…」と何度も思い返す事になる
90
あしたのジョーはどこにも所属してない何者でもない人間の物語ってのがポイントだよな。とにかく登場人物に親や兄弟がほぼ出てこないし高邁な理想もない。何者でもない持たざる者が親のためでも正義のためでもなくじゃあどうすんの?って話だから。そこであしたのためにってフレーズだもん。刺さるよな
91
石ノ森章太郎先生の漫画って読み方に慣れてくると「ムッ…石ノ森先生、この辺でこの連載に飽きたな」って瞬間がわかるようになるよね。
92
93
これがよりリアルに世界観を詰めるセブンの宇宙人になると完全にKGBみたいな感じになるのね。何を考え何を目的にしてくるか普通に理解できる。アイロス星人とか普通に「固形燃料を落とせ!」とか言ってくるしさ。シン・ウルトラマンもリアル世界観だから得体の知れない宇宙人感はちょっと難しいかもなー
94
95
96
97
メフィラス星人とか一見紳士っぽいんだけどキレポイントが変だもん。急にウルトラマンに「スパイめ!」とか怒り出したり。人っぽく振舞ってるつもりの異星人。そこがウルトラマン宇宙人の特徴で良さだよね。会話してるのに話が通じない怖さ。でもまあそういう部分を新作で踏襲しろと言われても困るよね
98
99
100