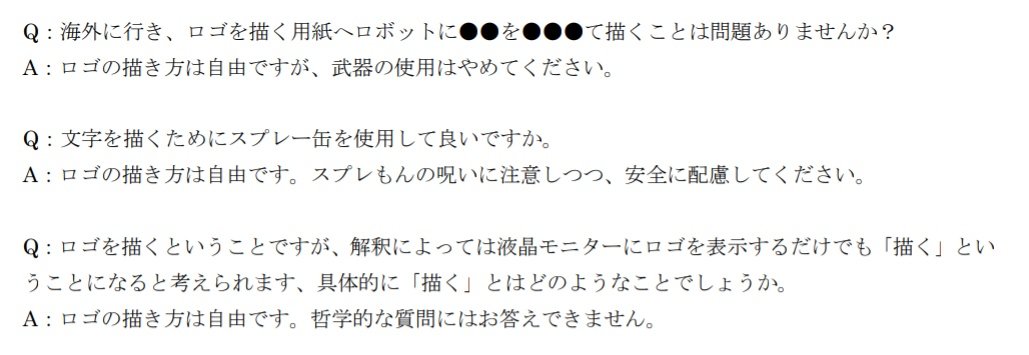176
177
178
179
180
181
今でも明治の看板商品である明治ブルガリアヨーグルト。
製法もさらにまろやかになるように日々改良が続けられている。
ネーミングに拘ったからこそ、今でも当時の本気度が続いているのだろう。
#にいがたさくらの小話 その347
182
183
軽々しくなければいいのかも。
彼らはそう考えた。俺たちの本気度を見せる。
工場に招いて製法も伝統に近づけていることを猛烈にアピール。
その結果、大使館は名前の使用を認める。絆されたのではない。本気度に感銘を受けたのだ。
しかし日本の一般庶民はブルガリアという言葉すら知らない。
184
185
186
187
188
現在では、それらの若者が歳を取ってしまったり、日本酒の銘柄の多様化によって売上は落ちているが、日本酒業界は若者だけでなく海外への布教にも力を入れている。
日本酒業界はさらなるイノベーションを起こせるか。
これからの日本酒業界にも注目したい。
#にいがたさくらの小話 その344
189
売り出した当初は全く売れないどころか、フタから液漏れがあり、商品回収などでマイナスだった。
それでも彼らは若者を諦めなかった。
フタは改善され、新たな販路を自販機や駅のキヨスクなどへ広げる。
電車で移動中に呑める酒が手軽に買える。
キヨスクへの導入はまさにイノベーションだった。
190
江戸時代の『下り酒』にルーツを持つ老舗酒造である大関にとって、カップ酒はまさにチャレンジだった。
だが同時に危機感もあった。
若者が日本酒を飲まなければこの業界全体が滅ぶ。
当時の若者はビールなどの洋酒に目が向いており、なんとかして日本酒を呑ませたい。
その思いで開発が始まる。
191
192
193
194
スプレもんに限らず、ロボコンには若き技術者のアイデアが詰まっている。
特にルールのQ&Aは必見だ。
そんなことまで考えるの?というのは、ロボコニストにとっては褒め言葉。
回答する方も大変だろうな。
わたしも昔やってましたけど。
#にいがたさくらの小話 その99改
195
色を変えるというアイデアはあまりにも奇抜だったが、技術が追いつかなかった。
スプレもんは伝説だけ残して一回戦で敗退。
床にドバドバと垂れる塗料に大会運営は困りまくる。
ちなみに作った大分高専は17回大会まで、惜しいところで全国出場が果たせなかったが、スプレもんの呪いと呼ばれた。
196
伝説が起きたのは、第4回。しかも地方予選だ。
この年のルールは、ロボットで箱を積み上げるというもの。
ただし、一番上の色のチームがその特典を総取りするというルール。
スプレもんは箱を乗せるという常識から解き放たれ、塗料をかけた。
スプレもんという名前だが、チョロチョロと流した。
197
198
199
200
英国海軍のカレーの流れを汲む当時のカレーには、南アジア料理では定番のチャツネが添えられていた。
だがある時、チャツネを切らしてしまう。
困ったシェフは代わりに福神漬を添えたのが始まりだという。
ちなみに福神漬を添えたのは一等客のみで、二等以下の客には沢庵が添えられていたらしい。