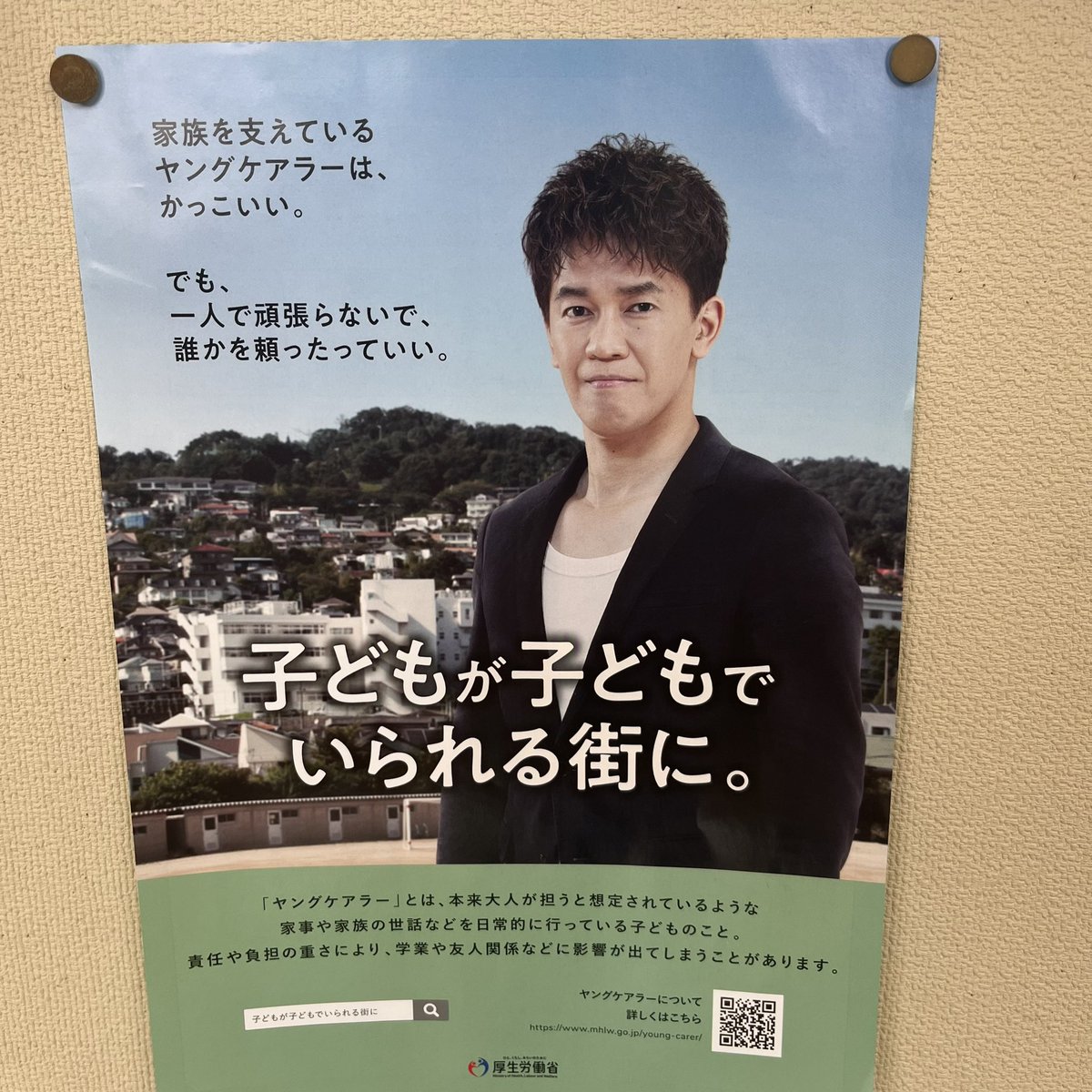226
多様性は誰の中にもある。大坂なおみさんも、そして私たちの誰もがあの場所に相応しい。だから彼女を批判するつもりは全くない。ただ聖火を手にする彼女が「多様性と調和」のシンボルとして「多様なバックグラウンドを持つ大坂選手が」とアナウンスされたことがあまりにも軽すぎて、うんざりした。
227
議員や企業経営者に向けて「子どもの貧困」やジェンダーギャップについて話す時「問題を放置したらこれだけ経済的損失がありますよ」という文脈を使ってた。その方が通じるから。でもやめた。人権という文脈で繋がることを私自身が諦めてどうするんだと。戦略でも何でもない、ただの逃げじゃないかと
228
ついでに「子どもの貧困?なら子ども食堂だ」という文脈がすでにズレているので、そこから探求してほしいです。
229
あとついでに。「他の団体からこんなことされました」「あそこは何もしてくれなかった」という話は私もよく聞きます。ですがそれはきっと私たちも他で言われてることです。制度に隙間が多すぎて「願ったとおりにいかない」支援なんてザラですし、マンパワーも部屋数も限られてる
230
「昔は今よりも地域の繋がりが強くて子どもを見守る目がありましたよね。近所の雷親父とかお節介おばさんとか」と言われることがあるけど同意しない。子どもが地域社会から「逸脱」しないよう見守る目はあった。でも家庭の中で安全に過ごせてるかについては、今以上に「見ない、触れない」だったと思う
231
なんだか度々店の奥で年配の男性店主がその女性やアルバイト女性を怒鳴りつける声が聞こえて来て、店員たちは接客時も表情暗くてびくびくしてて、何やらやべー店だなと思ってさっさと食べて帰った。美味しかったのに残念。で、もう2度と来たくなかったけど、
232
感情はコントロールできないのよね。コントロールできるのは感情表現(行動)の方
233
なんだか最近「許せない人を許せない」人が多くないかな?
不当な扱いを受け、尊厳を奪われ、傷つけられたらその相手を許す必要なんてない。怒りは自尊心を守るために大切な感情。そしてもし「許せる」時が来るのであれば、それは真っ当に怒って「許さない自分を許せた」その先にあるのだと思う。 twitter.com/marisakura/sta…
234
「対話しましょう」って言葉は、いつもいつも力を持ってる側から出てくる。被抑圧側でなくて。対話や多様性をうたう人や団体界隈での様々な加害事案や差別発言に触れる度に思う。対話は大切かもしれない。でも「対話しましょう」と言いたくなったら、まずその手の中のパワーの重みを味わった方がいい。
235
「社会はもっと厳しいぞ」は学校が子どもにルールを守らせるための常套句。社会を持ち出すのであれば「社会」で通用する価値観を教えてほしい。たしかに社会は厳しい、でもその厳しさから自分を守るための権利がある。学校ルールはただその権利を奪う。学校ルールほど「社会」に出て使えないものはない
236
でも彼らは「99回も言ってきたなんて嘘だ!聞いてない!不意打ちだ!」と言う。うん、だって聞こえていないんですもの。聞こえていないなら「無い」ことにされる。どこまでも平行線
237
人生何があるかわかりません。「シェルター入ったら生保要らない」と誤認されている方も、今後なにかのきっかけで住居がなくなり仕事もなくなるかもしれません。その時は躊躇なく支援を頼り、どこに住んでも生活保護という選択があることを覚えておいてほしいなぁと思います。
238
こうやって貧困がステレオタイプ化され「外車乗ってたり新しいスマホやゲーム機持ってたりおしゃれしてたら貧困じゃない」とか「貧困なのにそんなふうに見えてけしからん」っていう「本当に困ってる(ように見える)人探し」や「品行方正な困窮者探し」が始まって排除が進むんだと思う
239
「私は差別をしません」と言う人が増えても世の中から差別はなくならない。「私は差別をしてしまう」からその行動を抑制する手立てが生まれる。これ、学校の人権教育にまるっと欠けてる要素なんだよね
240
その後一度だけお誘いを受けて同じ店に入ったら、やっぱり店主が店員たちを怒鳴ったり激しく叱責する声がダダ漏れで。パワハラ店主が店員の勝手な判断を許すとは思えないからあの時私のメニューを勝手に変えたのは店主の指示だったんだろうな、なのに謝ることになった店員は気の毒だな、と思ったし
241
こども食堂運営者が「子どもの貧困問題に取り組んでいます」と自称し、それだけでなく「子どもの貧困」をダシに寄付を募り、またこども食堂にやってくる子たちへのスティグマを強化するような広告を、大手ニュースサイトに大々的に展開する。ちょっとこれ、許容できない
242
243
我々の現場、女性支援・困窮者支援の現場でもあるあるです。そしてそういう「助言」をする人たちもまた「世の中を良くするため」の活動や発信をしていたりする。関わらずにいられるのにわざわざ関わる姿勢を「善行」と呼ぶのかもしれない。でも関わらずにいららる特権を手放さず、特権に意識を向けずに
244
でもそこがちゃんと繋がらないと「誰かを助けたい(誰かを助ける自分になりたい)人たち」の願いが「当たり前の生活と権利の回復を必要としている人たち」の必要性に優先することになってしまう。それはきっと、彼らの願いにも反することになるだろうから。
245
多くの人にとって二次加害になりそうな中身だったのでシェアは控える。いじめの中身も開き直った態度も薄笑いする取材者の姿勢もどれもトリガーになるから。でも翻訳されて世界にばら撒かれて散々問題にされてほしいとも思う。加害を「やんちゃ」だと許容する風潮を葬るために。
246
「学校を休まない」ための健康じゃないんですよ、健康という土台があった上での学びであり教育なんですよ。
247
傷つけられ裏切られ続けてきた人たちと、ギリギリの条件環境で活動している私たち、その間のコミュニケーションにすれ違いや葛藤が生じることも多々あります。他団体についての訴えの中に明らかな暴力や搾取、権利侵害や違法行為なら然るべきところに調査を依頼すればいいしそうします
248
衝撃的で悲惨な事件が起きると反射的に「何か書かなくちゃ」「何か言わなきゃ」という気持ちになったりします。それはしばらく寝かせておいた方が良い言葉かもしれません。
249
私たちは「女性専用」のシェアハウスを運営してます。それは女性の安全のため。私自身女性として「安全を脅かされる」「住まいが見つからない」経験をしていますし、そういった女性たちの支援に長年携わってきました。だから女性専用です。なので身体的に女性でない方、そして中学生以上の男の子の→
250
そしてぜひ学校の先生方も生徒たちにまずそう問いかけてほしい。総合的な探求の時間を消化して終わり、AO入試でプレゼンして終わり、自分と切り離された「社会」に関心を持って終わりにならないために。それが「探求」だと思います。