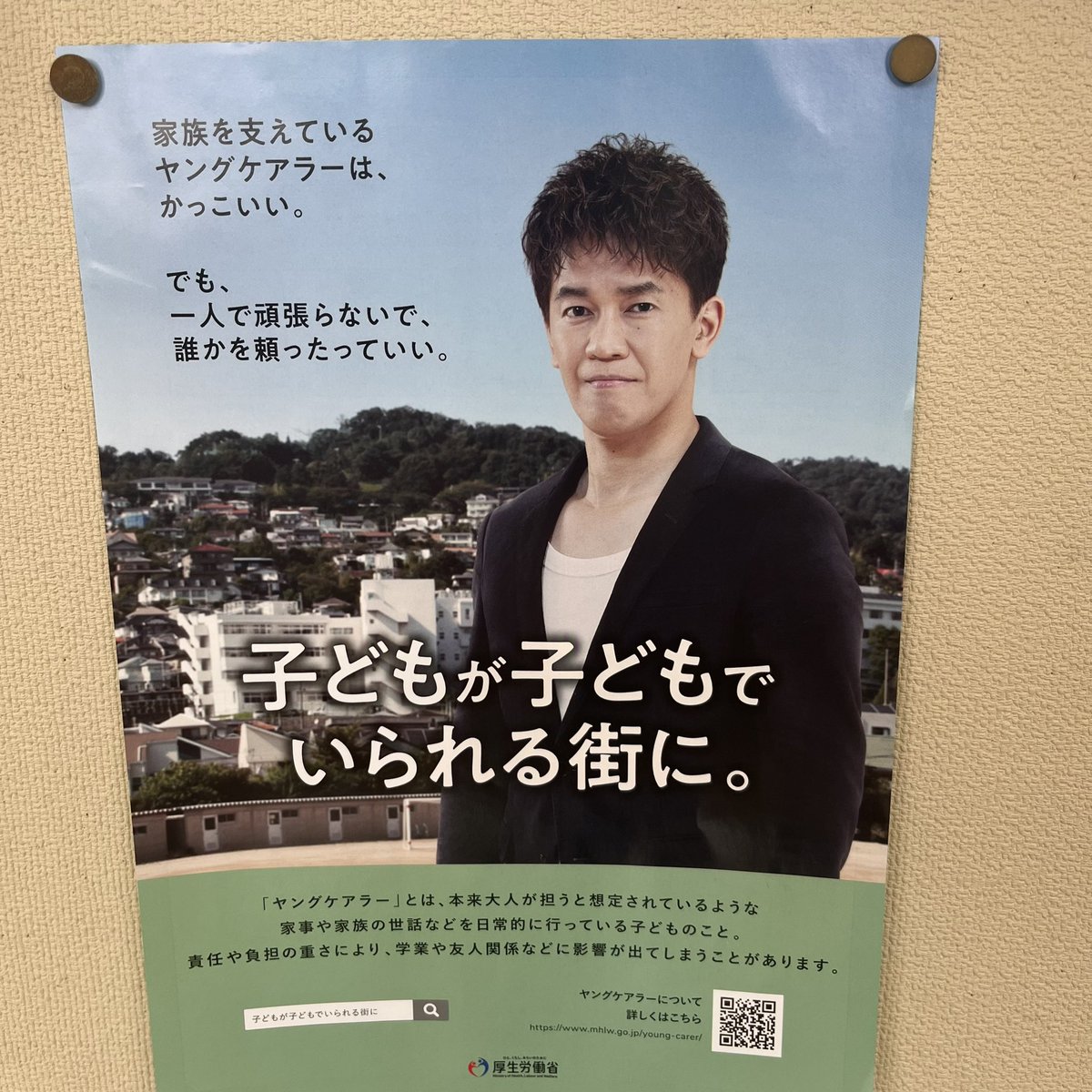376
そして生徒を家に泊める、愛車に乗せるといった行為は、例えそれが「善意」だとしても、それは「良い教師」の行いではありません。教師とは生徒という強弱のある関係性において境界線を踏み越えてくる行いは、たとえ「その子にとって」良かったとしても「良い教師」として評価されてはいけないものです
377
私も現場で、同じような「少しの逸脱」で家庭の中で苦しんでいる子どもたちを支えてきた先生方に出会ってきました。たしかにそれが必要な時はあります。でもそれはその時他に方法がなくて、やむを得ず選ばれた手段であり、そしてたまたま良い結果になっただけのことです。その先生たちの行いは→
378
結果として「子どもを助ける」ものになりました。ですが家に呼んだり泊めたり食事や物を提供したりプライベートで行動を共にしたりという行為は「良い教師の行い」として一般化されて良いものではありません→
379
同じ行いで子どもを苦しめることがあり、そして搾取目的で同様の行いをする悪質な例も存在します。逸脱に対して「良い教師の行い」というラベリングをすることは、苦しんでいる子たちの口を封じることになってしまいます→
380
#文春オンライン の記事は「美談」などではなく、子どもたちが「嫌だ」「おかしい」と言える機会と力を削ぐことに加担しています。抗議します。
381
子どもたちにあだ名や呼び捨てを禁止する前に、教師が生徒を呼び捨てするのを禁止してほしいんだけどな
382
会議である人の発言が妙に引っかかった。すごくおかしなことを言ってないのにモヤモヤした。しばらくして理由が分かった。「家庭」や「保護者」を全て「お母さん」と言っていたから。「お母さんとの連携を大切に」「お母さんと信頼関係を」「お母さんの関わりが大切」と。個別の事例ではなく一般論で
383
支援職が「支援につながる力のある人」の支援だけでいっぱいいっぱいだと隙間にこぼれ落ちてしまう人たちが見えなくなってしまう。市民活動に参加したり他団体の活動に加わったりできる余裕ある働き方が必要。そして「自力で支援につながれない人」にネガティブな感情を向けないために充分な報酬が必要
384
「私はそんな小さなこと気にしない」と言う人ね。あなたが気にしないでいられるのは、これまでの長い間誰かが気にして声を上げ続けてきたからだよ。
385
「可愛く/きれいに/かっこよく/美しくありたい」という願いとルッキズム批判は共存する。批判すべきは他者からのジャッジだから。でも「私が美しくありたい」という願いと「美しいと評価されたい」という願いの境界はひどく曖昧。私たちは幼い頃からあらゆる場面で「私は」の軸を奪われ続けてきたから
386
こども食堂は貧困対策じゃないし貧困対策にしてはいけないと繰り返し言ってるけど、やってくる子どもたちの声を聴き続けていると子どもを取り巻く様々な「政治の問題」に出会う。困窮もそのひとつ。だから私は政治に注文する。「政治には目をつぶって良いことだけしていたい」は、私にはできない
387
「本当に困っている人探し」をしてたらやがて誰もいなくなる。そもそもそんなことをする権限は誰にもない。だけど「本当に困っているようには見えない人」はいる。逆境は困っている人を「困った人」にしてしまうことがあるから。その場合お金や食料だけでない、他のレイヤーの支援が必要だったりする
388
日本には「みんな」はうんざりするほどたくさんある。でも「わたしたち」はほとんど無いように思う。
389
若年層の4人に1人が性被害
加害の最多は学校関係者
驚きも違和もない結果です。教師や同級生等からの卑猥な言葉かけが登校できなくなる理由(のひとつ)として子どもたちから打ち明けられることは珍しくありません。もちろん触られる等の被害も asahi.com/articles/ASQ6K…
390
小中学生の頃、親たちが「良い先生だね」という教師が苦手だった。エコひいきしたり抑圧的だったり理不尽な要求したり突然怒り出したり何が地雷になるか分からなくてビクビクしてた。だから怒られないように従い続けた。それが大人には「生徒に言うことをきかせられる良い先生」に見えたのかもしれない
391
若者の困窮は深刻。でもなぜ若者が困窮するか。彼らを育てた世代が困窮しているから。困窮が世代を超えてじわじわ拡大している。日本の政治は富を持つ側に向いている。若者だけじゃない、持たない中高年の側には向いていない。高齢者の困窮も相変わらず深刻だ→
392
最近インフルエンサーと呼ばれる人たちがしきりに「若者のための政治を」と発信しているけれど、彼らが「若者対高齢者」という図式を殊更に強調することに違和と危機を覚える。その対立構造は困窮を置き去りにする。見えなくする→
393
若者の政治離れを防ぐには?
私たちが若者のための政治を行う政治家を選べばいい。若者が政治から離れてるんじゃない、政治が若者から離れてるんです。さらに言えば若者ではなく「貧しい人」から離れてる。分断は年代の差によって起きてるんじゃない→
394
分断は年代の間で起きてるんじゃない。貧しい者、機会を奪われた者、努力できるチャンスに恵まれなかった者は、たとえ「若者」であっても、機会と富を持つ人たちの言う「若者のための政治」からはパージされるのではないか→
395
子ども若者のための政治の実現のためには「だれも困窮しない社会」の実現が必須。手薄な子ども若者・子育て世代への配分を強化するために削らなければならないのは高齢者のパイじゃない。富める側が持ちすぎている分。富の分布に世代による偏りはあっても、分断軸は年齢じゃない。間違えないでいたい
396
中絶の権利が覆された米国の判決。理不尽は突然降ってきたものじゃない、ひとりひとりの選択と行動の積み重ねの結果国の代表が選ばれ、判事が選ばれ、女性の安全と権利が奪われた。日本も同じ。たった1回の選挙、たった1回の選択、その積み重ねが私たちの権利を守ることもあるし、奪うこともある
397
福祉ってそもそも「つながり」が断たれた、つながりから置き去りにされた人たちのためにこそある。でも日本の福祉はむしろつながりに依存しようとしてる。「つながり」や「シェア」をキーワードに活動を展開する民間団体は多いけど、福祉のつながり依存に加担してないかセルフチェックが必要だと思う
398
メンタルヘルスって「こころの健康」が損なわれているというよりも「日常生活の中に不健康さ(困窮や暴力や抑圧や搾取や理不尽)」があってその影響が「こころ」に出ているんだと思う。だからカウンセリングルームや診察室の中だけで治療が完結するはずない
399
全てのケースがそうではないけれど、でも「不健康な状況に反応するこころはむしろ健康では」という視点って大事だと思うなぁ。その上で「不健康な状況(環境)」に様々な専門性をもって色んな角度から取り組んでいくこと
400