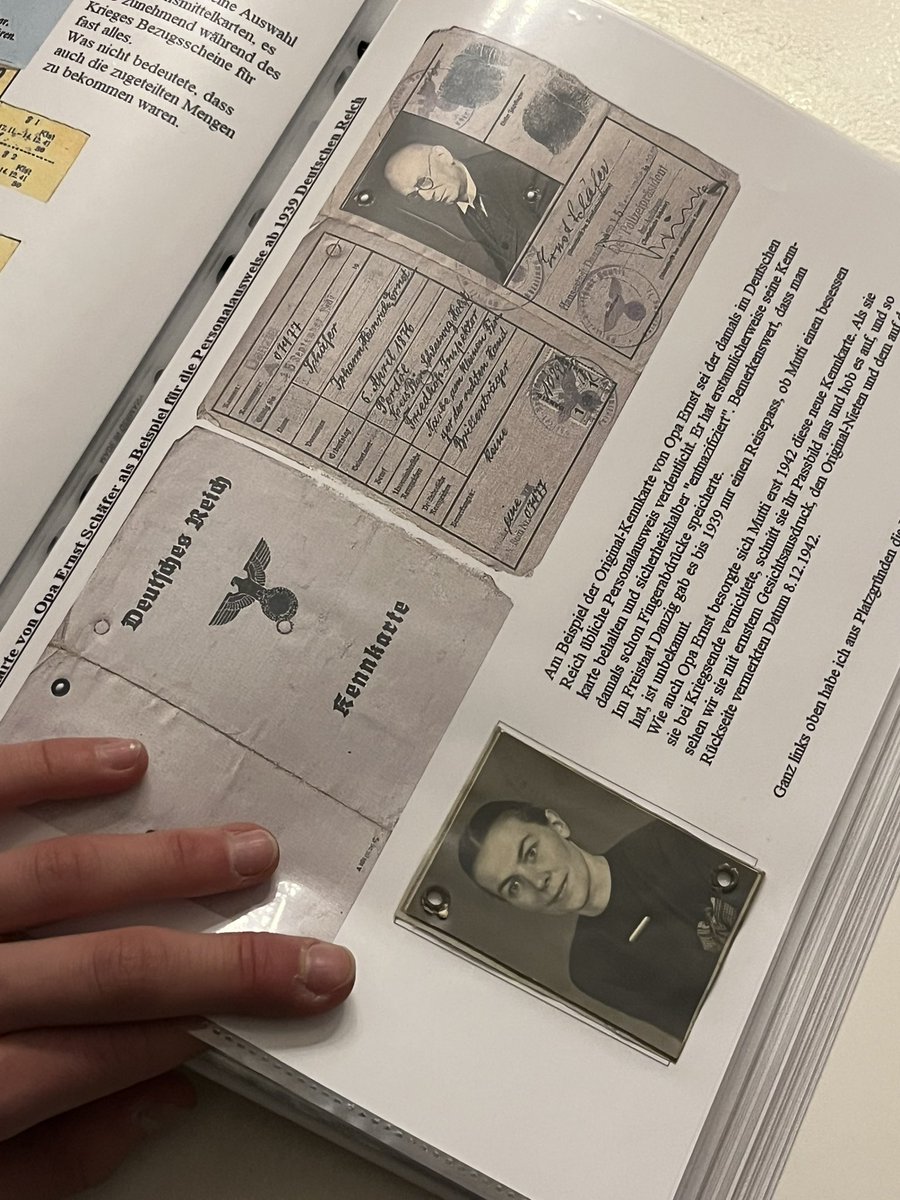1026
本物の教養人の強みというのは、
「極論で簡単に分断されない」ことだろうと思います。
その反面教師的な事例が最近目立ちすぎる。
1027
1028
③ウクライナ人の要求をフルサポートする。
④ウクライナ人の要求を基本的にサポートしつつ、武器援助は程々にする。
⑤ウクライナのEU加盟を早める。
⑥ウクライナのEU加盟は問題山積なので、慎重に考えるべき。汚職まみれの国なので。
要するに「そんなに簡単じゃねぇよ」というのがよく伝わる。
1029
美談的要素が日本の報道に比べて少ない。
また、特に⑥は日本のウクライナ戦争報道であまり直接触れたがらない点だが、これあってこそプーチンが「いけるんじゃね?」と開戦を決断した面もありそうなので、やはり重要と言える。重要で、しんどい。
これが「地続き」のリアリズムというものだろう。
1030
この番組を見ながら姉が「反戦デモに参加したいけど、最近は親ロシア派が乗っ取ることもあるから、そこがね…」と言っていた。
これはロシアと縁が深い人や情報エージェントばかりではない。新種のドイツ右派として知られるAfDも、最近は反EU以上に親ロシアの姿勢を強調するようになってきた。 twitter.com/marei_de_pon/s…
1031
ドイツの報道番組で特徴的なのが、専門家に対しキャスターが「ボク素人なんですけど」的にお伺いするのではなく「さあ、プロの見解を聞かせてもらおうか!」と議論的に聞き出す姿勢だ。
この「伝える・引き出す」報道技能によりスタジオに独自の緊張感が生じる。不明点をそのままにせずツッコむので。 twitter.com/marei_de_pon/s…
1032
【ロシア在住のバレリーナが日本のメディアの姿勢に疑問 「商品をよけて撮って」テレビ局からの依頼拒否】
news.yahoo.co.jp/articles/acdb1…
そんな依頼をしたら、拒否られた上にネットでバラされて炎上するんじゃないか、とか思わなかったんだろうか番組制作会社の人は。
思わなかったのだろうな。
1033
1034
1035
【「コオロギ給食」への批判が珍しく納得できる理由 昆虫だけでなく多岐にわたる“苦情の成分"】
news.yahoo.co.jp/articles/ca52d…
コオロギ食「推し」問題は当然ドイツ実家でも話題になったが、
「何それありえない。インパクトと意表を突く理屈で人心を掴もうとして失敗したのでは?」
という結論だった。
1036
コオロギ食推しの「推し」のムリヤリ感って、なんか凄く広告代理店ぽさが匂うんですよ。しかも、お金に余裕のあった時代のセンスを引きずってるというか。
そのへんも「反感が止まらない」一因ではないかと。
1038
「糾弾」の勢いと技巧ばかりがやたらと目立ち、誰かや何かを「守る」流れや感覚が、完全に遅れているというか後回しになっているネットの現状は良くないなとつくづく思う。
1039
お年寄りは、体力や運動能力に密かな不安を感じると、それを打ち消すように
「とくに衰えていない自分!」アピールのためことさら若々しく振る舞おうとすることがある。自らの老いを認めると「老け込んじゃう」と思っている。そういう人が免許返納したがらないんだ、という話を聞いてナルホドと思う。
1040
1041
【実質賃金4.1%減、1月で過去最大の下落 物価高響く - 日本経済新聞】
nikkei.com/article/DGXZQO…
この惨状を、政府与党および権力側言論はどうポジティブに言い換えるのだろうか。
1042
【ガーシー議員 あすに向け帰国しないと表明 “謝罪動画”を立花党首に預ける 「除名」処分濃厚】
newsdig.tbs.co.jp/articles/-/365…
世間をもてあそぶだけもてあそんでおいて、いざ行き詰まるとまったく責任を取らずに「頭だけ下げてみせる」タイプの個人や組織が目立ちすぎて困る2020年代です。
1043
【NHK党の立花孝志党首、辞任表明 政党名は「政治家女子48党」に】
news.yahoo.co.jp/articles/3e7fd…
この件の結末がどうあれ、
「政治パロディが政治のような顔をして影響力を発揮している」現状の構図を一種象徴するような話ではありますね。
1044
【イーロン・マスクの「ツイッター改革」から読み取れる「死ぬほど情報を喰わせる」社会路線の深層】
qjweb.jp/journal/83698/
無軌道、テキトー、思いつき優先! という見かけだけで判断してはいけない。最近のツイッターの「迷走」に見える箇所にこそ、実は将来の悪夢的生活感覚の一端が窺えるのだ。
1045
【コオロギ食論争に元農林水産大臣・山田正彦氏が警鐘「ゲノム編集の食品ってアメリカでは全然売れないんです。そんなものに日本は今、予算をつけてどんどん取り入れようとしているわけです」】
shueisha.online/newstopics/114…
「利権つながりでこそ企画が動く」政治的癒着構造の慢性化が問題の核心なのか。
1046
コオロギ食の安全性や意味については諸説あるわけですが、最近のコオロギ食推しムーヴに
「ひと昔前の広告代理店的センスにもとづくポジティブゴリ押し感」
があるのは明白で、その手のものを信用できるのかというのが生活の知恵としてまずあると思うのです。
1047
ワイドショー番組におけるWBCの、というか大谷翔平の「単なるネタ消費」ぶりを見せつけられると、あらためてSports Graphic Numberのような硬派スポーツ文化媒体の素晴らしさが痛感されてしまうのです。
#WBC2023
1048
Number読むと、ジャンルに限らずスポーツ記事を通じて知的滋養を得た実感があるのだが、ワイドショーのWBC特集を見ると知力が後退する予感がするのが凄い。
ヌートバーが素晴らしいのは「君が代を覚えた」からってワケじゃないんだよ!
1049
「ヌートバーのことを、そのルーツだけで語るのはあまりに惜しい」
「堅実で、インテリジェンスの高いプレーを見せるのがカージナルスの選手たちの伝統だ」
number.bunshun.jp/articles/-/856…
さすが文春Number、スポーツのエンタメ性の奥に潜む知的要素の掘り起こしで、並ぶものはない!
1050
異論はあるかもしれないが、こういう観点てメチャクチャ重要だと思うの。 twitter.com/yamayat/status…