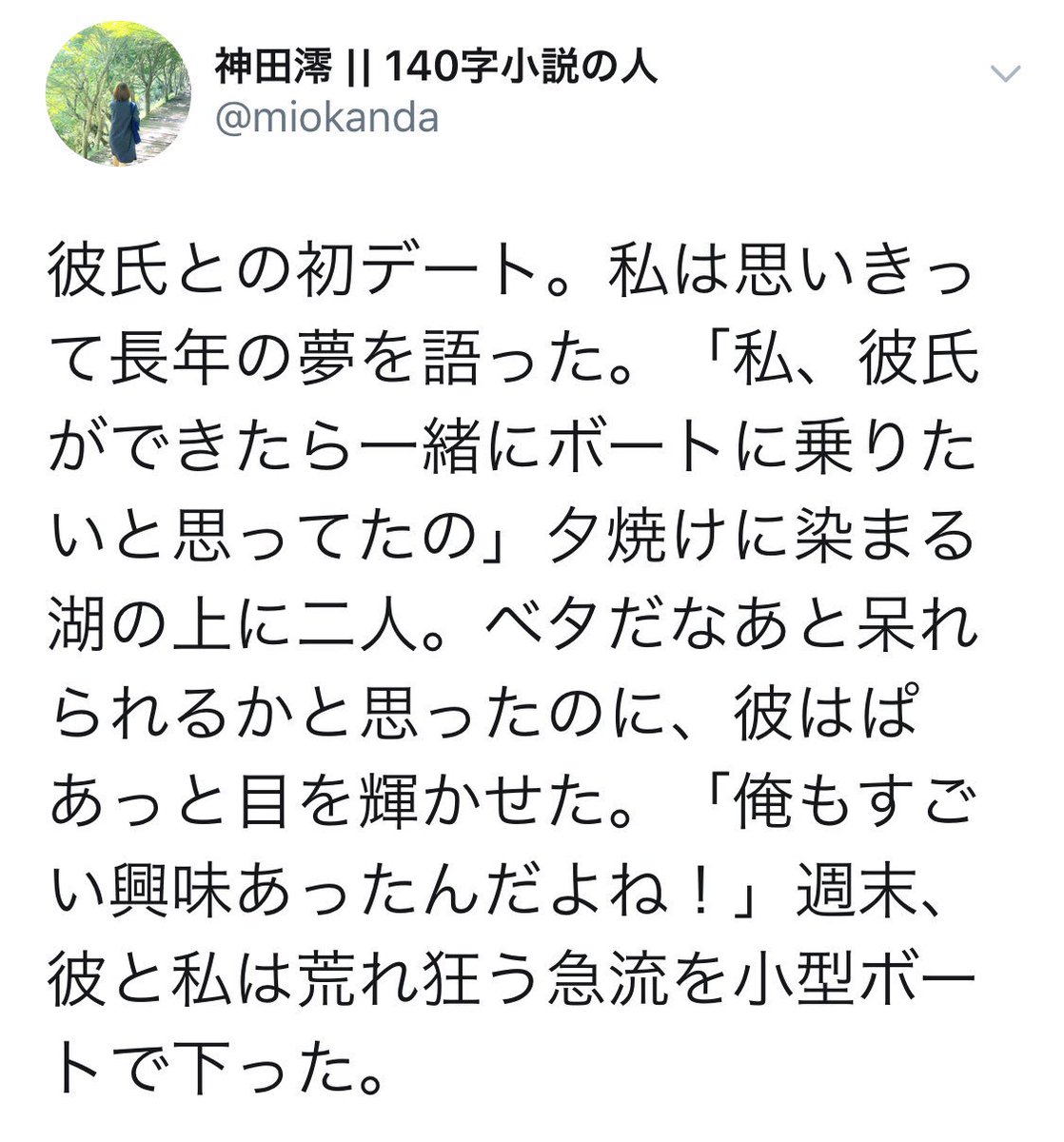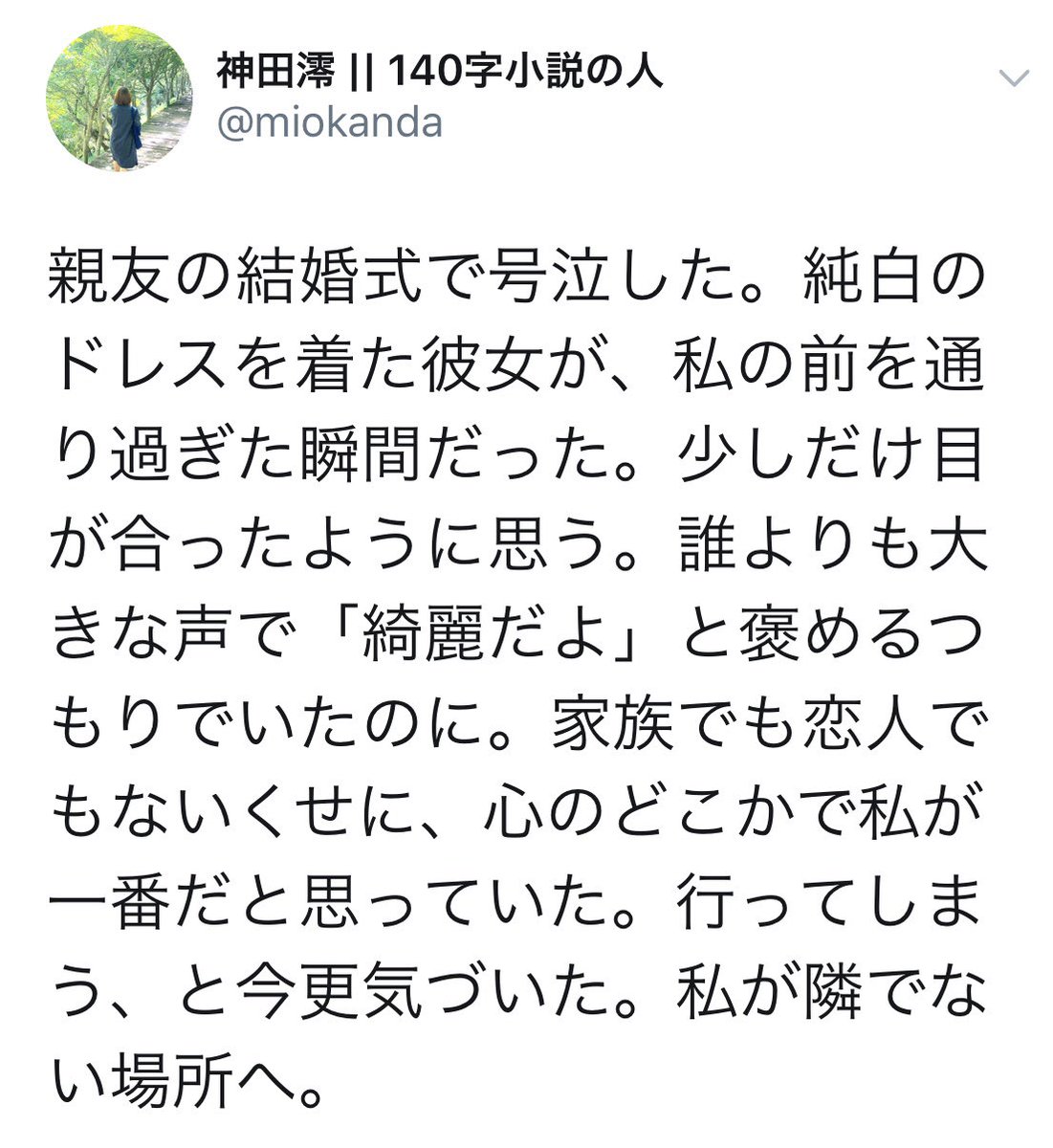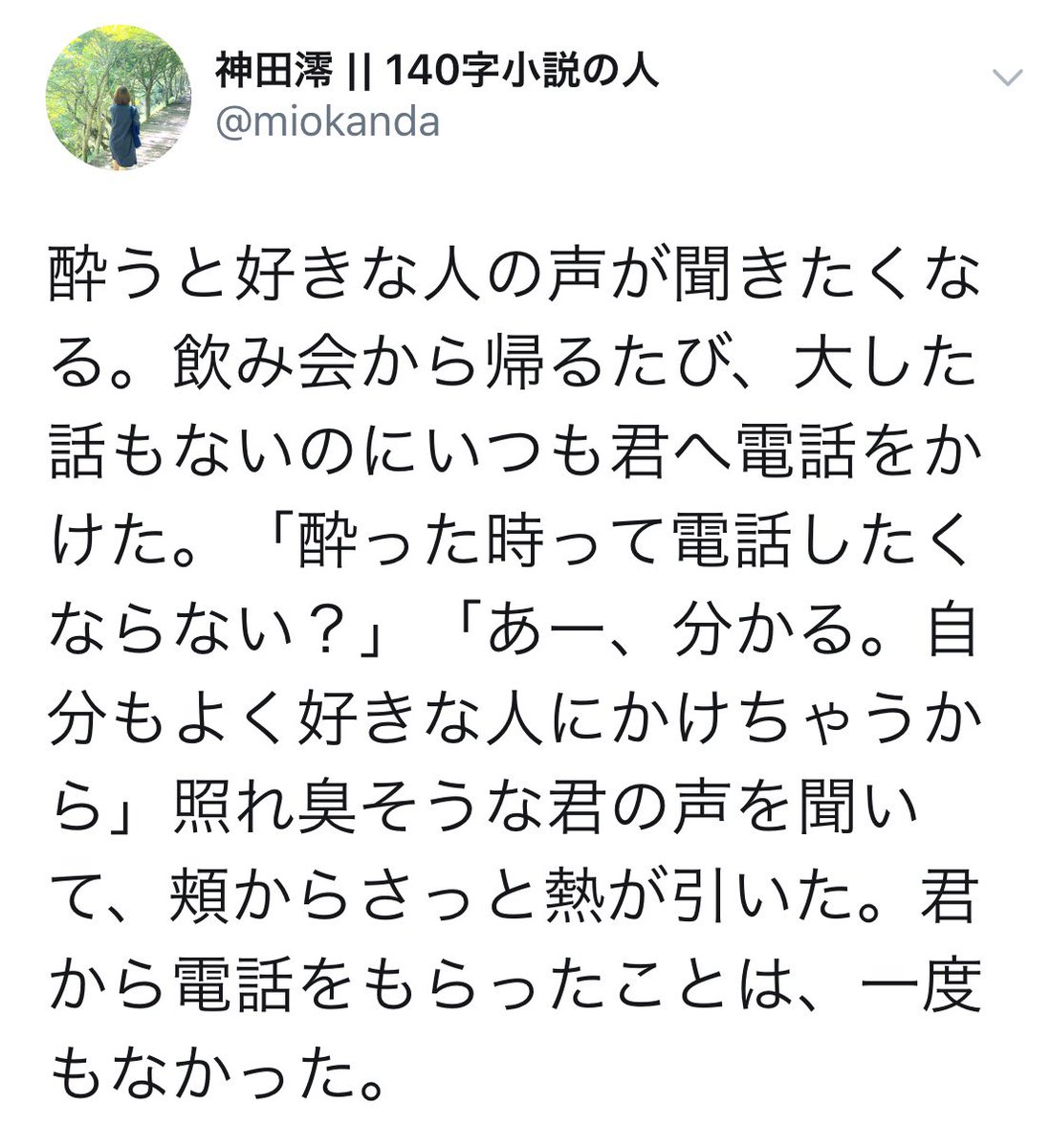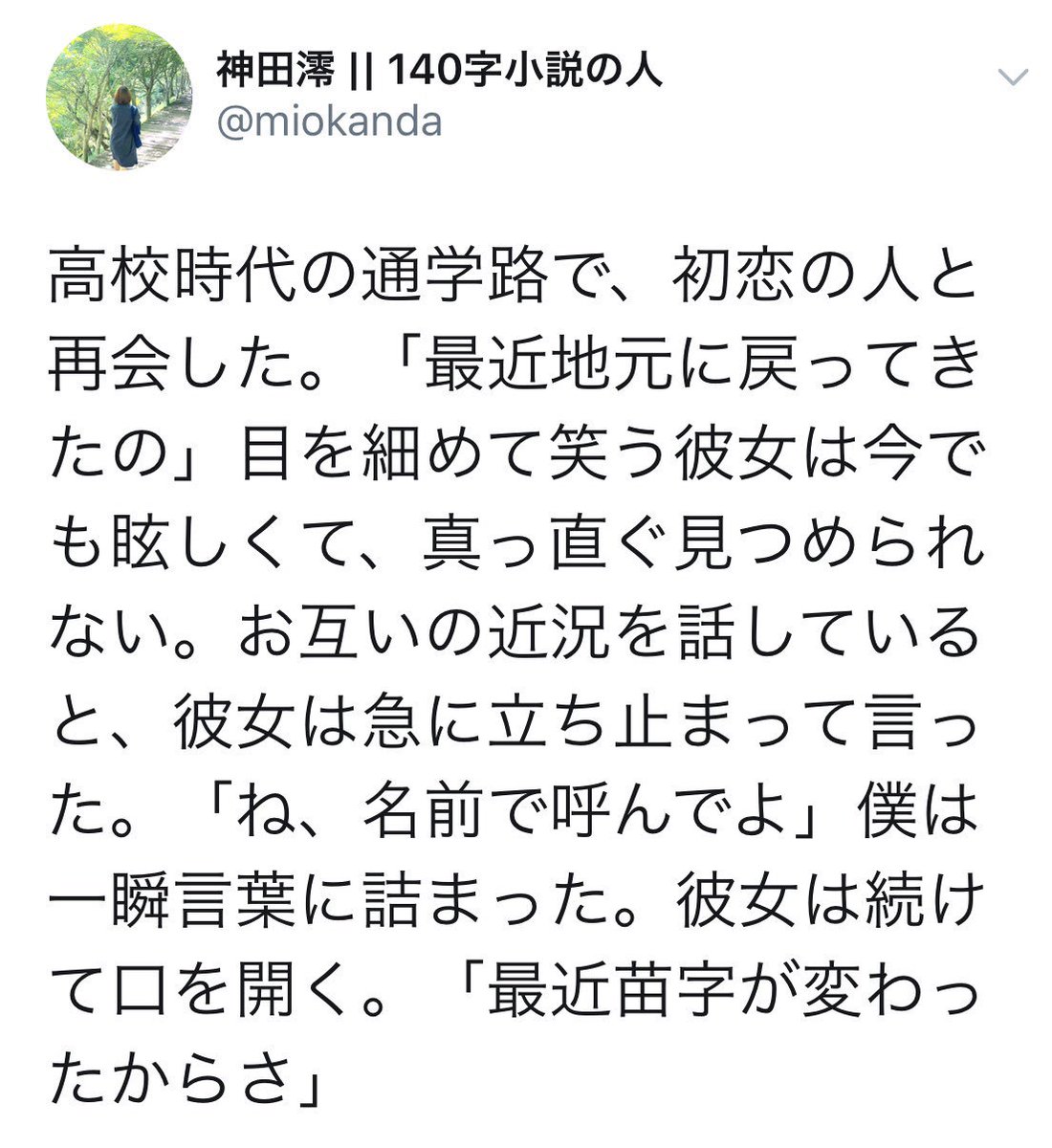276
「SNS何かやってる?」私が投げた質問に、彼は一瞬真顔になった。昼過ぎ、大学の食堂。「ちょっと待って」彼は鬼気迫る顔でiPhoneを触り始めた。さては元カノの写真を消しているのか。大人しく待っていると、彼の友達が席に走ってきて言った。「深夜の意味深ため息ポエム消したの!?好きだったのに」
277
寝る前に彼と電話をした。まだ温まりきらない布団を肩までかけて、天井を見つめながら。「今日は何してた?」「朝から勉強してて……」彼の近況を聞けるこの時間が何より幸せだ。「じゃあ、おやすみ」最後、彼は満足そうな声でそう言って電話を切った。これから私の一日について話そうとしていたのに。
278
私が好きになってしまった人は、省エネ人間だった。走っている姿を見たことがない。雨の日は外に出ないし、飲み会もさっさと帰る。そんな君を、土砂降りの雨の中、駅前で何時間も待たせる人がいる。「ごめんね。会議が長引いて」君はいいよ、と笑って私を迎えた。ああ、こんなの、好きになってしまう。
279
「私に彼氏ができたらどうする?」「え、泣く」幼馴染は白いシャツの袖で涙を拭うふりをした。そんな台詞はいくらでも言うけれど、彼に告白されたことはない。曖昧な関係のまま、十七歳になった。夏休みを待つ教室の片隅。「話があるんですが」放課後、彼の腕を引き寄せた。「ハンカチの準備はいい?」
280
夢に好きな人が出てきた。冬の遊園地で手を繋いで、輝くイルミネーションを見た。吐く息が白いってだけでなんだか面白くて、二人で何度も空気を真白に染めた。幸せだった。年の差なんて気にならないくらいに。一人の部屋で目が覚めると好きな人に会いたくなった。今はもう夢の中でしか会えないけれど。
281
夕暮れの事故が妻の命を奪った。あれから半年。家に帰るたびに涙した夜をこえ、前を向こう、と思い始めた十二月。会社から書類の訂正を求められた。僕は狼狽えて聞いた。「配偶者の有無、無にマルですか?」担当者は頷いた。指先が震える。妻はプロポーズを泣いて喜んだのに。僕の妻は、あの人なのに。
282
ヒーローとして戦うのが僕の仕事だ。その気になればこの星を壊せるくらいには強いが、万能じゃない。休憩は必要だし、地球の裏側で泣いている子には気づかない。けれどあっちを助ければこっちを助けなかったと非難される毎日。だから時々考える。楽になれるかな。怪物に振るう拳をこの星に向けたなら。
283
#平成の最後に自分の代表作を貼る
#140字小説
いつもお読みくださり、ありがとうございます。たくさんの反響をいただいたものをまとめました。
284
八年も付き合った君と別れたのに涙ひとつ出ない。むしろ朝日がいつもより綺麗で、聞き流す音楽が豊かに響く気がした。靴箱の奥からお気に入りのパンプスを取り出す。私はどこにだっていける、と思った。さよならを紡げないでいた唇が情けない。私の心はずっと前から、君と離れる準備ができていたんだ。
285
彼女と別れそう、と君が言った。私って性格悪い。嬉しいと思ってしまった。いつか振り向くかな。面倒だけど髪を伸ばした。趣味じゃない服装も、君の好みだからいつも身に纏った。ずるいけど本気の恋。桜が散る頃、君はそのまま結婚した。式場の隅では、見た目だけ君好みの私が、俯いて拍手をしていた。
286
LINEも電話もこっちから。最後に君からデートに誘われたのはいつだっけ。何かが欠けたまま付き合って一年が経った。「どうしたの?今日は静かだね」買い物中、少し先を歩く君が振り返る。答えられず俯いた。自分でも分からないんだ。昔は違った。愛の大きさが等しくなくても、こんな風に泣かなかった。
287
君は誕生日が来るたびに花束をくれた。カーネーションに薔薇、スイートピーに鈴蘭。驚かせるつもりだろうが、いつも車の後部座席に大きな包装が見えていた。不器用だけど正直な人。けれど今年の誕生日、後ろの席に花束はなかった。交際五年目。「もう、恋人はやめよっか」差し出されたのは指輪だった。
288
忘れられない言葉がある。傷つき、全てを失った私に友人が言った。「ここにいていいんだよ」それは優しくて、強い言葉だった。後になって思い知った。「ここ」を持つ人でなければ言えない。人を支える力がないと言えない。生きようと思った。いつか大切な人を、優しいだけではない言葉で救えるように。
289
朝からそわそわしていた。窓の外は曇り空。新品の可愛いルームウェアを隠すようにリュックに詰めた。「あのさ」洗い物をするお母さんに声をかける。「今日、友達の家に泊まってくるから」楽しんできてね、というその顔をまっすぐ見れない。私は変わってしまった。大好きなお母さんに嘘をつける人間に。
290
「お互い人気歌手になろうね!」桜の木の下でそう言って幼馴染と握手をした。大きな夢を胸に宿して。高校を卒業して幼馴染はすぐに成功した。「今作ってる曲、どう思う?」人気者になったあの子は今も時々デモ音源を送ってくる。東京でまだ何者にもなれない私へ。嬉しいはずなのに胸がチクリと痛んだ。
291
土曜の九時に通話しようと約束した。初めてできた彼氏。それだけで一週間頑張れてしまった。『ごめん。課題が忙しくて』LINEがきたのは夜の八時過ぎ。『分かった』が書けなくてスタンプだけ返した。あと十年もすれば懐かしくなるだけだろう、今夜のことも。布団の中で十五の私がこんなに泣いていても。
292
『泊まっていい?終電なくなっちゃった』深夜、片思いしている人からLINEが来た。泊まる?うちに?舞い上がらない訳がなかった。ベッドの上、まずは息を整える。部屋はそこそこ散らかっている。水回りも掃除して、後は……。考えているとまたスマホが鳴った。『他の子がOKしてくれたや。急にごめんね』
293
グラスにカルーアを30ml、ミルクを90ml。レシピ通りに作ったカクテルを口に含んだ瞬間、思わず顔を顰めた。僕には甘すぎる。甘いお酒ばかり残していった君に文句を言いたくなった。『うちに置いたお酒消費してよ』返事はOKのスタンプ。「わざと置いたの」と聞かされたのは、君が恋人になった後だった。
294
【本日予約スタート!】
『最後は会ってさよならをしよう』(KADOKAWA)
2021年1月21日に発売。
「140字の物語」をメインに、初の発表となる中編&エッセイなど書き下ろし多数。
いまご予約いただいた方に特別限定の特典🎁があります
↓のツイートをcheck!
Amazonで予約
amazon.co.jp/dp/4046049545/
295
「僕の好きなタイプ?」彼は照れた顔で言った。「うん。教えてよ」勇気を出してやっと聞けた。期待と不安が入り交じって胸の鼓動が高まる。「僕とは正反対の人かな」なるほどと頷くことしかできなかった。みっともなく泣いてしまいそうだった。「君と僕は似てるね」と言われて、昨日は嬉しかったのに。
296
SF小説の主人公に激しく共感した。こんな体験は生まれて初めて。パラレルワールドを彷徨う旅人の一生を描いた物語だった。主人公の生い立ちや性格が自分とそっくりで感情移入しやすかった。深夜、何度も頷きながらページを捲る。小説を全て読み終えてから作者と自分の名前が同じであることに気づいた。
297
「告白されたら誰とでも付き合うよ」学校帰り、君のそんな言葉を聞いてから、眠れぬ夜が続いた。もし他の子に告白されたら。そもそも、こんな軽い人と上手く付き合える自信もない。ついに君の親友に相談を持ちかけると、彼は驚いて言った。「え?あいつ、好きな子じゃないと嫌だって言ってたけど……」
298
「彼女の誕生日にサプライズを用意したんだけど」職場の昼休み。やはりモテる同僚は違うなと思いながら頷いた。「当日、フラッシュモブを依頼してさ。でも彼女、そういうの嫌いだから振られたんだ」「それは失敗だったね」彼は笑いながら首を横に振った。「穏便に別れたかったから、あえて選んだんだ」
299
キッチンに立つたびに昔の恋人のことを思い出してしまう。大げさに褒めてくれるから、いつの間にか料理が好きになった。本当は面倒臭がりだったのに。置きっぱなしだった服も歯ブラシも処理したけれど、思い出は戸棚の中に詰まったまま。ばかだなぁ私。一人じゃ使わないのに、こんなに調味料を買って。
300
「恋人ができたんだ」信号待ちで君は早口に言った。昼下がり、強い日差しが肌を焦がしていく。「ふーん」心配そうな君の顔を見て、恋人ができた嬉しさで報告したのではないと確信した。どうしても祝ってほしいのだ。「おめでとう」許すように呟く。信号が青に変わり、先月告白したことをまた後悔した。