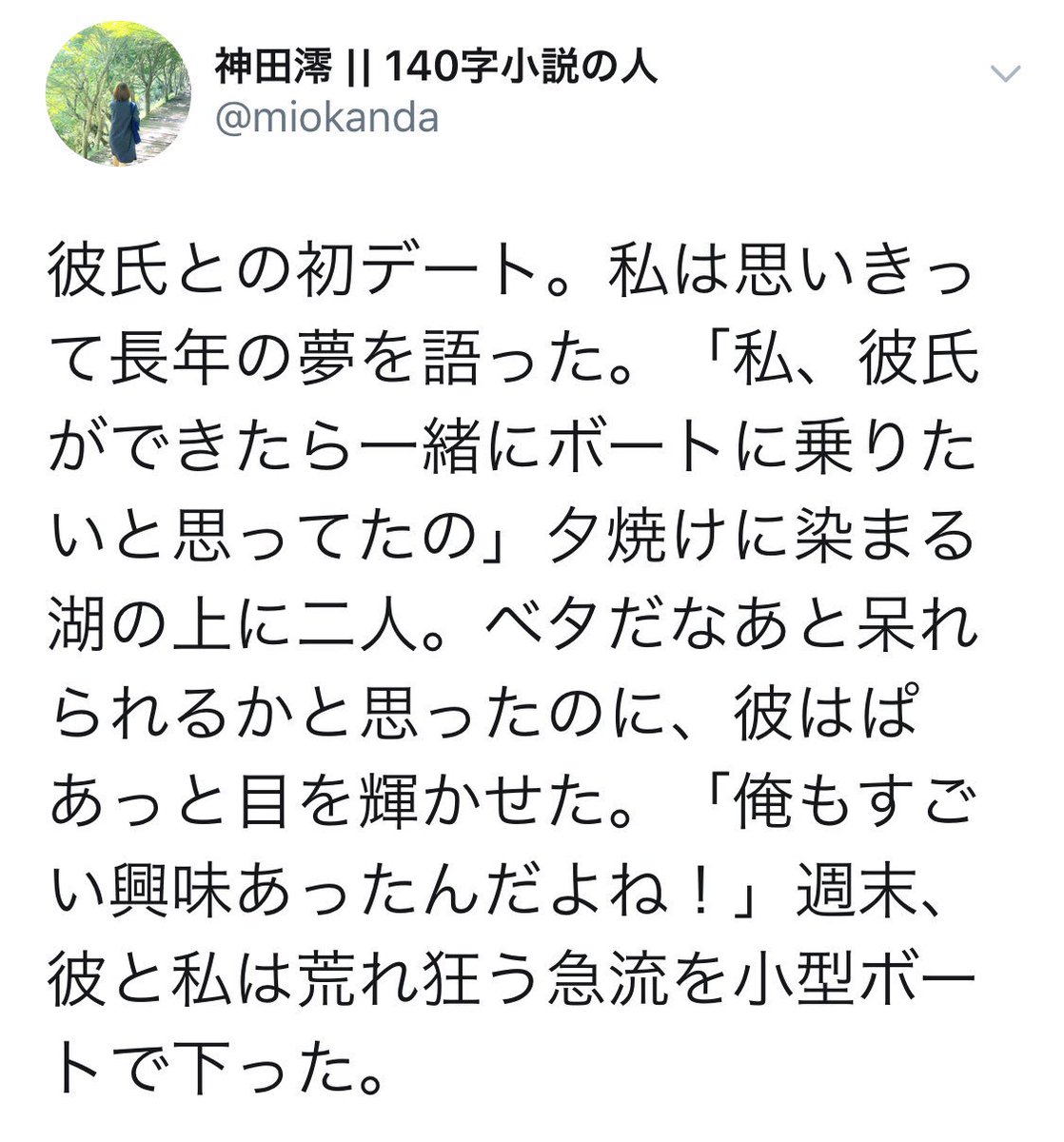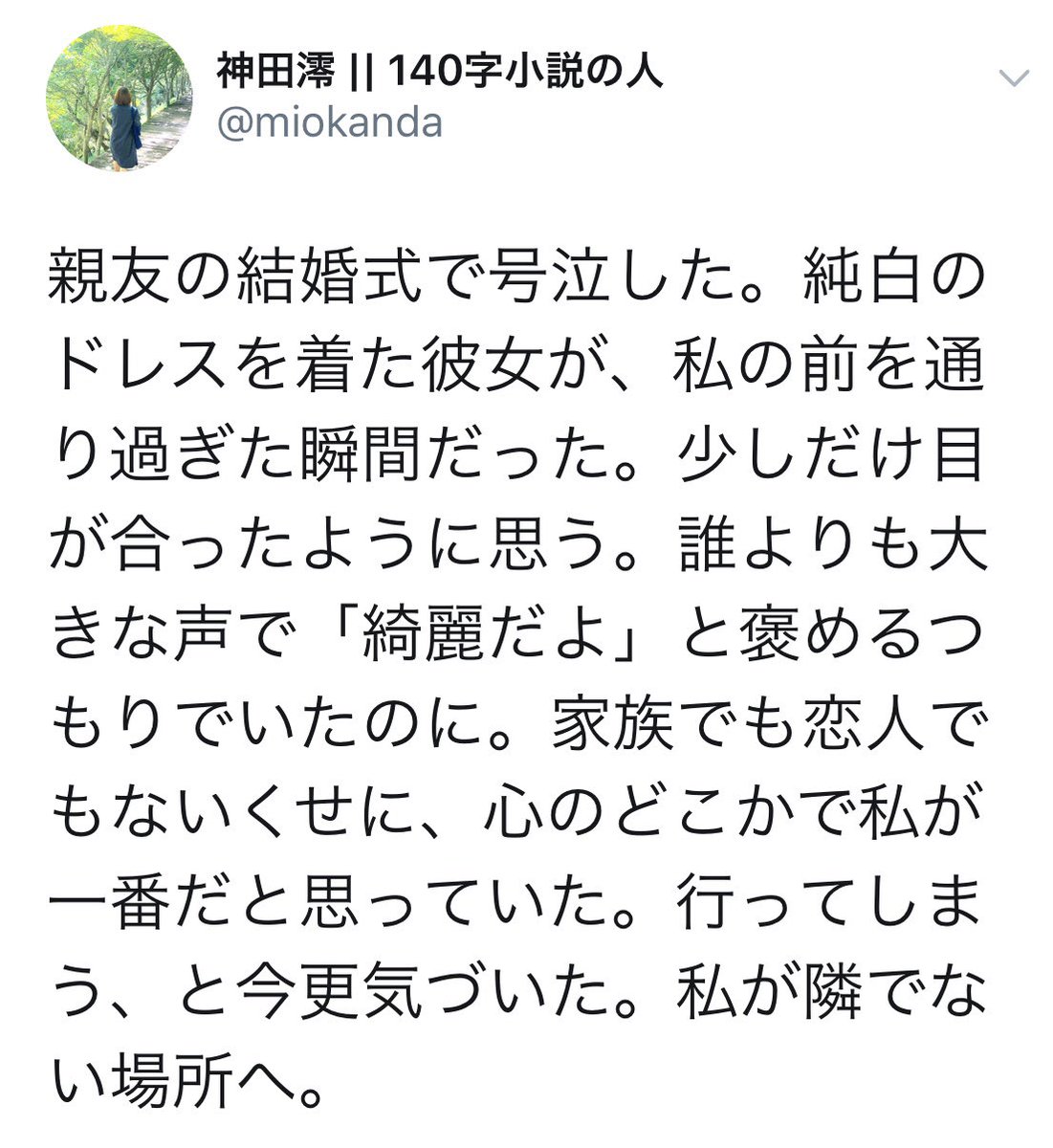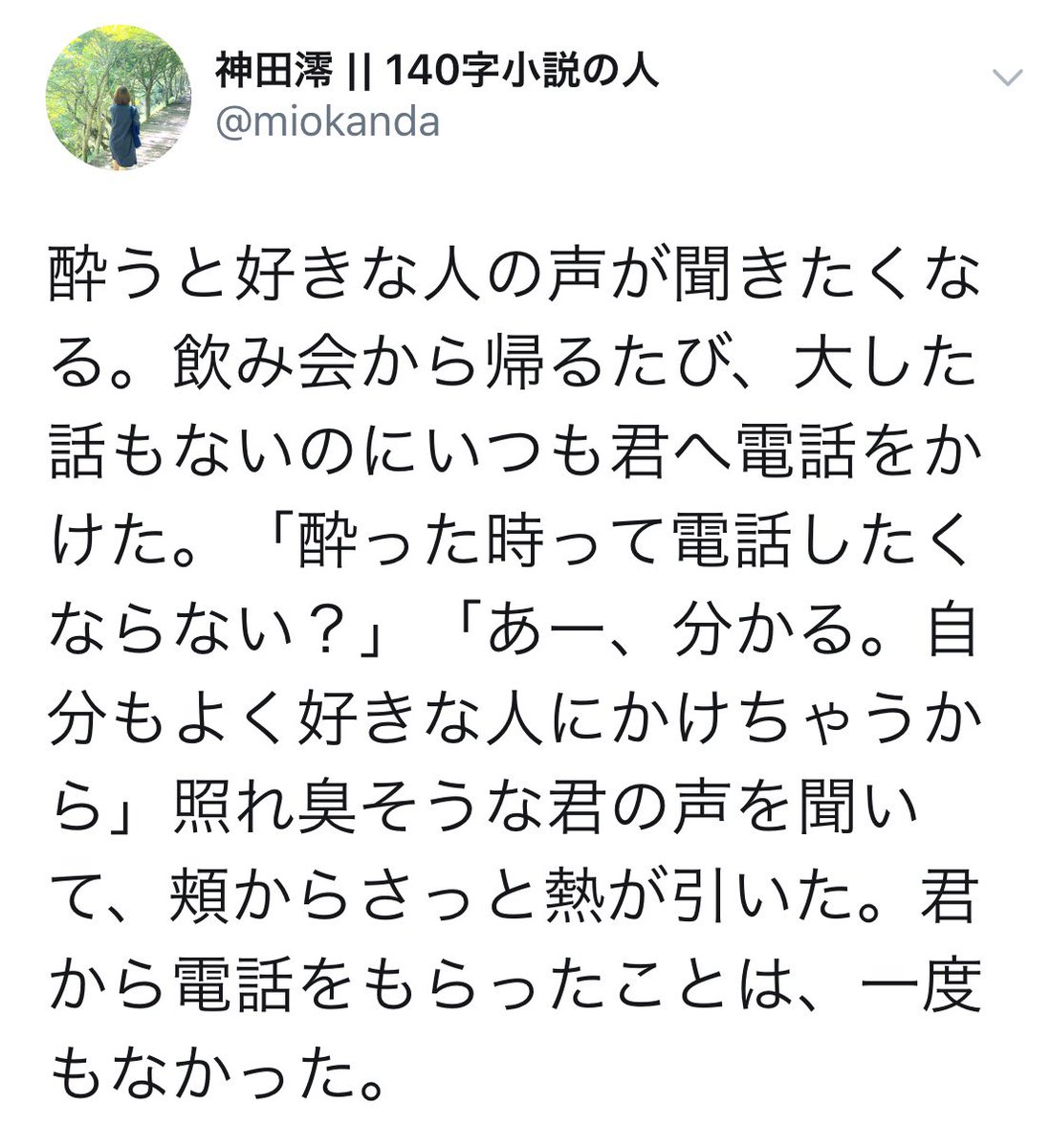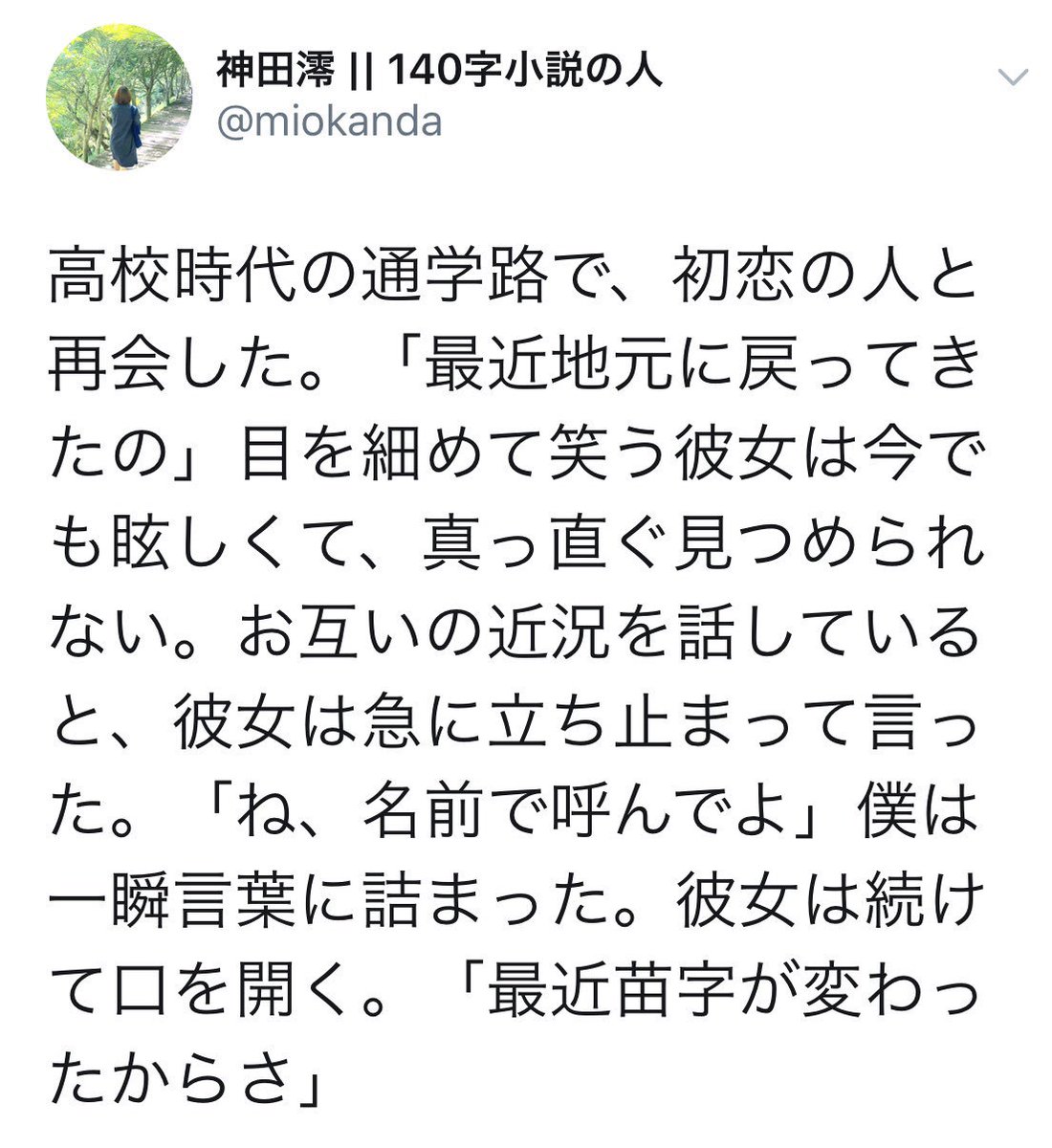1
朝、瞼を開けた彼はまだ眠そうだった。「よく寝た」呑気な顔で欠伸なんかして。私は親指と人差し指の腹でその頬を摘みながらほんとだよ、と笑った。「ごめん、もしかして出かける約束してたっけ?」「うん、そうだったね。今思い出したよ」そこから先は声にならなかった。彼が目覚めたのは二年ぶりだ。
2
ずっと好きだった人に恋人ができた。まったく騙されたような気分だ。恋愛には興味ないかな、といつも言っていたのに。昔から遅刻癖があるから心配だけれど「相手の子は気が長いから大丈夫」なんて君はいい気なものだ。今日も「5分遅れる」と通知が来る。まあ確かに、5年に比べれば5分なんて一瞬だ。
3
高校時代の通学路で、初恋の人と再会した。「最近地元に戻ってきたの」目を細めて笑う彼女は今でも眩しくて、真っ直ぐ見つめられない。お互いの近況を話していると、彼女は急に立ち止まって言った。「ね、名前で呼んでよ」僕は一瞬言葉に詰まった。彼女は続けて口を開く。「最近苗字が変わったからさ」
4
2018年 #140字小説 まとめ 第1弾
今年は広告風にまとめてみました。
5
「彼女の誕生日にサプライズを用意したんだけど」職場の昼休み。やはりモテる同僚は違うなと思いながら頷いた。「当日、フラッシュモブを依頼してさ。でも彼女、そういうの嫌いだから振られたんだ」「それは失敗だったね」彼は笑いながら首を横に振った。「穏便に別れたかったから、あえて選んだんだ」
6
「好きな人いる?って、ほぼ告白だよね」お喋りが止まらない私とは対照的に、幼馴染はゲームに没頭中。ボスを倒すので忙しいそうだ。「聞いてる!?」「うん」絶対嘘だ。私は諦めて本棚から漫画を取り出した。5分後、ゲームを終えた彼は隣に腰掛け、不機嫌そうに言った。「まさか好きなヤツいんの?」
7
君が告白の返事を迷っていたから、つい言ってしまった。「付き合ってください。一週間でいいから」期間限定でも幸せだった。何度も作り直したクッキーを君が美味しいと喜んでくれて。寝る前にはおやすみと送り合って。それでも最終日は来る。「もう無理」君は頭を抱えた。「こんなん、好きになるやろ」
8
大好きな人がいた。この人と結婚するんだと信じて疑わなかった。可愛いスカートを買ったのも、いくつものヘアアレンジを覚えたのも、その人と付き合ってから。別れたとき、このまま死ぬのも悪くないな、と思った。「他に好きな人ができた」一番悲しいさよならの理由を口にしたのは、三年後の私だった。
9
パパには人に言えない趣味がある。15歳の夏、私は偶然その秘密を知った。タンスの奥、スラックスの下に隠されていたのは、フリル付きのワンピース。一体いつ着ているんだろう。試しに袖を通してみたある日、パパが急に帰ってきた。「マジかぁ」その目には涙が。生前、ママはよくこの服を着たらしい。
10
沈黙が続く深夜のファミレス。悩んでいた様子の彼女がついに口を開いた。「もう終わりにしよう……」僕はため息をついた。「誘ったのはそっちだろ」「ごめん。でも、もう冷めちゃったから」僕は何を見落としていたんだろう。諦めきれずに黙ったままでいた。まったく、この店の間違い探しは難しすぎる。
11
この子は僕のことを信用しすぎだ。「ねえ、好きになったきっかけとか書いた方が良いかな」クラスメイトは真剣な眼差しでシャーペンを動かしている。「その方が良いんじゃない」ラブレターの添削なんて、絶対向いてないのに。「ごめん、最後の質問」彼女は手を止めた。「あんたの苗字ってどう書くの?」
12
「SNS何かやってる?」私が投げた質問に、彼は一瞬真顔になった。昼過ぎ、大学の食堂。「ちょっと待って」彼は鬼気迫る顔でiPhoneを触り始めた。さては元カノの写真を消しているのか。大人しく待っていると、彼の友達が席に走ってきて言った。「深夜の意味深ため息ポエム消したの!?好きだったのに」
13
「ねえ、チョコ好き?」やっと聞けた。同じ弓道部の彼は、横にいる私をちらりと見ながら答えた。「大好き」珍しい笑顔にこちらがどきりとしてしまう。「良かった。甘いもの食べないって聞いてたから」彼は不思議そうな顔をした後、急にその場でうずくまった。「好き?の部分しか聞こえてなかった……」
14
彼女が亡くなってから五年が経った。泣き崩れ、空っぽな頭でトーク履歴ばかり見ていた僕も、もうすぐ大人になる。この冬、新しい恋人ができた。優しい君のことだ、きっと空から祝福してくれているだろう。君が遺した手紙を読み返した夜、僕は消された文字の跡があることに気づいた。「私を忘れないで」
15
推しはいても彼氏はいたことがなかった。そのせいか、ここ最近は驚きっぱなしだ。「その髪型可愛い」課金もしていないのに褒めてくれる。こんなにファンサを貰っていいのか。ツーショット撮り放題、無料。遠征するどころか会いに来てくれる、当選確実イベント。どこにお金を注げばいい、恋愛は難しい。
16
人の寿命が見える。この妙な能力のせいで、私は恋人と長続きしたことがない。好きになればなるほど、その数字を見るたびに泣いてしまうからだ。けれど「一目惚れです」と告白してくれた君の寿命は見えなかった。運命の人だ、と思った。初めて会った日の夜、真夜中の事故は君の命を連れ去ってしまった。
17
生まれて初めて年下の彼氏ができた。人懐っこくて、素直で、思わず可愛いねと撫でたくなってしまう。その話を聞いた親友は、神妙な面持ちで口を開いた。「彼氏に可愛いって言わない方がいいよ」そうか、相手にとっては嬉しくないのか。彼女は続けて言った。「私の彼氏、私より可愛くなっちゃったから」
18
私には好きな人がいる。たとえ、彼が他の誰かを愛していたとしても。「もう一度好きになってほしいんだ」前の彼女の話を聞くたびに、絶対に勝てない、と思い知って涙した。季節は巡る。ある日、彼は事故で亡くなった。彼の母は俯いて声を震わせた。「記憶を失う前のあなたは、この子の彼女だったのよ」
19
五年付き合っているけれど、ペアのものは何も持っていない。君は恥ずかしがり屋なのだ。けれど一つくらい、と思う。誕生日の前日、それとなくアピールしてみた。「何かお揃いにしてみたいね」君は自慢げに頷く。「用意はしてる」深夜十二時、渡されたのは婚約指輪だった。「お揃いのは二人で選ぼっか」
20
#平成の最後に自分の代表作を貼る
#140字小説
いつもお読みくださり、ありがとうございます。たくさんの反響をいただいたものをまとめました。
21
「ねえ、私のこと好き?」焼酎で酔った彼女はソファで横になりながら言った。僕はもちろん、と返事をした。しかし彼女は質問をやめない。「料理下手なのに?」「うん」「がさつなのに?」「うん」彼女は真顔になった。「それってさぁ」悪趣味だと言われるだろうか。「私のことめっちゃ好きじゃん……」
23
「見て見て」大学帰りの彼女が見せてきたのはスマホの壁紙。そこには俺の顔が大きく映し出されていた。「没収アンド削除」「あー!」既に何度も取り上げているのに懲りないやつだ。散々格闘した末、壁紙はベージュ一色に再設定された。「やっと別の画像にしたか」「ううん。眉間を拡大した」「やめろ」
24
好きだと気づいた頃には、もう手の届かないところにいた。春の終わり。諦めたいのに、君は私にばかり恋愛相談をする。「また彼女の話?」何度目かの呼び出しで、君は首を横に振った。「今は彼女いないよ」その言葉を聞いて、押し殺していた感情が苦しいほどに溢れてきた。「私……」「妻ならいるけど」
25
「告白されたら誰とでも付き合うよ」学校帰り、君のそんな言葉を聞いてから、眠れぬ夜が続いた。もし他の子に告白されたら。そもそも、こんな軽い人と上手く付き合える自信もない。ついに君の親友に相談を持ちかけると、彼は驚いて言った。「え?あいつ、好きな子じゃないと嫌だって言ってたけど……」