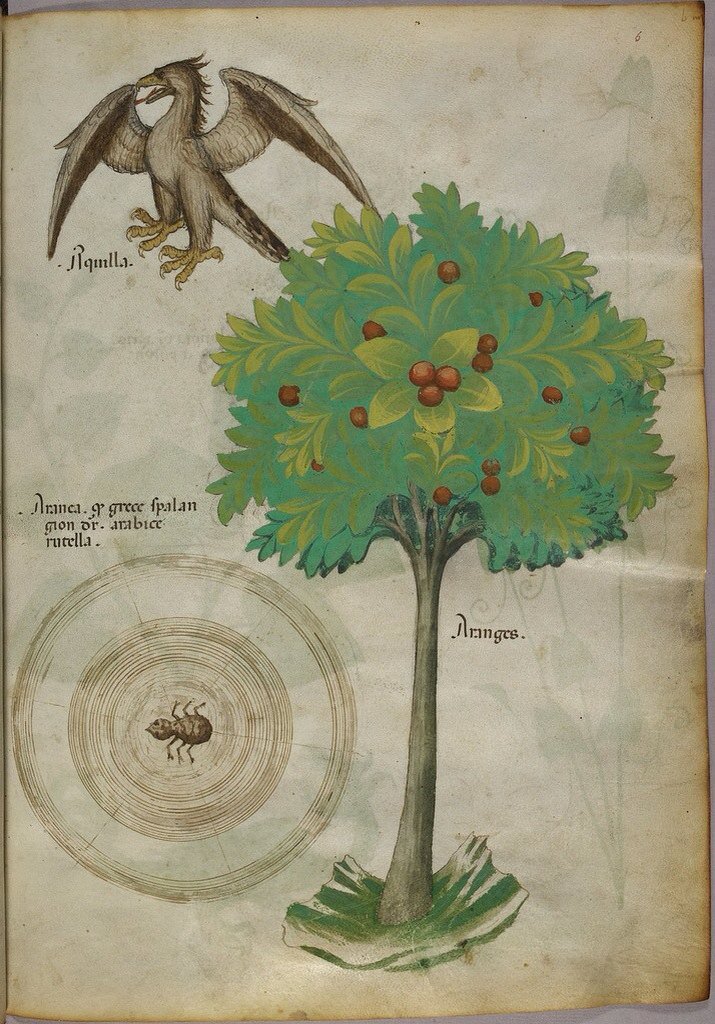251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
イバン バレネチェア著「ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑 」amzn.to/2zUhTHQ 19世紀の自然哲学者ボンバストゥス博士が語る植物たちはどこか子供の頃聞いたことのある植物ばかり。もちろんボンバストゥスなんて学者は存在しない。絵本の世界で遊べる人たちには、どうぞ。
269
270
271
272
273
274
275