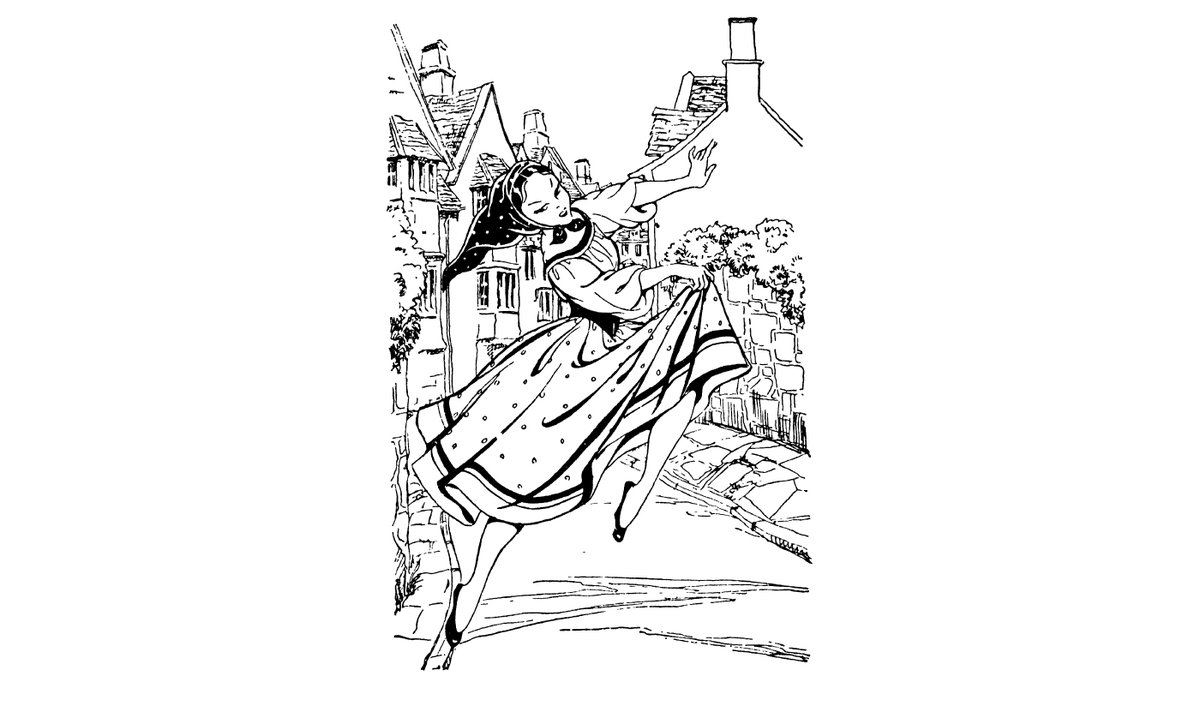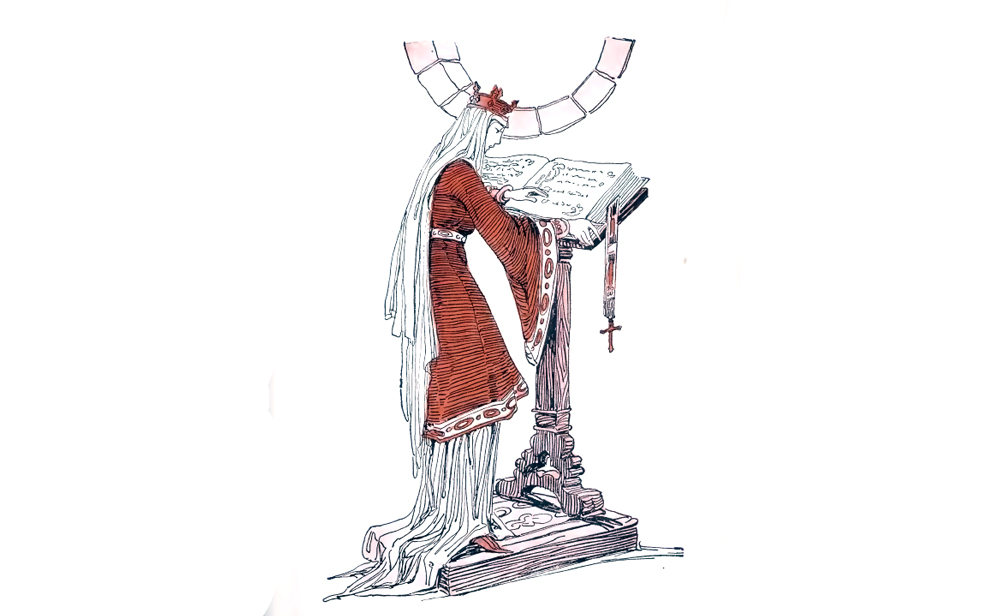1476
--悪魔は神父を見て激高し、そのまま遁走してしまいました。かくして悪魔の布とスーツがこの世に残ってしまい、いろいろと不思議な話が始まるのであります。ある種の聖遺物の口上か、あるいは魔法の服の伝来話か。ちなみに悪魔の服は派手なストライプが多いとされています。根拠は不明。
1477
1478
ーーたまにペットで持ち込まれた個体が逃げて見つかったりすると教会まで巻き込んで黙示録的騒動になったとのこと。ガマガエルも同じく棲息していないのですが、こちらは持ち込まれた外来種が繁殖しつつあって問題視されています。
1479
雑。とある英国海軍艦長が1795年4月に「海戦における臆病行為」の容疑で軍事法廷で有罪とされた事件がありまして。その艦長の行動が実は「呪い」によるものとの説が流布したのであります。いわく艦長が一方的に婚約を破棄して別の婚約者に乗り換えた際、前の女性から呪われたのだとーー
1480
1481
チェンバースによれば、昔はイースターでも「トリックオアトリート」を行っていて、ハロウィンのそれよりもずっと荒っぽかったそうです。ワルガキどもが「お金をくれなきゃ靴をもらう」と通行人を取り囲み、6ペンスばかし要求します。断ると靴を持っていかれます。19世紀前半には廃れたそうです。
1482
1483
この短編が掲載されていたのは『ウィー・ウィズダム』誌1925年3月号。日本の少女がワシントンに向かうという設定は日米人形交換交流事業を思わせますが、こちらが始まるのは1927年。むしろこの種の物語が人形交換のヒントになったのでは、と。
1484
1485
ーーお屋敷に出没する修道女の幽霊といった伝承には十分に裏付けがあったとのこと。場所の記憶なのか、そのまま亡くなった人の「残念」か。英国におけるカトリック弾圧は17世紀になっても収まらず、19世紀前半まで尾を引いたそうです。
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500