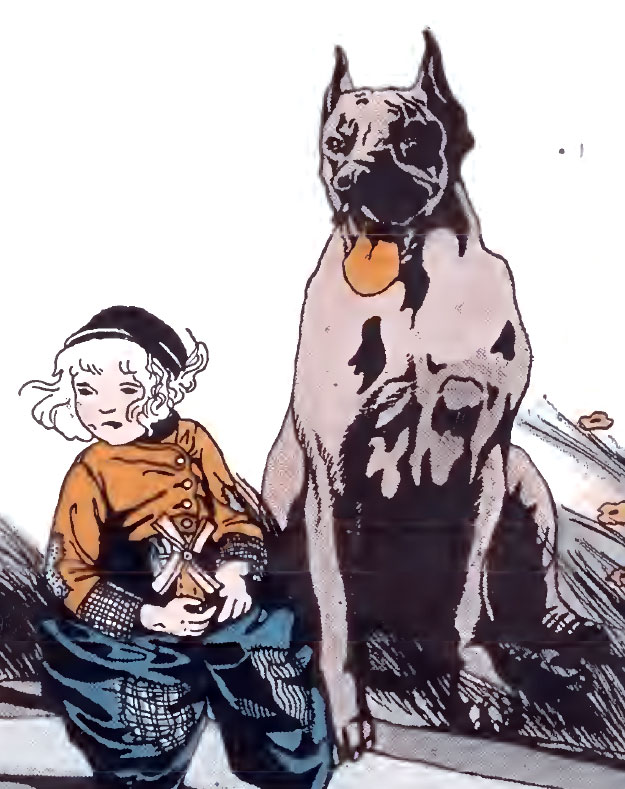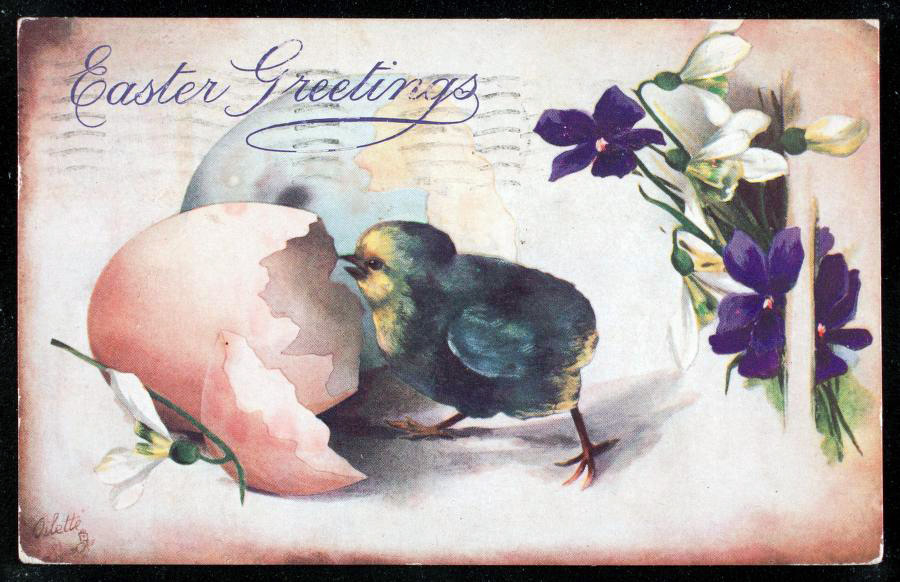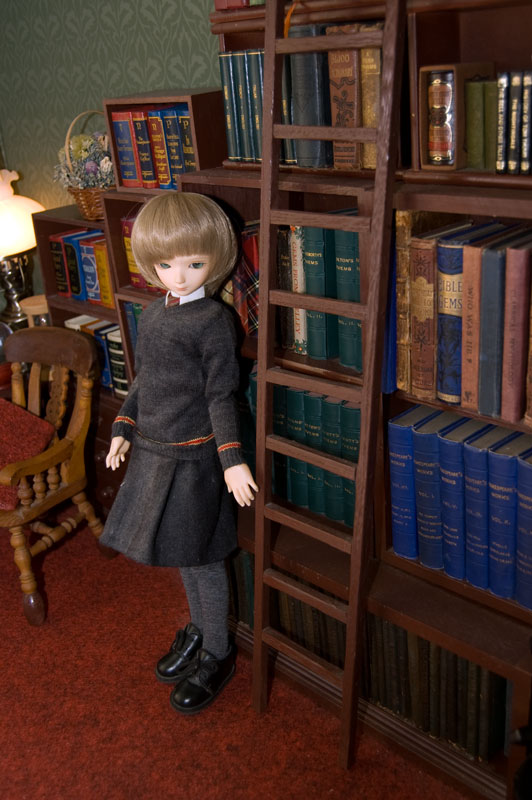726
727
728
729
#小さいころ勘違いしてたこと選手権
成仏とはフランス人になることだと思っておりました。
730
731
732
733
734
刃物を貰う際は銅貨の一枚でも渡して購入した形式にするとのこと。借りたナイフを返す際のジョークは「隣の空き地にーー」レベルでよいそうです。ゆりかごの底の部分にナイフを取り付けて妖精よけにする話もあります。
735
736
737
738
739
740
ゆえにーー
貴婦人「きっとあなたには緑のガウンが似合いましてよ」
といったセリフもかなり怖いのであります。白では露骨すぎるわけです。面白や、と。
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750