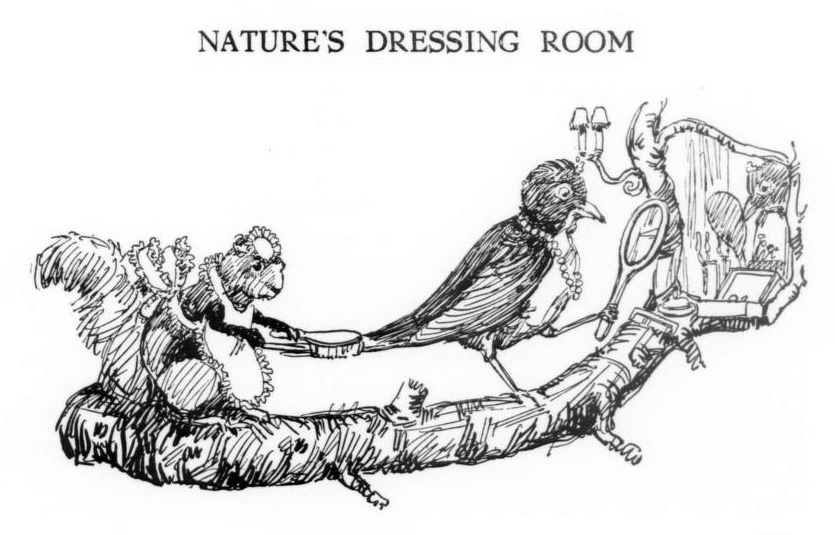576
577
578
579
本日は #うさぎの日 でもあるとのこと。
スコットランドの魔女はノウサギに化けるとされておるのです。月光のなかでじっとたたずむノウサギがいて、つかまえようとする子供がいるわけですが、どちらがつかまるのかわかったものではありません。絵はデラメアのダンダンデリーの書からラスロップ作。
580
581
本日はテディベアの日とのことなので遅ればせながら再掲。何事も怖くしようと思えば怖くなるのであります。 twitter.com/MuseeMagica/st…
582
#天使週間
天使の剣はフランベルジュというトピックがありましたが、あれはもっぱら対人用のようです。悪魔相手になると槍や片手剣を描く例が多く、使い分けがされているのであります。聖書の記述と絵画制作上の約束事は両立するのか。興味深いのであります。
583
#ビスケットの日 だそうで。
伝承にある「魔法のビスケット」はたいてい「いくらかじってもなくならない」糧食系で味や風味に言及がありません。美味しさは魔法を使わずとも追求できるからか。図は1920年代のナショナル・ビスケット・カンパニーの広告。略してナビスコか、と自分も今気づきました。
584
585
586
587
え、ここは・・?たしかわたし、トラックにはねられて・・・そうだ、ステータス画面! twitter.com/bijutsufan/sta…
588
589
590
そういうわけで4月23日はドラゴン退治というよりはドラゴンと聖人が共謀した日ととらえておるのであります。 #ドラゴンの日 twitter.com/MuseeMagica/st…
591
592
593
長崎県生月に伝わる潜伏キリシタンの聖画、いわゆる納戸神ではないでしょうか。モチーフは「太陽を身にまとい月を足元に置く女」「その女は身ごもっていた」(黙示録12章)。えらく抽象的な表現をされているものか、と。 twitter.com/ii_museum/stat…
594
595
596
597
598
雑。ゆえあってザビエルの書簡集(英訳)をチェックしておるのですが、当時のままの地名表記がかっこいいのであります。
鹿児島 Cagoxima 都 Meaco
豊後 Boungo 平戸 Firando
なんかで使いたく思うのですが、思いつきません。
599
さて #13日の金曜日
凶日という発想はもちろん英国にも古来より存在していて、ここに紹介するのはそのひとつ。△が凶、Xが大凶。これに金曜日が重なるとトリプル凶となりますが、面白いのは五月に凶日がない点。さらに13日もない点でしょう。13日の金曜日は比較的近年の発明なのであります。
600