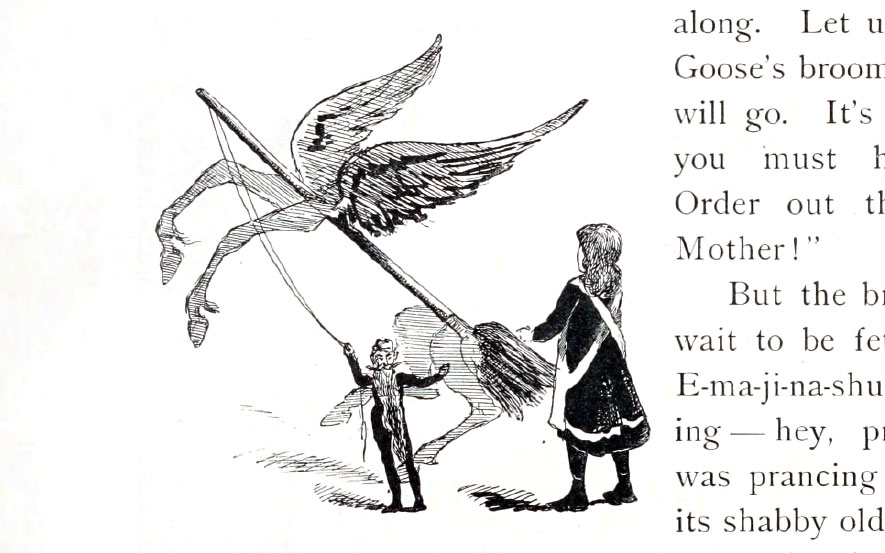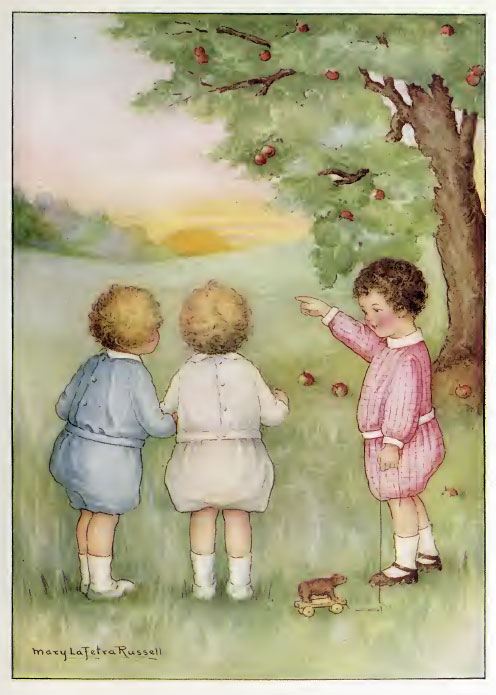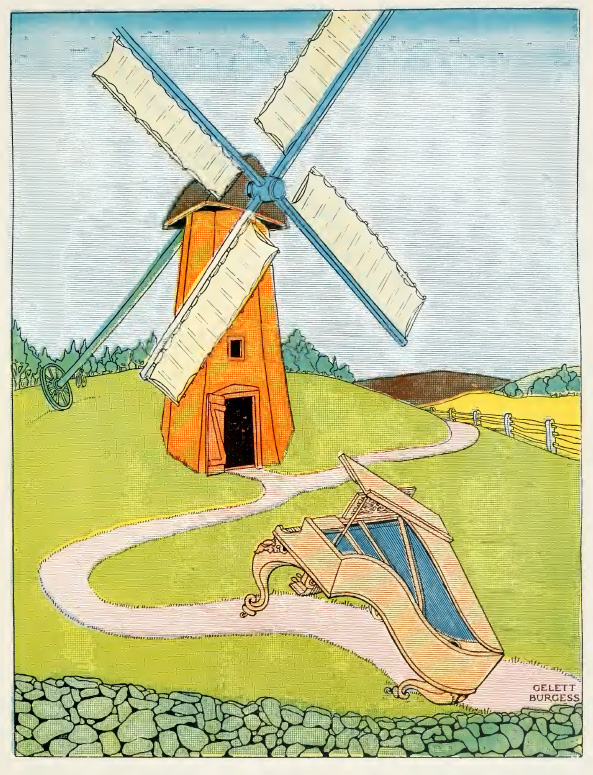551
552
553
554
555
556
557
本日は #時の記念日 ということで関連伝承。
・古い時計のねじを巻いて動かすと忘れていた何かが動き始める
・割れた砂時計の砂はアンラッキー
割れた砂時計の砂はいろいろと呪術的応用が伝わっておるのです。
559
560
561
ーー「こんなものを目にできるとはなんという幸運か」。こういった一連の変成を術式化して儀式に組み込む作業を19世紀のオカルティストたちは好んで行っておりましたので、後続の者たちも民話童話の類を渉猟するのであります。絵はラッカム。
562
#伝説級の猫
当館からはご存知「ふとりたおした猫」を。1985年、ロンドンはノッチングヒル界隈をシメていた大物。ほとんどケットシーであります。
563
雑。妖精からプレゼントされる代表的アイテム
・幸運の財布(常に金貨三枚が入っている)
・七里靴
・暗闇の帽子(不可視効果)
・願望の帽子
・鋭利の剣(万物を切断して刃こぼれしない)
・象牙の鏡(あらゆる場所を映し出す)
・空飛ぶ絨毯
一番恐ろしいのは言うまでもなく願望の帽子です。
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575