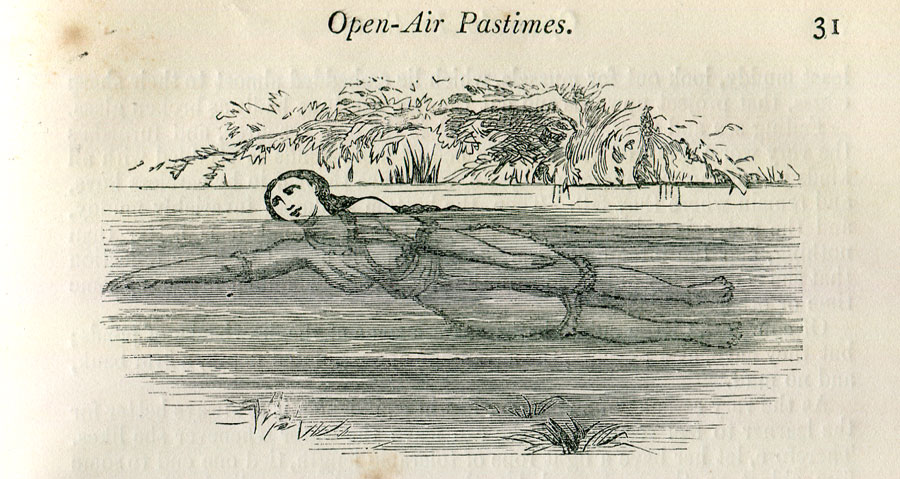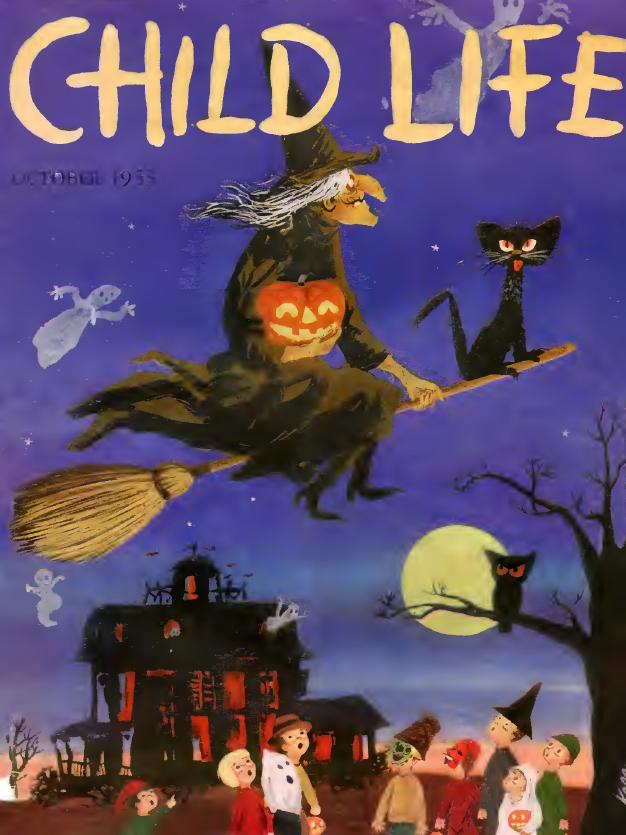501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
これは男の子の可能性がありますね。当時、男児に女児服を着せて育てる習慣があったのです。とりわけこのオフショルダーの服はそういった場合によく見るのであります。 twitter.com/wikivictorian/…
519
520
521
522
523
524
#世界ミツバチの日 とのこと。
ミツバチに関する伝承
・ミツバチの数を数えてはならない
・分蜂の際に鐘を鳴らすと群れを呼びこめる
・冠婚葬祭の際に通知を怠ると不都合が生じる
19世紀英国の家庭菜園には蜂籠が常設されていて、蜂蜜採取はもとより受粉その他に活用されていたそうです。
525