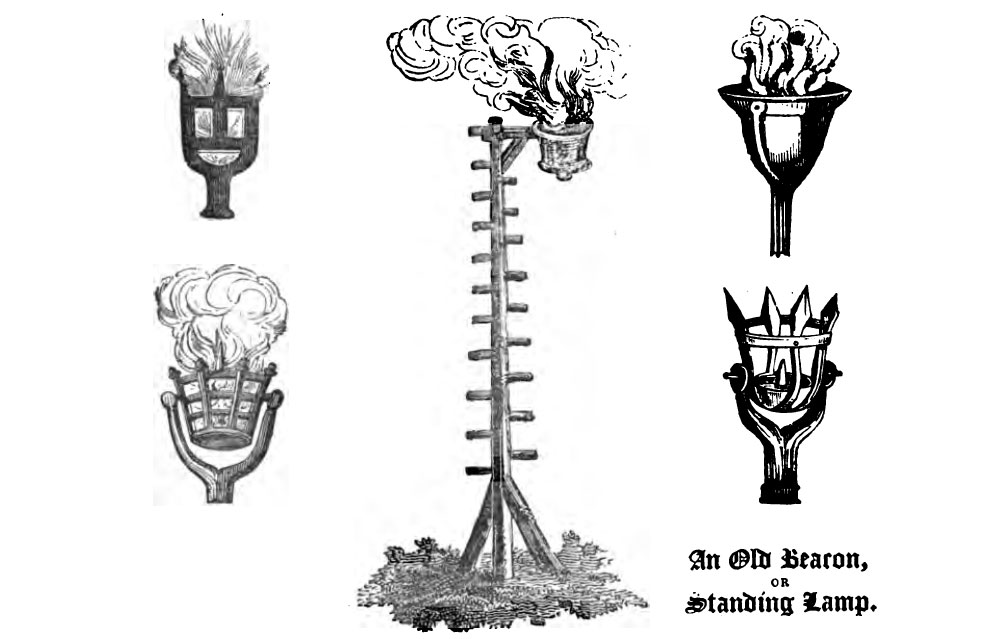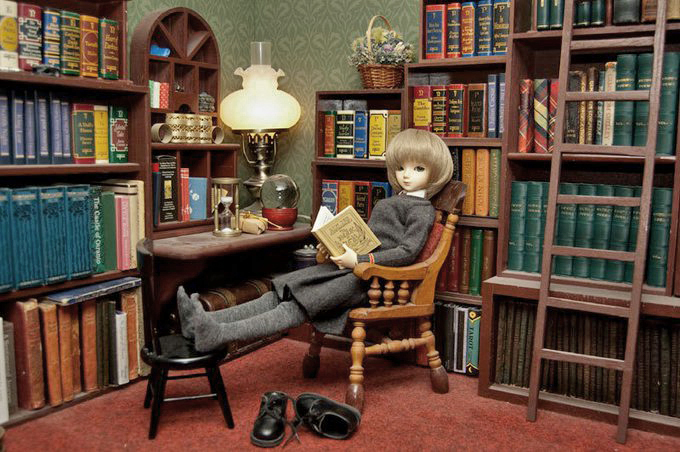376
377
378
379
380
381
382
383
384
雑。「妖精金」fairy gold は唾液をつけると消えるという伝承がありまして。ロンドンなどでは商人がその日最初に貰う貨幣(handsel) に唾をつける習慣があったとのこと。オリンピックの優勝者たちがメダルをかじっているのもこれが遠因かもしれません。唾液あるいはキスの解呪伝承は古いのであります。
385
386
387
388
389
家族年金だけで女房子供を養うには苦しい場合が多く、そもそも立場的に生涯独身を期待されているのであります。えんえんと旅行していたり、クラブで寝起きしたり。最後は田舎のコテージで本を読み薔薇を育て犬を飼い魚を釣る日々に入るという、向いてる人には最高の一生でありましょう。
390
391
392
#宝石言葉 がトレンドにあるので。
とりあえず調べますと1846年のオズグッド詩集にそれらしきものがありました。花言葉が流行るなか宝石がすねてるぞ、「宝石は決して枯れない花」だぞ、と。そしていろいろな宝石の特徴を宝石言葉として述べていくという趣向。興味深し。
393
394
395
397
398
#厳粛な場での不意の一撃
最近聞こえてきたものとしてーー
「新郎はわが社でも嘱望されるオランウータンとして」
課長さんはオールラウンダーと言いたかったらしいのですが、慣れないカタカナはよしたほうがいいのであります。
399
400