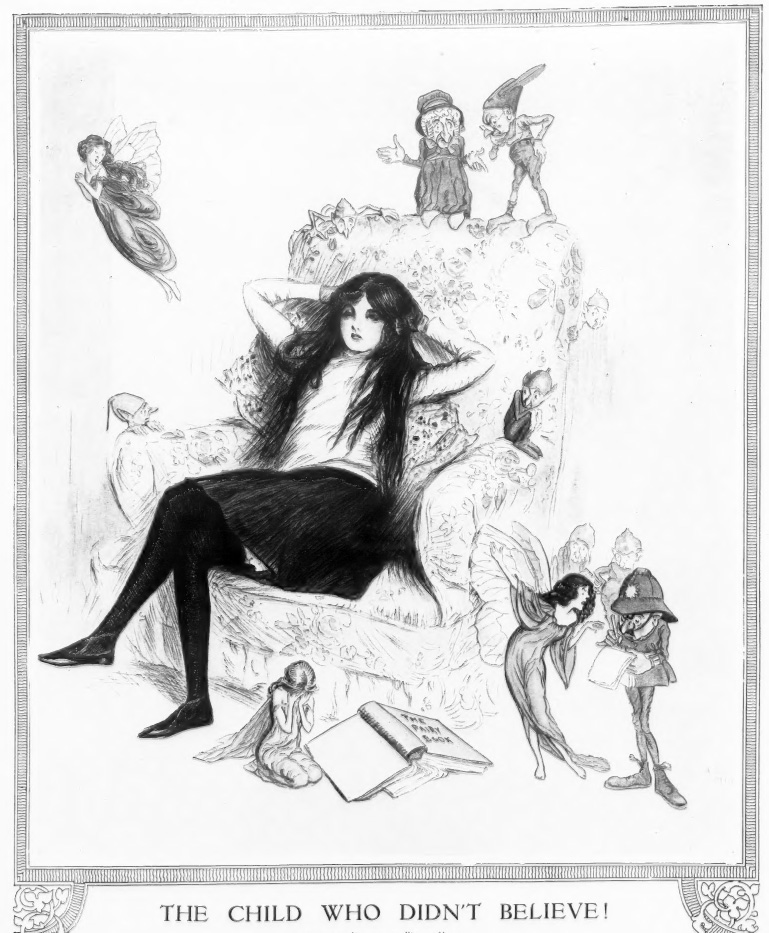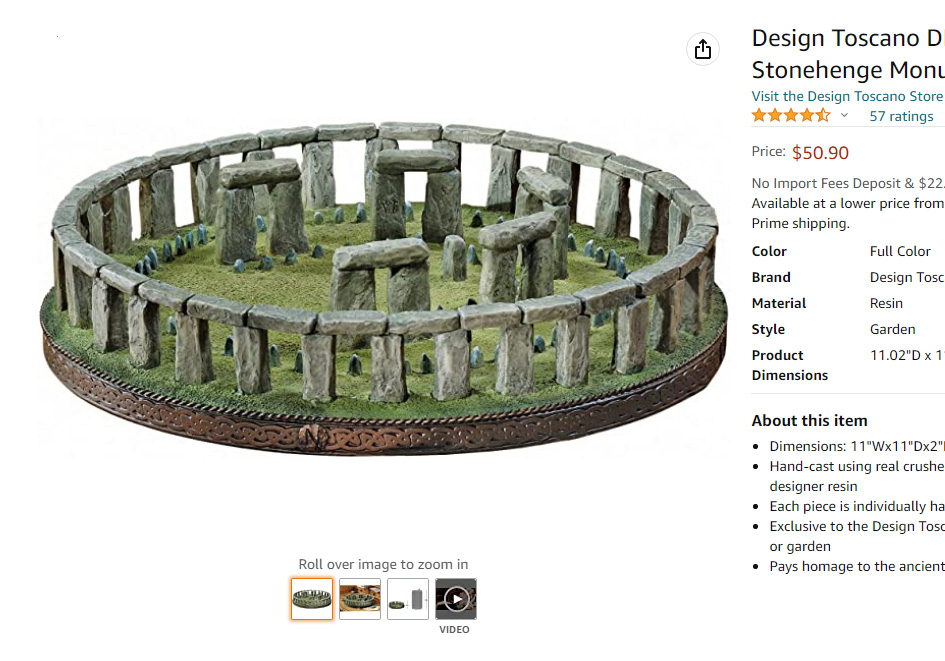326
327
328
329
#時の記念日 だそうで。
西洋の花暦でも和名トケイソウがちょうどこの時期に配されるのであります。洋名「パッションフラワー」、その花のなかにキリストの受難「パッション」の道具がすべて見られるゆえの名称とのこと。図は洗礼証明書に見るパッションフラワー図案の例。護符として強力なり、と。
330
331
332
333
すべての死者の日。思い出してくれる友人がいない人のために、教会ではロウソクを灯したり、鐘を鳴らしたりして孤独な霊を慰めるといいます。11月2日の黄昏時、遠くで鐘の音が聞こえたり、不思議な明かりが見えたときは、ちょっとだけ敬礼するのが心得なんだそうです。
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
346
347
348
349
350