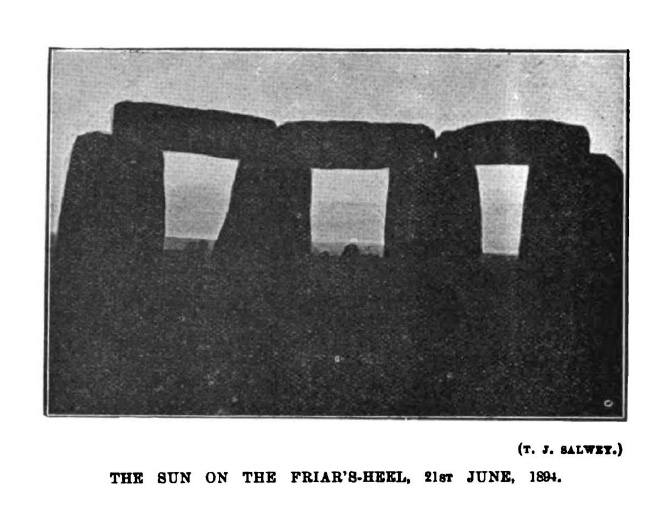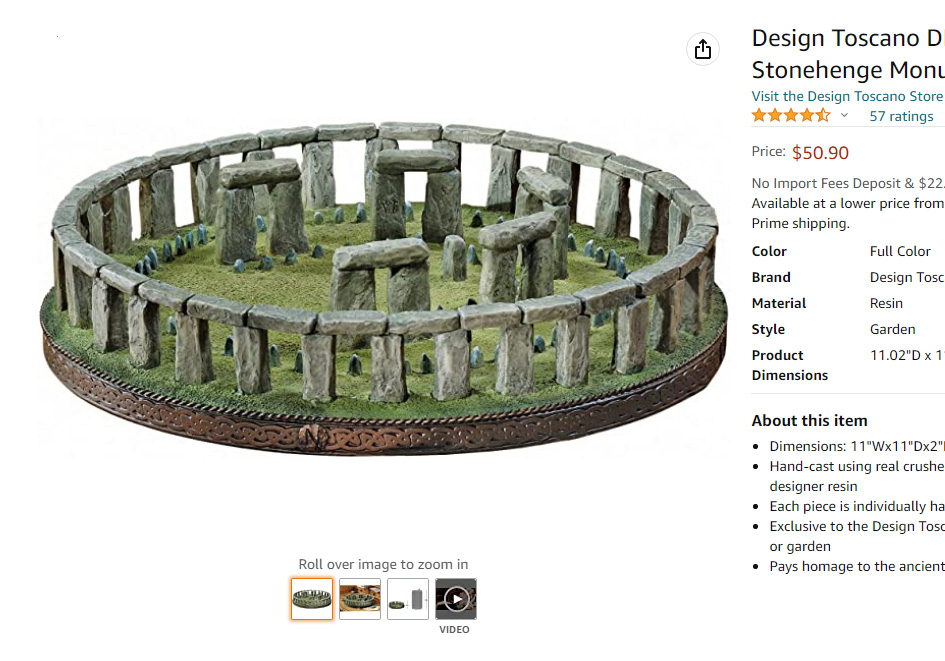1251
1252
1254
1255
1256
1257
1259
1260
1261
1262
1263
1264
聖ヨハネ関連で再掲。ローマに複数。アミアン、ダマスカスのも有名だとか。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1265
6月25日は #船員デー 。ということで船乗りに関する伝承
・魔女からロープで縛った風を買う(六ペンス)
・金のイヤリングをすると視力が増す
・馬のしっぽとイワシが嫌い(その形の雲が嵐の予兆)
・ウサギの話は船上では禁忌
・出港時に追いかけてくるカモメは死者の魂
主に英国系の伝承です。
1266
船上でのウサギの禁忌に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275