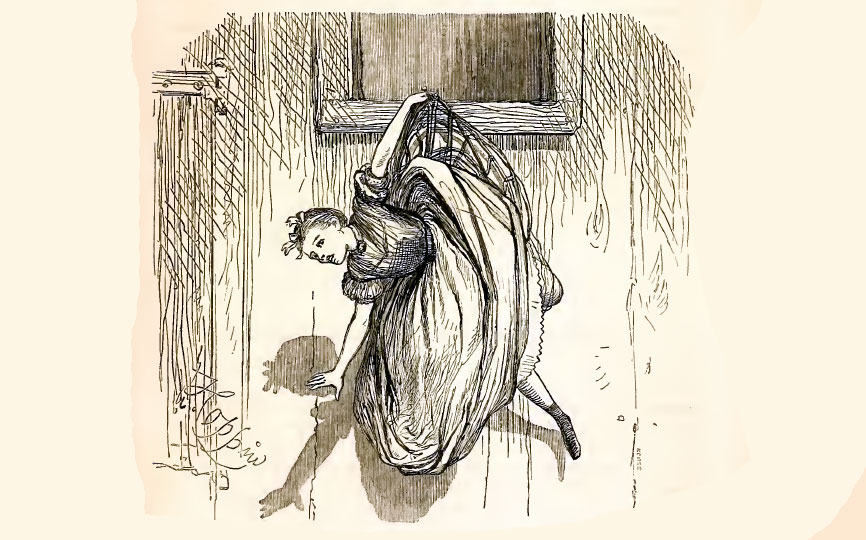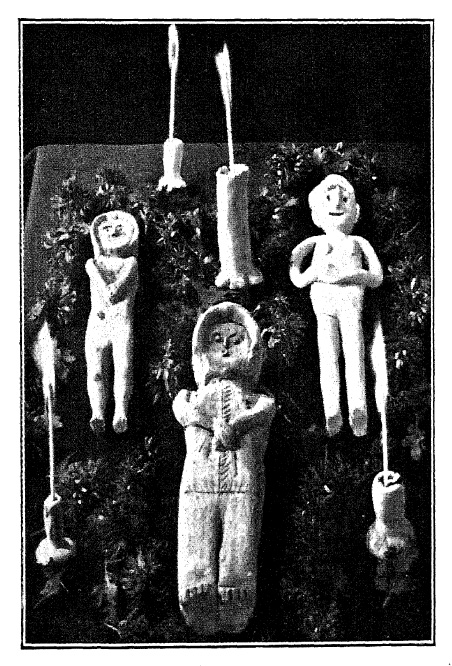1226
1227
こちらは日本に伝わったヨセフィ子さまの貴重なお姿、ということで再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1228
暦。6月4日は #虫の日 とのこと。
ウィリアム・ロスコーが1807年に発表した子供向けの詩「蝶の舞踏会あるいはバッタの宴」は好評を博し、イラスト付きの普及版が飛ぶように売れたそうです。擬人化ものながらも英国児童の昆虫リテラシーの向上に大いに寄与したのであります。続編に「蝶の葬式」。
1229
雑。ときどき面白い会話が流れてきたりするのです。
「作品は大好きだけどそれを書いた作家は嫌いという人に会いまして」
「あー、あるわなあ」
「産みの親が嫌いってどういう心理なんですか?」
「きみ、嫁さんのご両親、好きか?」
「・・・なるほど」
1230
1231
1232
長崎県生月に伝わる潜伏キリシタンの聖画、いわゆる納戸神ではないでしょうか。モチーフは「太陽を身にまとい月を足元に置く女」「その女は身ごもっていた」(黙示録12章)。えらく抽象的な表現をされているものか、と。 twitter.com/ii_museum/stat…
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
ゆえにーー
貴婦人「きっとあなたには緑のガウンが似合いましてよ」
といったセリフもかなり怖いのであります。白では露骨すぎるわけです。面白や、と。
1242
1243
1244
1246
1247
1248
1249
1250