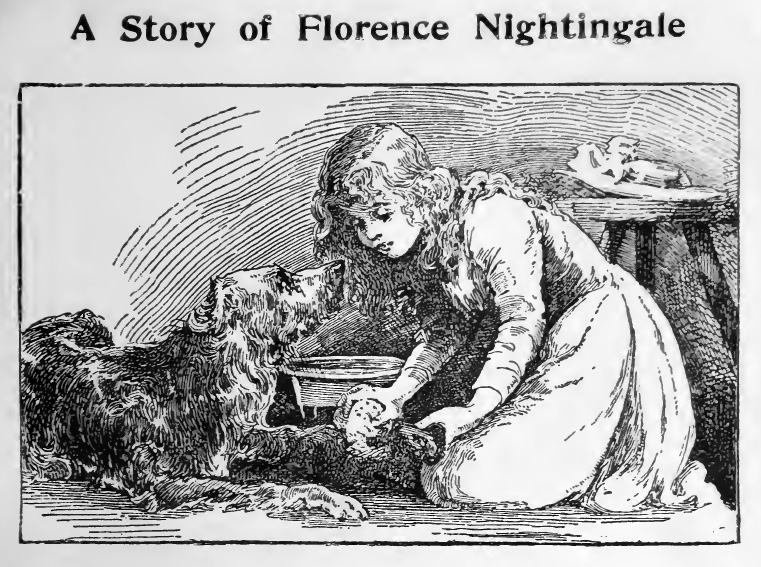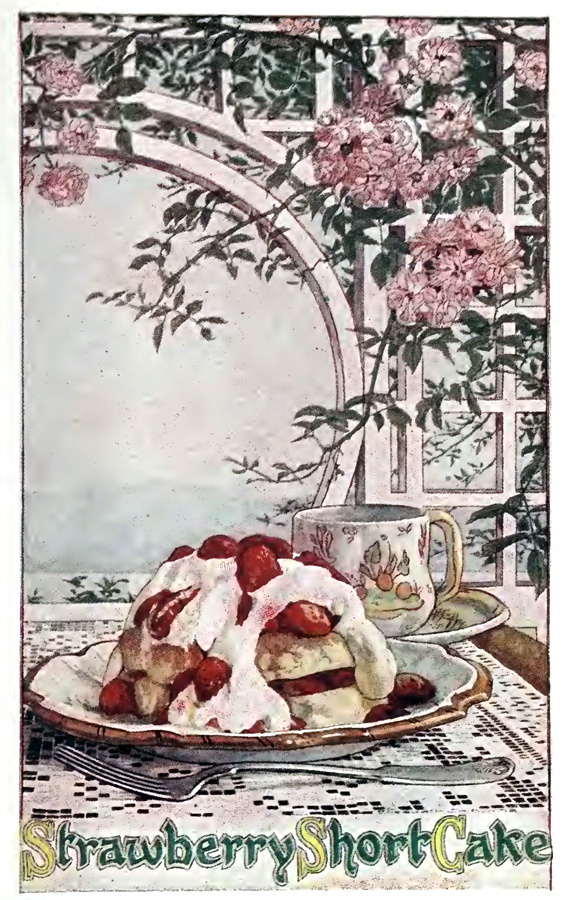1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
既視感があったので数分間記憶の棚をひっくり返した結果、でてきた答えが「ロマサガ2のラスボス合体の図」。諸氏の賛同やいかに。 twitter.com/Estetism_jp/st…
1183
1184
1185
1186
母の日とのことで再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1187
1188
1189
1190
1191
1192
さて #13日の金曜日
凶日という発想はもちろん英国にも古来より存在していて、ここに紹介するのはそのひとつ。△が凶、Xが大凶。これに金曜日が重なるとトリプル凶となりますが、面白いのは五月に凶日がない点。さらに13日もない点でしょう。13日の金曜日は比較的近年の発明なのであります。
1193
#愛犬の日 とのこと。
魔法関係でよく目にする犬種名としてはマスチフ、ニューファンドランドといった巨大犬、鋭い嗅覚で有名なブラッドハウンドあたりでしょうか。魔犬の類はぬっと出現して近寄ってくるだけで、こちらが怖がらないかぎり害はないとされています。
1194
1195
暦。5月14日は #けん玉の日 とのこと。
けん玉は英語では a cup and ball と言いまして、道化の持ち物のひとつ。世界をもてあそぶのであります。そのモットーは「愚行が世界を支配する」。神聖道化は地球そのものを遊具とする不逞の輩なり、と。絵はマッケンジーの『アウルグラス』(1860)から。
1196
1197
1198
1199
夏の夕暮れの読書、ということでこれも再掲しておきましょう。あちらは蚊の類が少ないのでうらやましいです。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1200
初夏の窓辺あるいは屋外での読書には日本ならでは問題もあるのです。蚊取り線香の匂いは、それはそれで風情があると思いますが。 twitter.com/MuseeMagica/st…