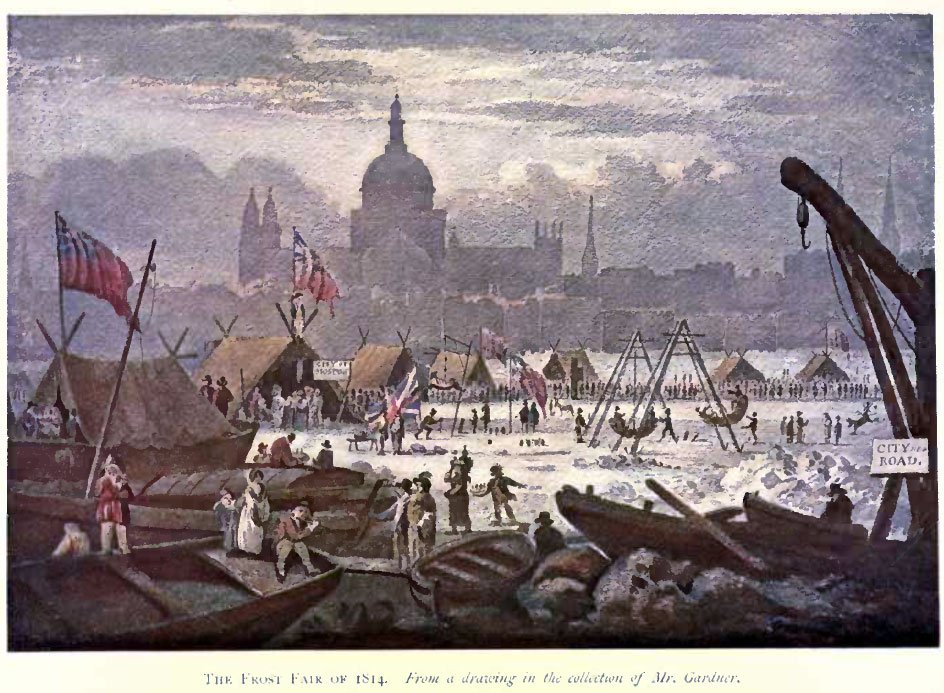976
977
978
979
トレンドに「愚者の棺」なるものが。
タロットの愚者に関していえば、あれは放浪者でもありますので野垂れ死にが基本。屍は崖下で白骨化するか獣に食われるのであります。棺はちゃんとお葬式をあげてもらえた証拠ですので、「愚者の棺」は矛盾ワードなのでしょう。面白や、と。
980
981
982
983
984
985
986
987
988
先のキューカンバーサンドイッチに関して。アフタヌーンティーに出すキュウリのサンドイッチは薄ければ薄いほど偉いとのこと。極薄のパンのスライスを作るには、切り出すパン面に先にバターを塗って粘着力を確保するのがコツだとか。分厚いサンドを出すとあとでいろいろ言われる怖い世界であります。
989
990
瓶詰の奇術師関連で再掲。この当時は帯剣している人も多かったため、剣を抜く人をまず取り押さえる、あるいは抜く前に取り上げるのが重要だったそうです。ネコを振り回すのは意味不明。 twitter.com/MuseeMagica/st…
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000