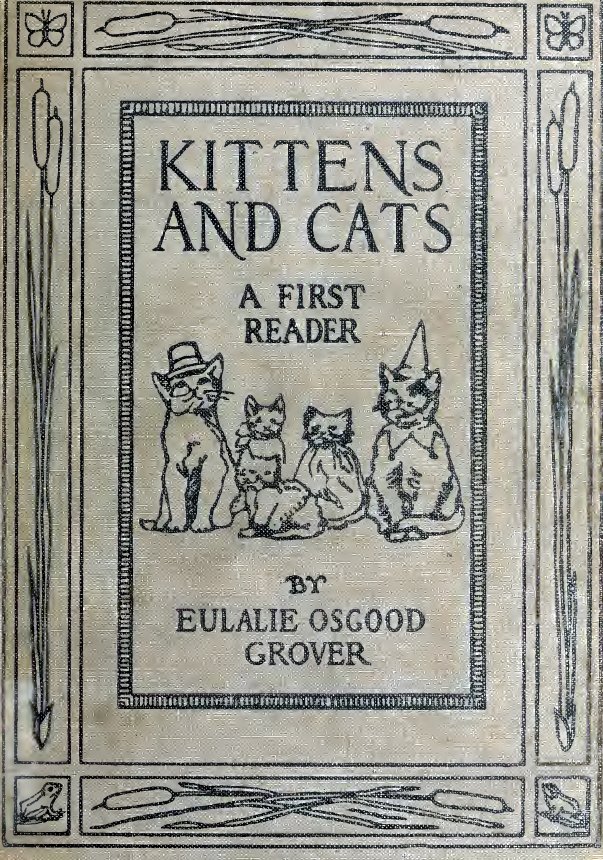676
先のリツイートに関して。エルフはタフで働き者の徒弟たちです。森のなかの低血圧どもとは違うのであります。手放す車がすねる話は具体的に経験あり。このあたり、理屈抜きの感性でありましょう。 twitter.com/MuseeMagica/st…
677
678
679
680
681
682
683
684
#StrawberryMoon
ストロベリー・ムーンはブルーベリースカイと対句であります。濃紺の夕空にピンクの月が浮かぶのが理想ですが、今日はちょっと曇って暗かったのであります。少しぼんやり。
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700