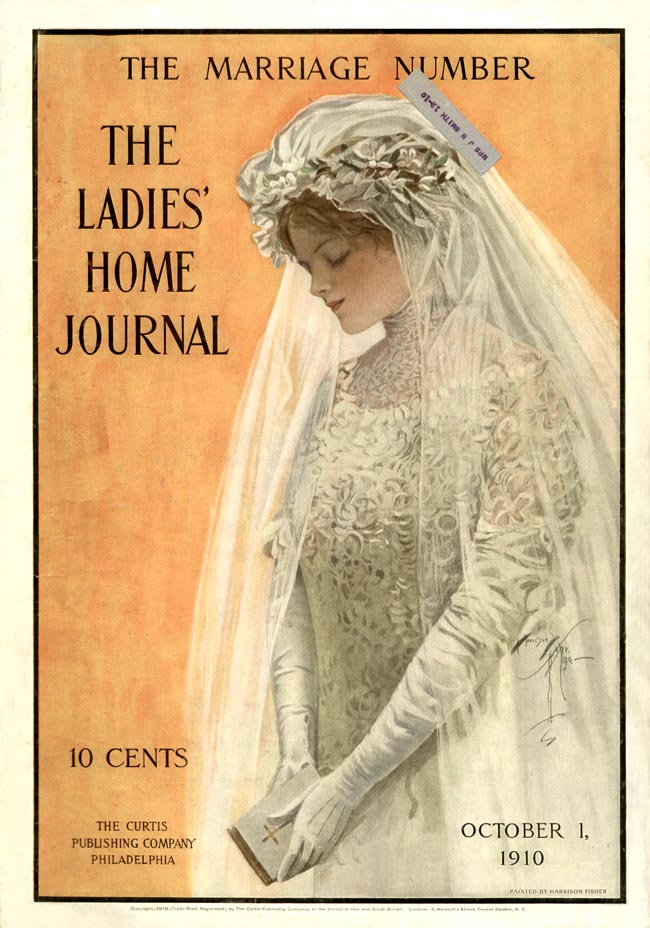626
627
628
629
631
再掲。アラジンの住む都を北京としている英語作品が多い印象。辮髪もよく見かけます。 twitter.com/MuseeMagica/st…
632
5月22日は #サイクリングの日 とのこと。
1890年代のロンドンでは若い女性の間で自転車が大流行。ブルーマー姿で暴走するニューガールたちが半ば社会問題化。月夜のサイクリングデートが憧れのロマンス行動だったようです。当時のオカルト関係者の間でも自転車保有率が高かったのであります。
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
ジャンヌを貶めようとする勢力の活動にも振幅があるようで、「悪魔の手先」といった古典的なものから「19歳と言い張っているが実は27歳」といった微妙なものまで見つかります。どちらがクリティカルかわかりにくいです。
645
646
647
648
649
650