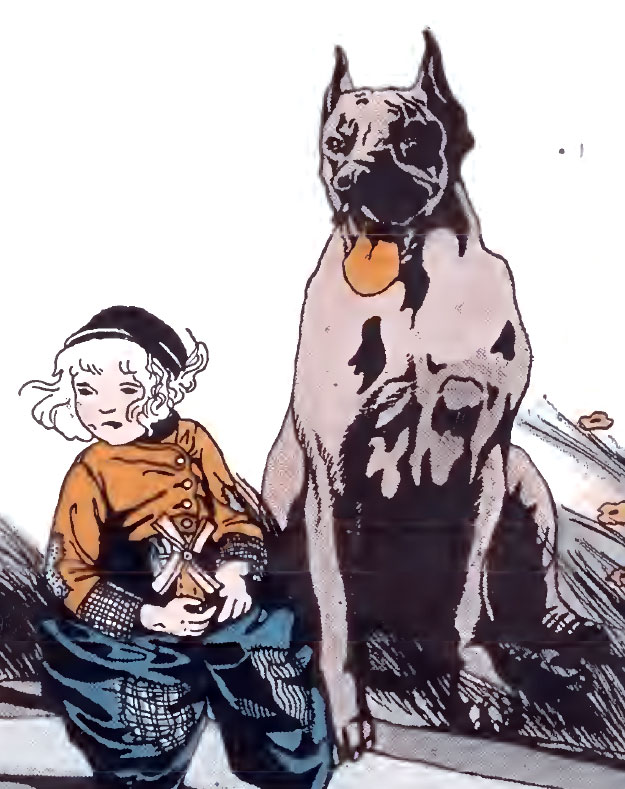401
402
403
404
405
もちろんクリスマスに高価な童話本をプレゼントされるのは一部の恵まれた子供たちだけでしょう。学校から貰えるご褒美本は優等生の特権。華麗な装丁で魔法と妖精を語るフェアリーブックはある種の怨嗟の対象ともなり、トロフィーと化していくのでありました。
406
407
408
409
410
411
412
413
414
BBCウェールズによるマリロイドの映像。 twitter.com/BBCWales/statu…
415
416
417
418
卵に関する伝承
・割った卵の殻はきちんと潰さないとアンラッキー
・夜に卵をとりこむとアンラッキー
・新婚の夫に義母がオムレツを作ってやると夫婦仲がうまくいく
・悪魔がくれるメンドリは黄金の卵を産む
卵の殻は悪しき手に渡ると呪術の材料にされるとのこと。義母のオムレツはロシアの伝承です。
419
420
クリスマスに新しい靴や靴下をおろし、その際に銀貨などを入れておくわけです。本来もらうべきは靴や靴下であってプレゼントは副次的だったのですが、そこらが混乱して現在に至ったとのこと。
421
422
423
玄関でステップ&バックするのは、もともと「新年最初に玄関から入ってくるものが一年の動向を決める」という伝承があるためで、下手なやつに来られるくらいなら自分でやってしまえという発想です。
424
425
他にも黒髪が歓迎される話がかの国には多いのです。一説には、冬場に食い詰めた北欧系が襲ってくる時代が長かったため、寒い時期の金髪には本能的に警戒感があるとか。