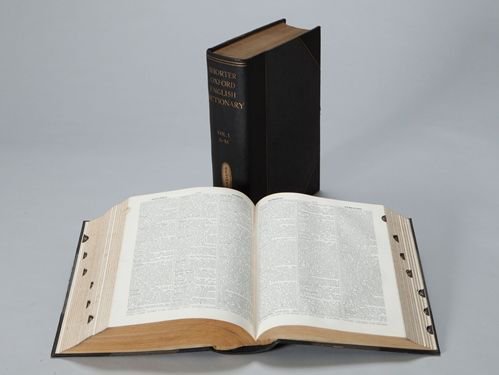826
827
今日(5/23)は世界亀の日だそうです。そこで亀に関する資料をご紹介します。画像は「天保雑記」より、天保10年(1839)に東京三田のとある大工の家の庭先に現れた緑の毛の亀の図です。「亀甲鮮カニテ金光見ユ」と記されています。buff.ly/3e4eiKw
828
829
【デジタル化作業】
当館では計画的に資料のデジタル化に取り組んでいます。1mから4m程の大きな絵図などは、非接触大型上面スキャナーを用いてスキャニングします。画像は準備が整い次第「国立公文書館デジタルアーカイブ」で公開しています。buff.ly/2H1VFqQ
830
弘安2年(1279)10月16日、阿仏尼が相続争いの訴訟のため、京から鎌倉を目指す旅に出発。幕府の武家法による有利な判決を得ることが目的でした。この際に書かれた紀行文が『十六夜日記』。16日に出発したことからこの名前で呼ばれています。buff.ly/2ydOOZJ
831
慶長20年(1615)4月28日、豊臣方の武将大野治房(大野主馬)らが、徳川方の兵站基地である堺の町に火を放ちました。この事件をもって、大坂夏の陣は開戦しました。画像は『駿府記』で、四月二十九日条に、この事件の記述があります。buff.ly/2HJDzgg
832
天正元年(1573)8月27日、織田信長が浅井氏の本拠地である北近江の小谷城を攻略しました。元亀元年(1570)に信長から離反した浅井久政・長政父子は籠城戦の末に自刃し、浅井氏は滅亡しました。信長の妹お市の方は長政の妻です。画像は『安土日記』(信長公記)の該当部分。 buff.ly/2Hp2hkY
833
834
デジタル展示「昭和二十年」を公開しました。平成27年開催の企画展をベースとし、昭和20年(1945)を中心に、8月15日の玉音放送のもとになった「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」など、大きな転換期を迎えたわが国の姿を伝える資料をご紹介しています。ぜひご覧ください。
buff.ly/2VKXYYZ
835
今日(1/20)は二十四節気の一つ「大寒」です。一年で最も寒さが厳しくなる頃。画像は紅葉山文庫旧蔵の『拾遺和歌集』より清原元輔の和歌――冬の夜の池のこほりのさやけきは月のひかりのみがくなりけり――月光が磨くかのような冴えわたる氷の美しさが詠まれています。
buff.ly/35ZUcwo
836
春の特別展は、祝日を除く毎週木曜・金曜は20時まで開館しています(入館は閉館の30分前まで)。午後からのお出かけでもゆっくりご観覧頂けます。週末前のお時間に幕末に思いを馳せにいらっしゃいませんか?
#知られざる幕末
837
平成30年は、明治元年(1868)から起算して満150年の年に当たります。これを契機に、政府においては「明治150年」に関連する施策に積極的に取り組んでいます。今後、国立公文書館でも、関連事業に取り組んでいく予定です。
※関連サイトbuff.ly/2wDhOpa
838
今年(2018)は明治元年(慶応4年)(1868)から数えて満150年の年です。同年9月8日、「明治改元の詔」(画像は「勅語録」採録のもの)が発せられ、あわせて天皇一代に元号を一つとする「一世一元」の制も定められました。(続く
buff.ly/2NlFJpc
839
食欲の秋ですね。画像は江戸時代前期の図解百科事典である『訓蒙図彙』から、秋の果実です。梨、奈(カリン)、棗(ナツメ)、栗が描かれています。本書は京都の儒学者中村惕斎が編纂しました。平易な内容で、大人から子供まで多くの読者を得ました。buff.ly/2xoX7NS
840
「平成」のクリアファイル、大変ご好評頂いております!購入希望の方は、5月6日(日)まで開催の特別展「江戸幕府、最後の闘い」の観覧とあわせて、ぜひご来館くださいね。当館オリジナルグッズについてはこちらもご参照ください→buff.ly/2jjzi5w
841
明日(7/22)から、つくば分館で企画展「平家物語―変わりゆく時代を学ぼう―」を開催します。当館所蔵資料により、『平家物語』に登場する天狗・怨霊・物怪( もののけ) などに注目し、武士たちの物語の背後にある妖しくも美しい世界をご紹介します。ぜひお立ち寄りください! buff.ly/32EwEN5
842
寛文12年(1672)12月18日、保科正之が62歳で逝去しました。三代将軍徳川家光の異母弟に当ります。家光の死後、幼少の四代将軍家綱を補佐し、会津松平家の祖となった江戸時代屈指の名君です。画像は『譜牒余録』のうち、逝去についての記述。
buff.ly/2BgrQ3S
843
天平3年7月25日(731年8月31日)、大伴旅人が没しました。「令和」の典拠となった梅花の宴を主催した人物として改めて脚光を浴びましたね。画像は寛永20年(1643)版『万葉集』より、亡き旅人に捧げられた歌ー―よしえやし栄えし君のいませしば昨日も今日も我を召さましを
buff.ly/2Cx5lZ8
844
今日(7/23)は大暑。紅葉山文庫旧蔵の『源氏物語』から涼しげな画像を探してみました。「常夏」では光源氏たちが釣殿の上で、氷水を使った水飯を食べている場面が登場します。冷蔵庫もエアコンもない当時では、大変な贅沢だったようですよ。buff.ly/2ugSeqr
845
いよいよ明日(9/22)から、平成30年秋の特別展 明治150年記念「躍動する明治-近代日本の幕開け-」が始まります。今回の特別展では、歴史の教科書や年表で目にする出来事を中心に、明治前半期の日本の歩みを振り返ります。ぜひご来場下さい。
buff.ly/2IgMIdf
#躍動する明治 #明治150
846
今日(5/7)は博士の日。明治21年(1888)5月7日、伊藤圭介、加藤弘之、菊池大麓ら25名の学者に日本で初めての博士号が授与されたことにちなみます。今回はその内の1人、山川健次郎の履歴書をご紹介。会津出身の山川は米国に留学し理学博士となり、東大総長にもなっています。buff.ly/357S4nz
847
永禄11年(1568)12月3日、後の福岡藩初代藩主黒田長政が生まれました。画像は『黒田長政記』から関ヶ原の戦いの場面。9月15日の開戦以前に西軍の金吾中納言(小早川秀秋)や吉川蔵人(吉川広家)らと接触していたことが記されています。
buff.ly/2raa0e8
848
当館グッズの新商品は近衛前久自筆と伝えられる『三十六人歌合』をモチーフにしたクリアファイル!激動の戦国乱世を生き、関白・太政大臣を務めた前久は書家としても著名でした。 #麒麟がくる では #本郷奏多 さんが演じていますね。リンク先には狩野探幽による龍・虎の図も。
buff.ly/2GDNJ3G
849
現在、当館では第1回企画展「競い合う武士たち―武芸からスポーツへ―」を開催中!画像は展示資料『おあむ物語』より。同書は石田三成の家臣の娘「おあむ」の若い頃の体験記。関ヶ原の戦いの際、味方が討ち取った敵の首に、死化粧としてお歯黒を施す場面です。
buff.ly/2O6UTxz
850
今日(1/20)は二十四節気の一つ「大寒」。最も寒さが厳しい頃。『新古今和歌集』の藤原定家の和歌「駒とめて袖うちはらふかげもなしさののわたりの雪の夕ぐれ」を思い出しました。一面の雪景色を想像させますね。次のツイートで解説しますよ!(続
buff.ly/2szVLjA