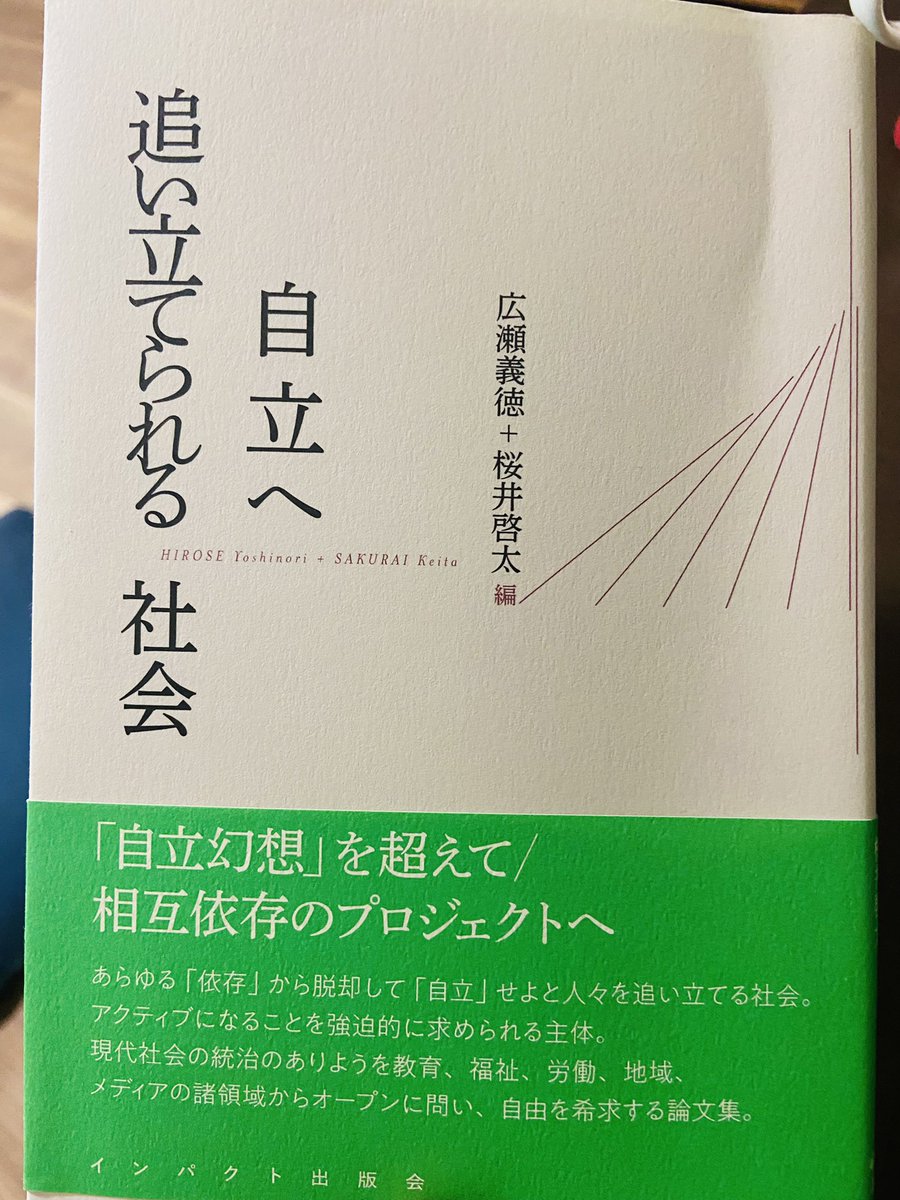126
自閉症スペクトラムの子どもを「外国人」に例えている書籍。著者は「わかりやすさ」をもって例えたのだろうけど、どちらの差別も偏見も助長している。 twitter.com/_shiopan/statu…
127
配偶者がいなくて一人暮らしでも四六時中仕事ばかりだったら、確実にセルフネグレクト状態になる。一時期の私はそうだった。持続可能ではない。でもそうしないと仕事を任せられなかったり評価されなかったりする場合、そうならざるを得ない。
128
教育は大切なのだけど、気をつけないと構造の問題を個人化することにつながる。差別禁止の制度を作らずに「差別をやめよう」と教育だけで解決しようとしたり、同性婚ができる制度をつくらずに「性的マイノリティのことを理解しましょう」と教育だけで解決しようとする。
129
マイノリティ属性の中にもさらに主流とそうでないものがあって、だこらこそ交差性の視点は本当に大切。フェミニストが「このコミュ障が」って言っていたり、障害者運動の中で女性差別があったり。特に対人コミュニケーションの困難さに対する差別はめちゃくちゃ難しい。
130
「相談したり助けを求めたりする力が必要」とか子どもや若者に言うけれど、10代の方と話してると「相談したいと思う人がいない」「上から目線の話されるこら相談したくない」など出てくる。相談してよかったなあという経験がなかったらそりゃ相談しようなんて思わない。
131
誰にでも等しく人権があること、そして、自分にはどんな権利があるのか、それを守るために自分はどんな行動ができるのか?を知りそのために行動した経験がないと、他者の権利主張に対して「ずるい」や「特別扱いは無理」と思ってしまうのかもしれない。
132
133
こうやって一つずつマジョリティ特権のある人には当たり前だったことがマイノリティ属性の人にとっても当たり前になっていくのは、声を上げた人たちがいたから。 twitter.com/akinaln/status…
134
もっと言うと、障害のない自分自身に特権があり、自分たち特権者仕様の社会に自分は恩恵を受けてきていること、特権者仕様の社会を維持することにこれまで加担してきたこと、などに気づく。「救ってあげたい」「トレーニングでよりよくしたい」的考えに疑いをもつ機会をつくる大切さ。
135
たしかに誰もが何かしらの特徴は持っているし、そもそもグラデーションなので、発達障害の場合は特に「みんなちがってみんないい」トラップに陥りやすい。でもたしかに世の中は発達障害の特徴がない人を中心に作られているということは、可視化し続けなければならない、と思っている。
136
「多様性」を謳いながら、これまで差別行為をしてきた人たちを起用しその説明もなく、性的マイノリティ差別をしてきた人の作った曲を使い、テレビでは手話通訳がなく、セネガル出身のアーティストの開会式出演を拒否。「安全安心」を謳いながら全くバブルにはなっていない。私はこの状況を楽しめない。
137
差別発言・行為をして辞任・解任された人たちを擁護する声を目にする。
細かい事実関係は当然わからないけれど、どんな理由があっても差別は差別で、その「擁護するつもりはありませんが」こそが、差別の温存に加担してきたのではないか。
138
その場は誰が用意すべきなのかというと、教育者としてのアイデンティティを持ちマジョリティ特権を多く持つ私のような立場の人なのだろう。「抑圧を受けている当事者が用意すべきだ」という主張にはまったくもって賛成できない。私と同じく教育者のアイデンティティを持つ人たちと一緒に作戦会議したい
139
マジョリティ特権の認識のある人にはあー耳が痛いってなるツイートなのかも(私含め)。一方で、マジョリティ特権の認識のない人にこれを伝えても反感を買うだけになってしまう。どうしたらいいのか。それを考えるのがマジョリティ性が高くてアライでありたい私の役割。一緒に考えたい人募集中。
140
子どもの権利や障害のある方の権利を中心に見据えた教育や支援について話すと、「理想を語るな。変に夢を見させるな。現実とのギャップに苦しむのは子どもや保護者だ」と専門家から言われることが昔からよくある。
141
「難しいことはわからないけど人生楽しもう」とか「無い物ねだりしないで今あるものに感謝して」とかいうメッセージには本当に要注意。
142
143
「できない自分はダメだ。いなくなるべきだ。」と思っていないか。周りの人にそう思わせてしまっていないか。休むことに罪悪感を持っていないか。人の人生は、生活は、こうあるべきだと勝手に決めたり、決められたりしていないか。
無自覚にそういう考えに基づいて組織や仕組みや制度を作っていないか
144
文科省の会議でも意見をしたが、「専門性が足りない」「専門性を身につけるべき」とずーーっと、繰り返されている。一人で全てができるようになるのは無理。必要な専門性を定義して、教師以外の人も含めたチームがどうしたら機能するか、そのための仕組みや条件を検討すべき。
145
例えば合理的配慮が特別扱いでずるい!って言うけれど、私たち今なんならマジョリティとして「特別扱い」受けている状態だね、とか、ずるいと思うなら、実は自分も気付かぬうちに抑圧受けてて合理的配慮が必要かもね?とか、そういう講演を最近はしている。
146
本田先生のシェアありがたい😭記事を急ピッチで書いたのは、国連勧告により、障害のある子とない子が場を共にする/しないの二元論の議論になってしまい、立場や障害種ごとの分断が強化され、結果少数派がいることを前提とした通常教育改革が進まないことを危惧したから。
147
「境界知能」の人に支援が届きづらい、という文脈は大切だけれど、IQだけを重視することはスティグマにつながりやすくなってしまうのでは。
そもそも知的障害は知能だけではなく適応行動も含めているのに、数値でわかりやすいからかIQだけに焦点当てられがち。
148
・「気にし過ぎ」
・「もっと冷静に」
・「もっとポジティブに」
・「文句ばかり言っても仕方ない」
・「もっと戦略的に」
と他者の発言に対して思った時は、自分とその人との社会的な立ち位置を踏まえているか、関係性に不均衡さはないか、チェックすることにしている。
149
なぜかすごく拡散されているので確認しておくと、
・人間誰もがマジョリティ性とマイノリティ性を持っている
・マジョリティ性が高ければ高いほど自分の特権に気が付きづらい
など前提に言っています。
出口先生の論考を参考にどうぞ。
co-coco.jp/series/study/m…
150
えいなかさんの「ケアの欠如な放棄は加害」の記事やツイート、本当にハッとした。関係性を築くことはケアをし合うこと。ケアをしあうことで関係性は成り立つため、どちらかがケアをしてどちらかがケアをしない、という役割分担は成り立たない。ケアを放棄している人との関係性を維持する必要はない。