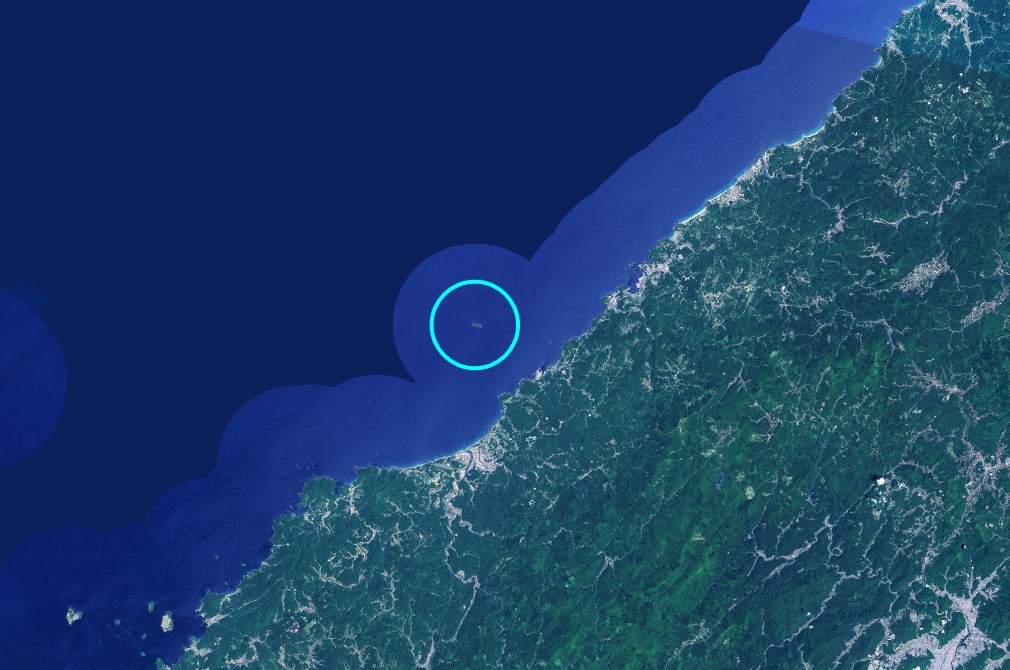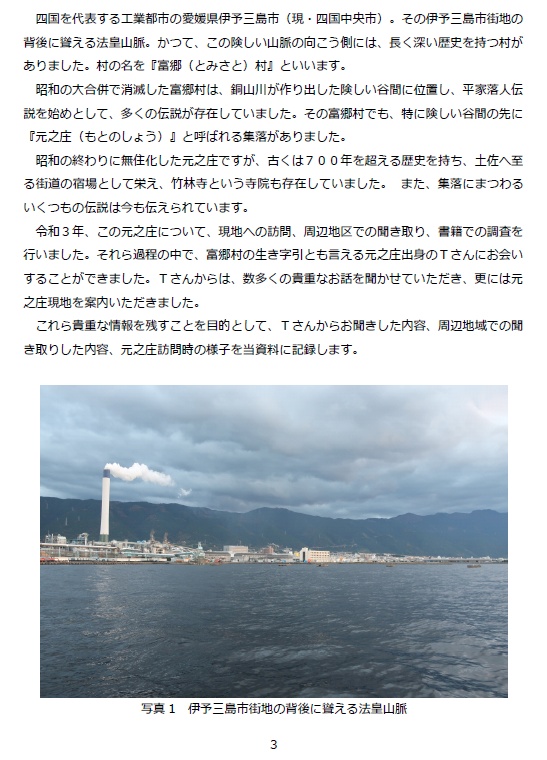151
152
153
156
157
158
159
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174