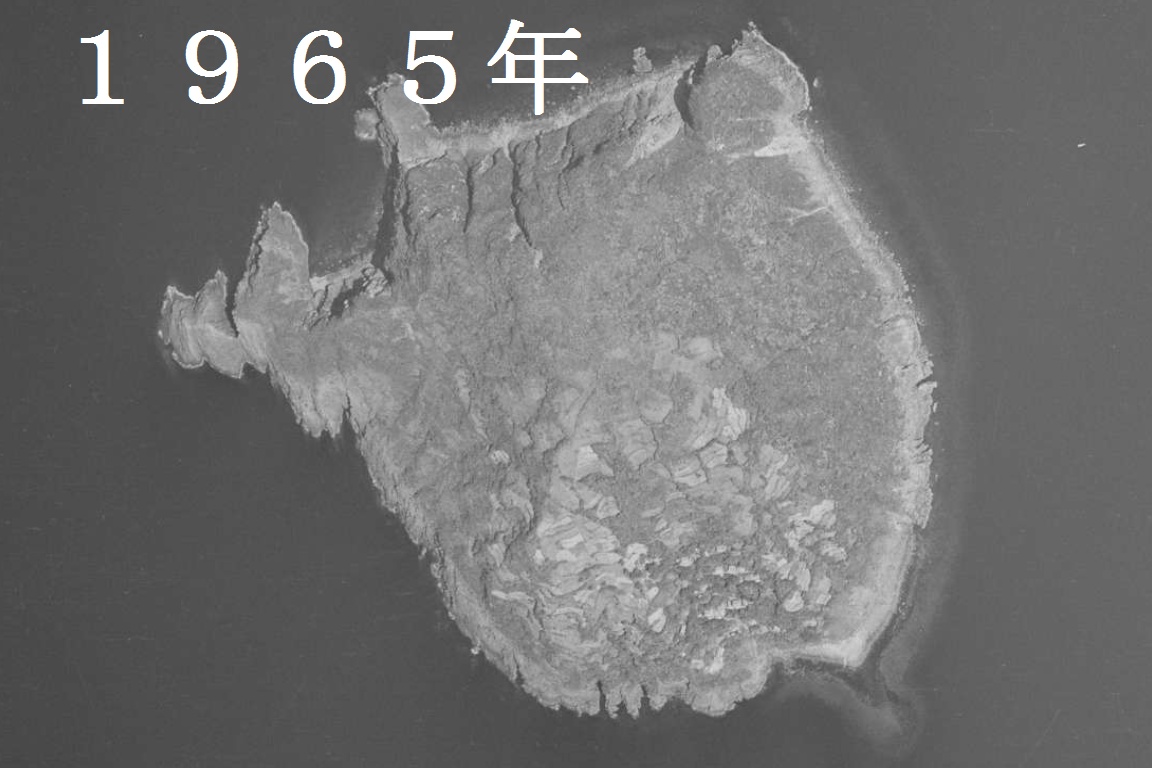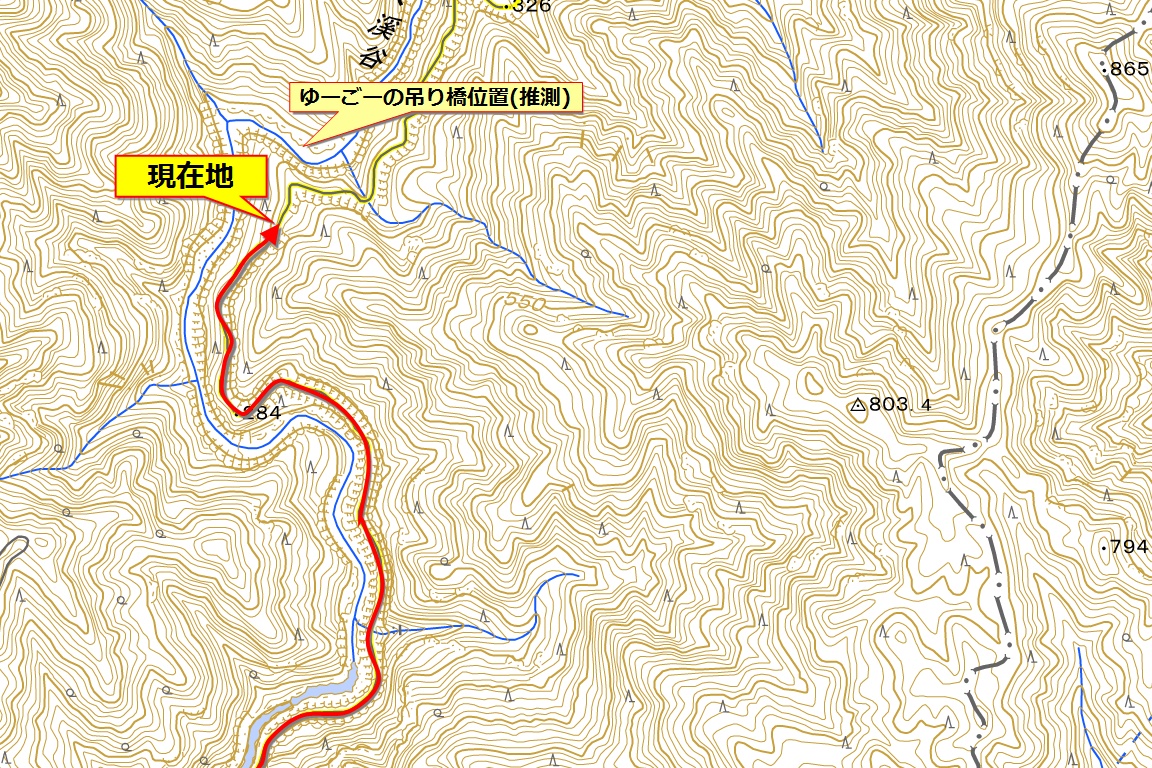376
377
378
379
380
383
385
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
400