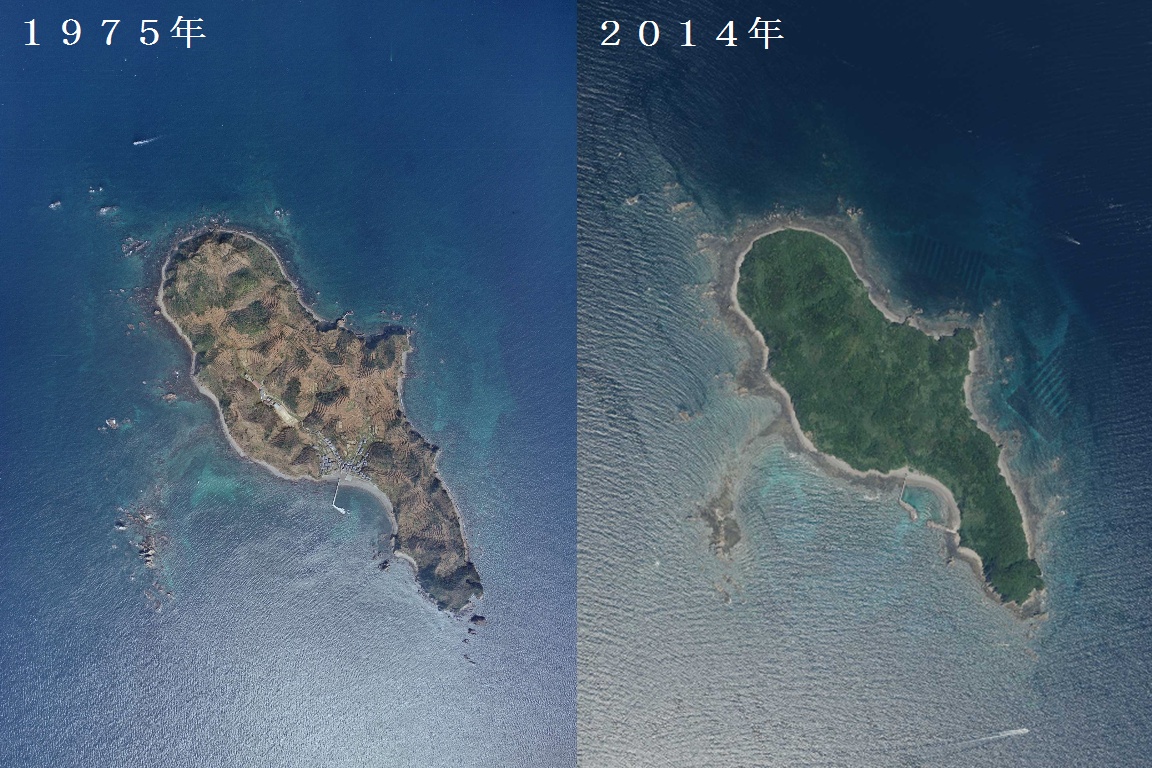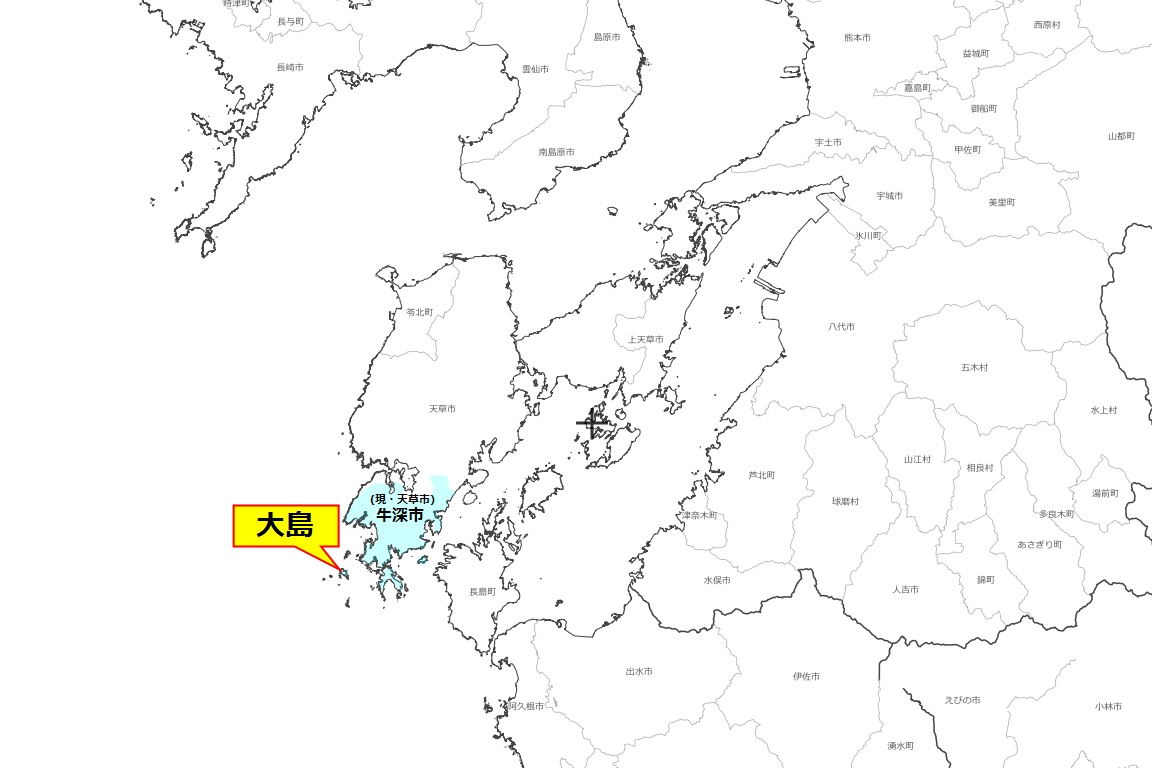151
152
153
154
155
156
158
159
162
163
164
165
166
173
174
175
以上で大入集落についてのツイートは終わりです。大入訪問にあたり、大変お世話になりました東栄町教育委員会様、お話を伺わせていただいた東薗目地区のOさん、そして花祭に関して色々ご教授いただいた花祭りだのんさん(@kawagggg)には、この場をお借りしてお礼申し上げます。