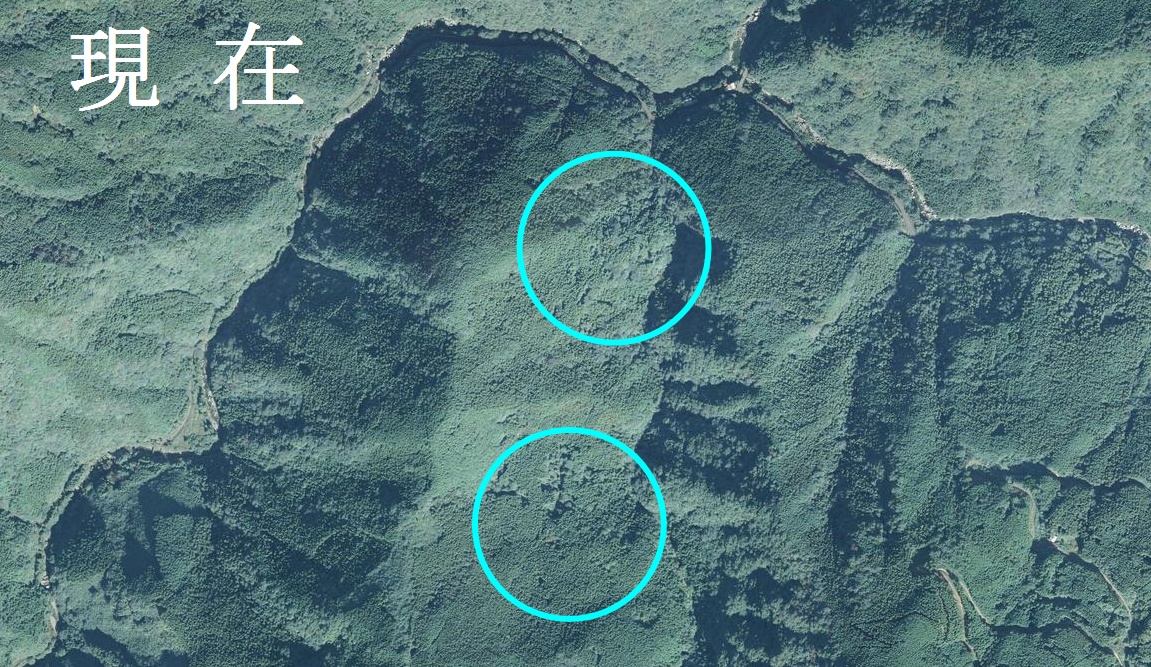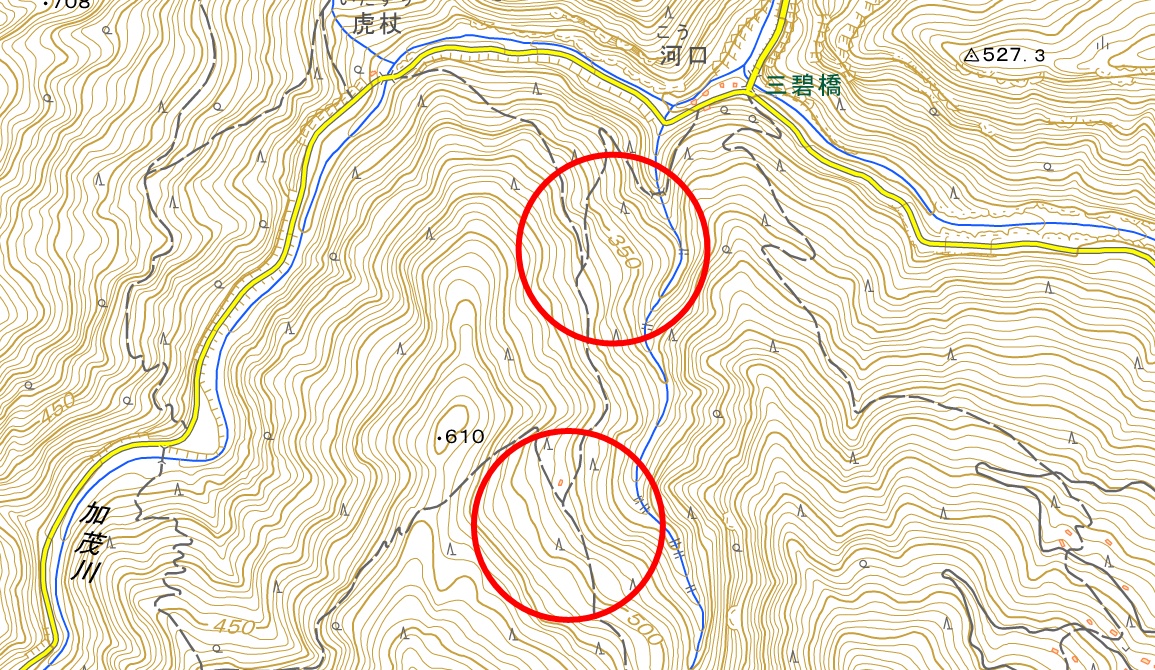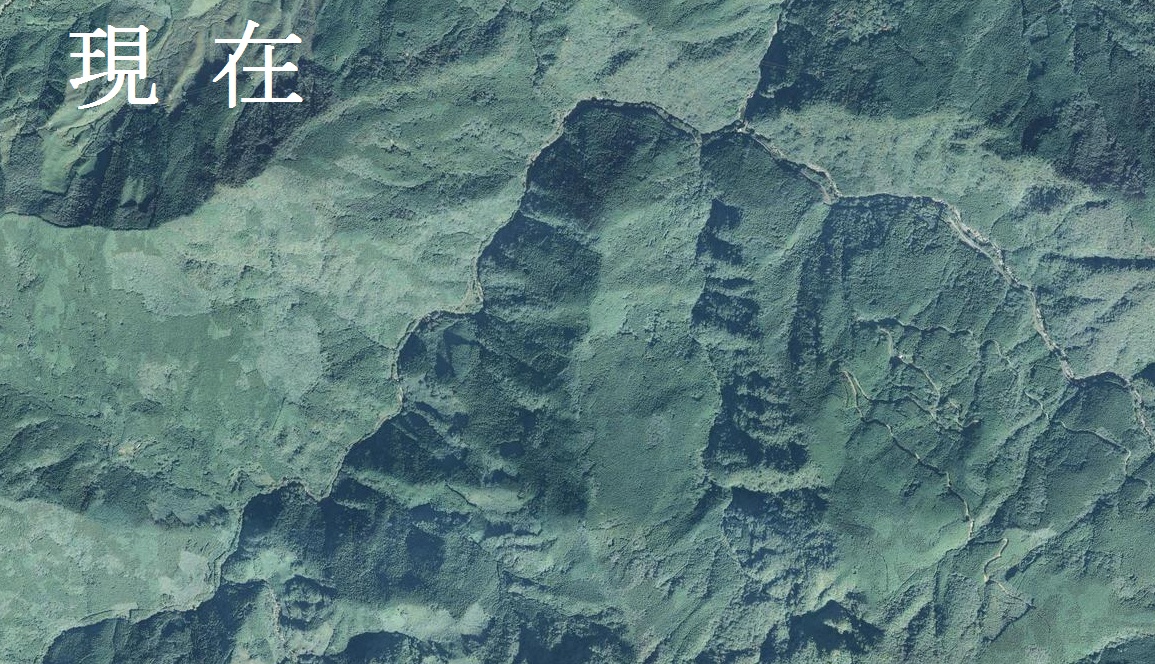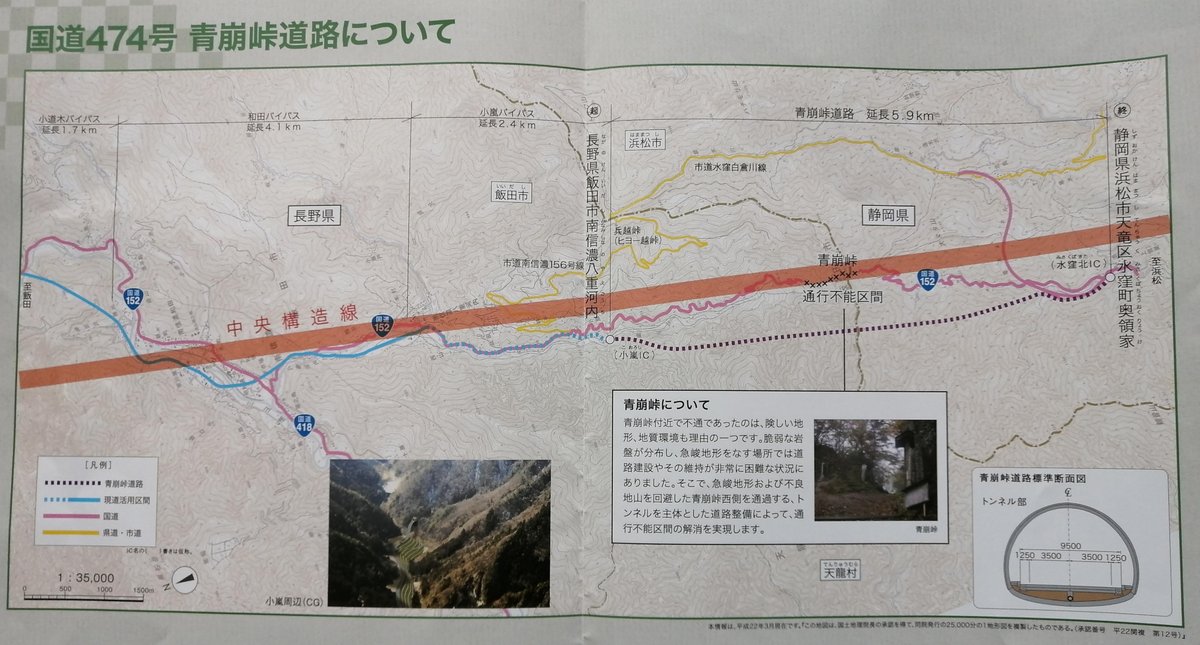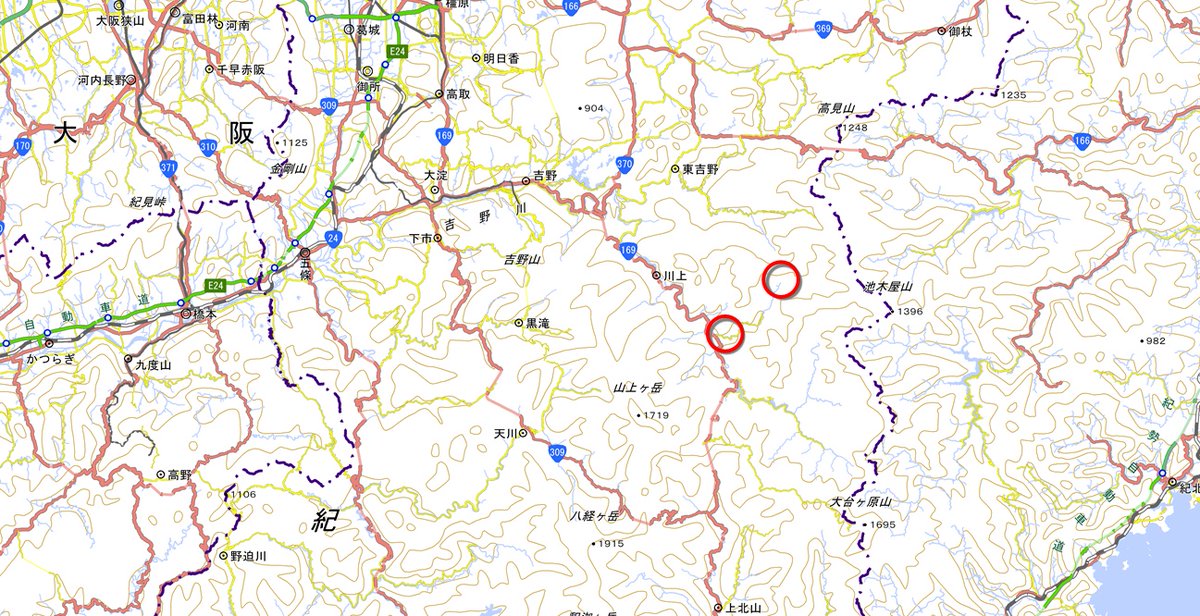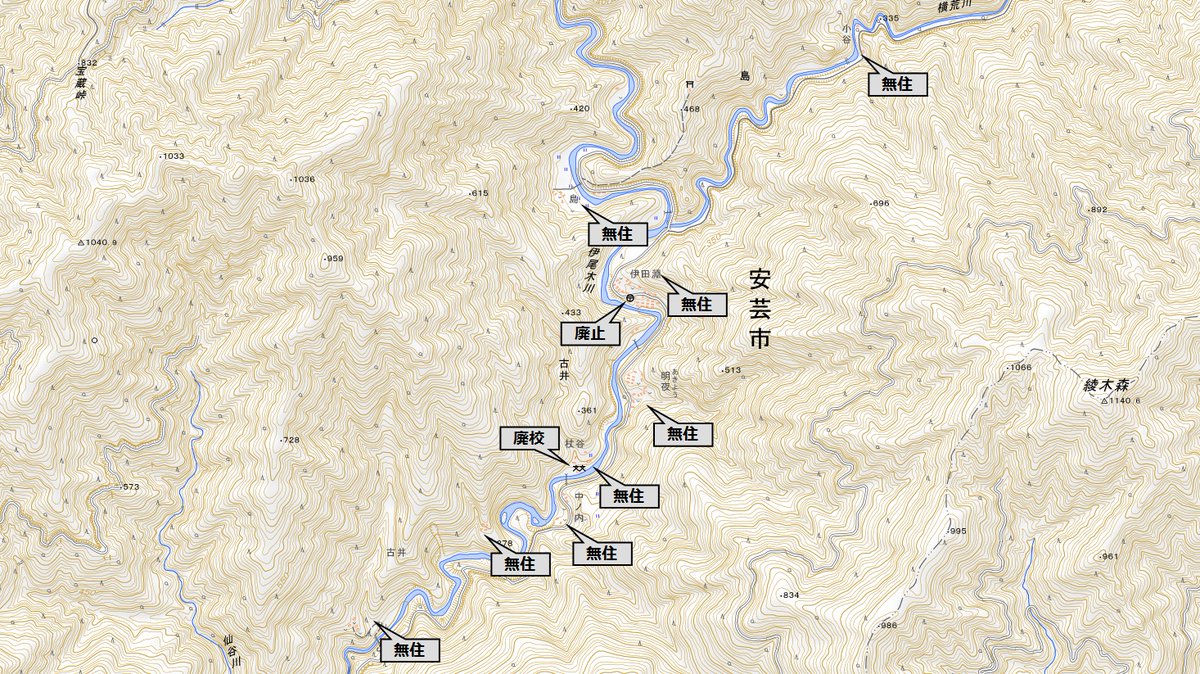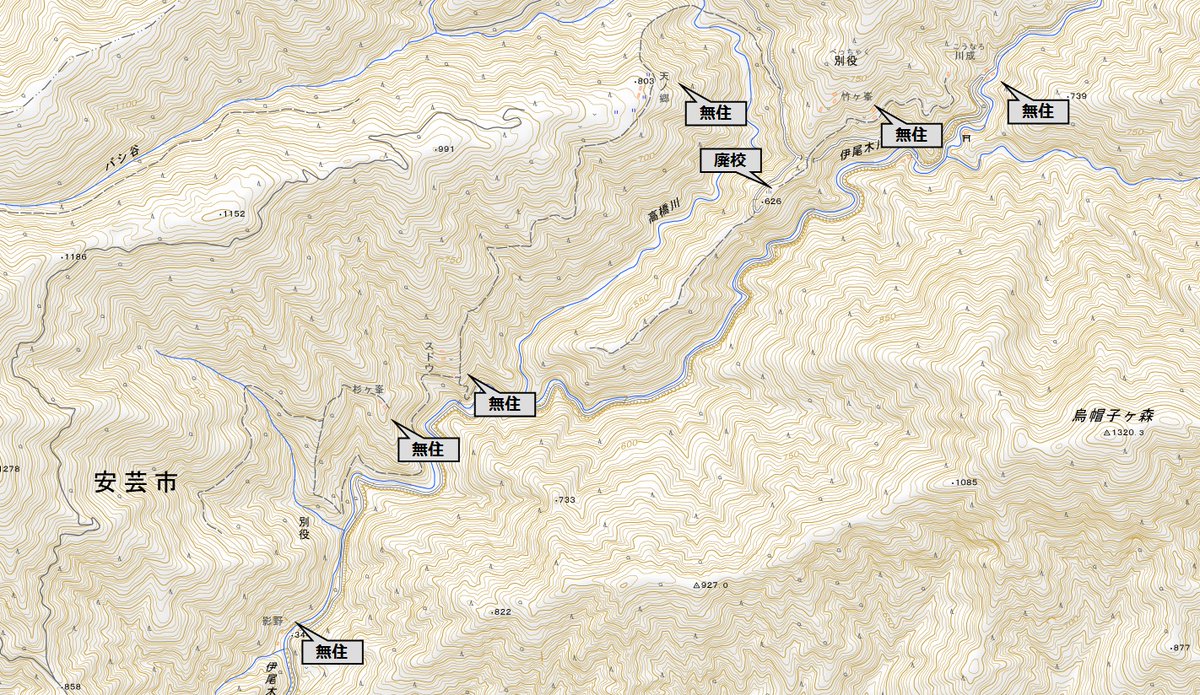401
402
403
404
407
408
410
411
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425