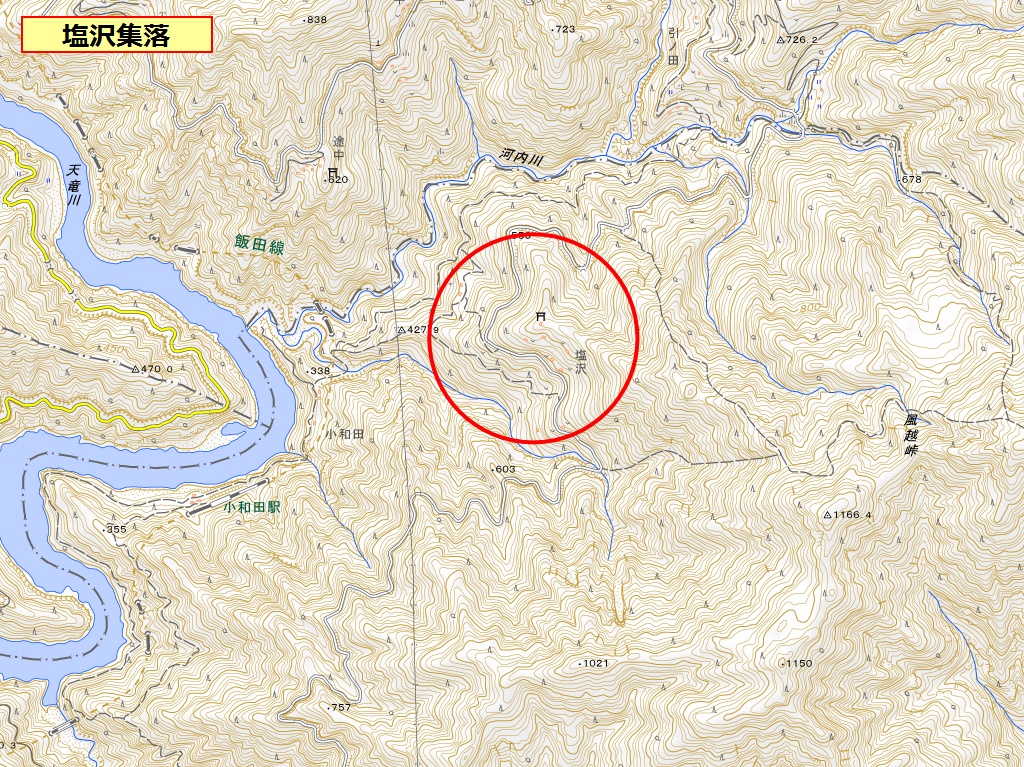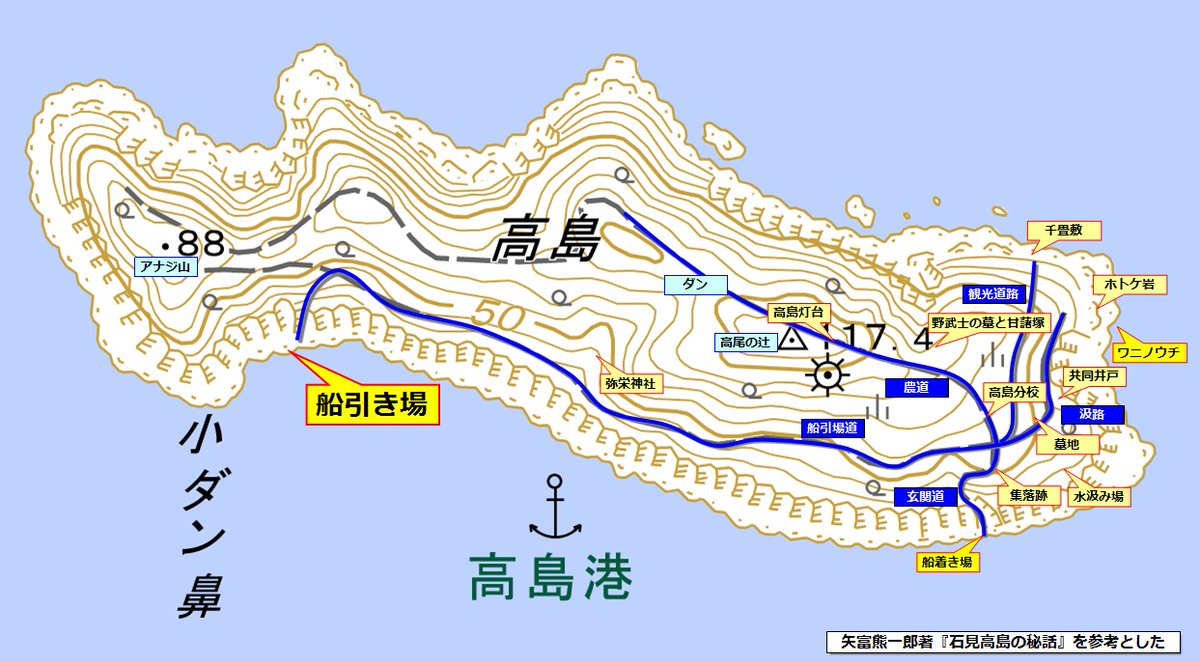277
280
281
282
283
285
288
290
以上で高島についてのツイートは終わりです。今回ご協力いただいた島民の方々、益田市役所のKさん、船長、そして同行いただいた百島氏(@momoshima_jun)、及び鎌手地区自治会のTさん、他1名には、この場をお借りしてお礼申し上げます。
291
292
293
294
高島訪島は終わった。しかし、これで終わることはできない。聞き取り会での内容を纏め、記録として伝えなければならない。そう思い、一つの資料を作成した。リンク先にアップしたので、そちらを参照ください。(見れない方はご連絡ください)
drive.google.com/file/d/179GoG3…
295
296
297
298
299
300