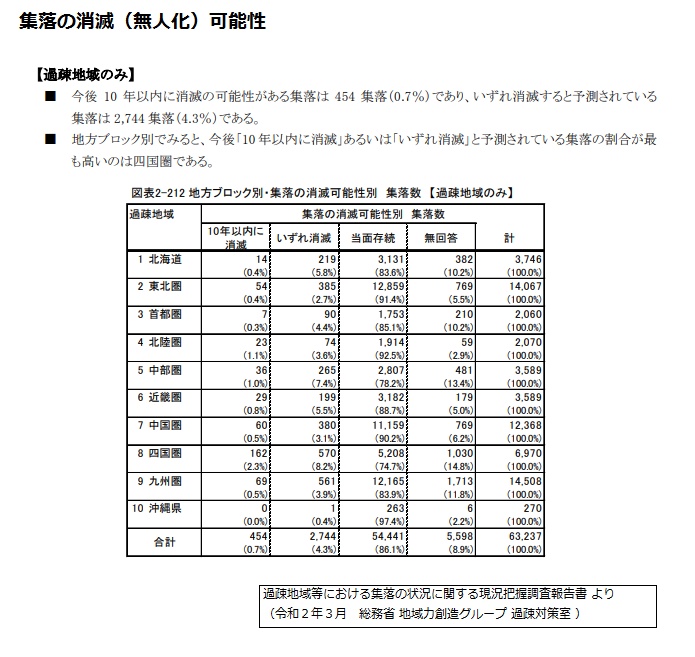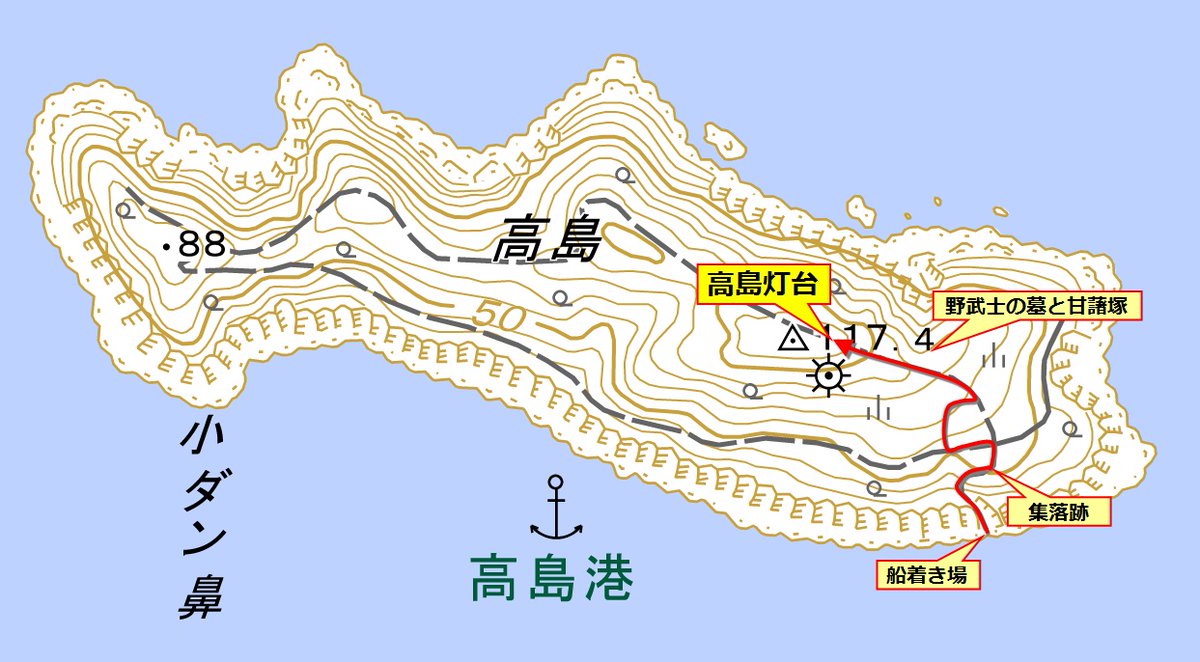201
204
205
206
以上で大入集落についてのツイートは終わりです。大入訪問にあたり、大変お世話になりました東栄町教育委員会様、お話を伺わせていただいた東薗目地区のOさん、そして花祭に関して色々ご教授いただいた花祭りだのんさん(@kawagggg)には、この場をお借りしてお礼申し上げます。
207
208
210
211
212
213
214
215
217
218
222
223
224
225