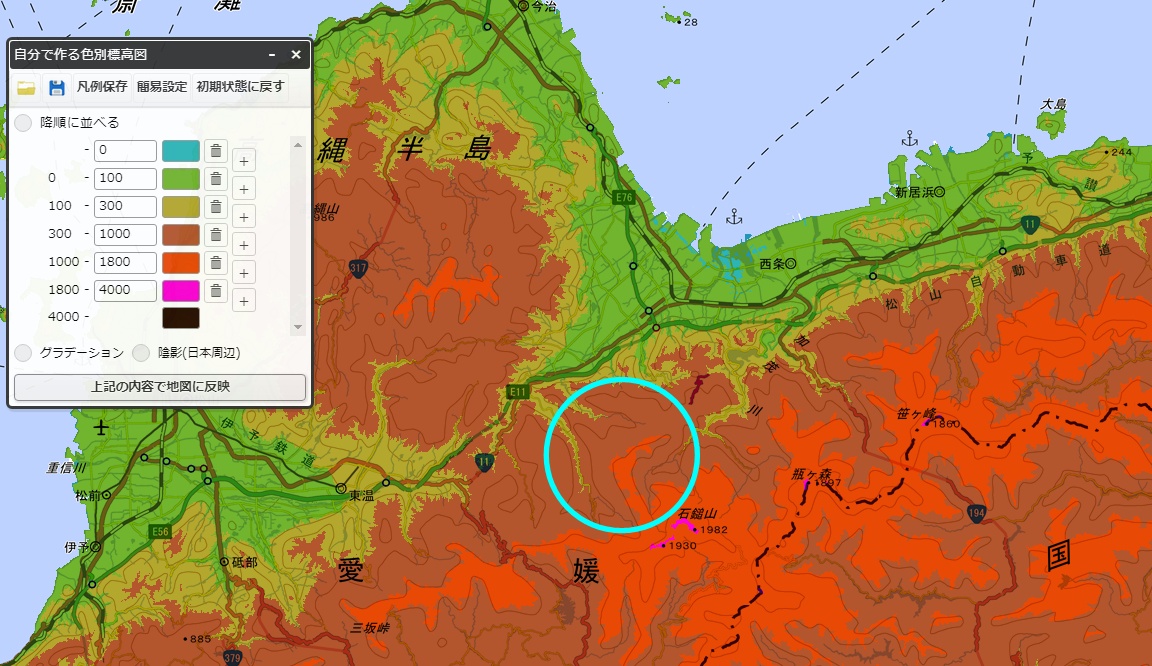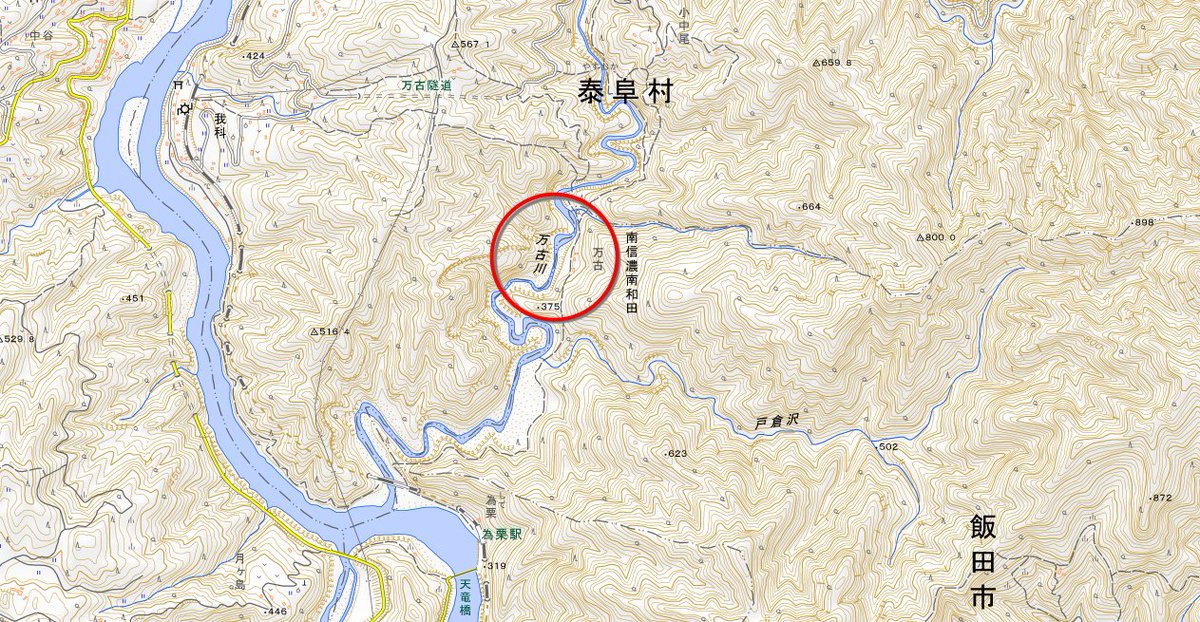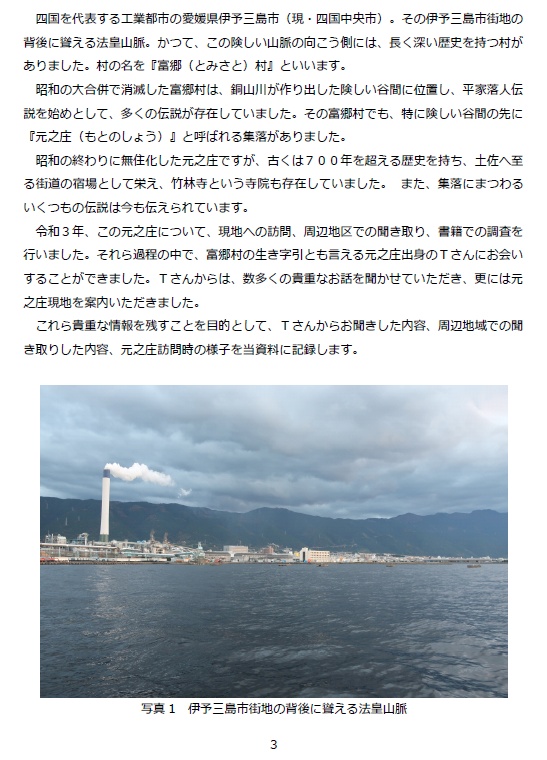176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
『臥蛇島(がじゃじま)』
絶海の孤島。その言葉はこの島のためにある。島の地形、環境はあまりにも厳しい。それでも、長年暮らし続けてきた人々がいたのだ。S.45年集団離島。百島さん@momoshima_junツイートにあるリンク先のPDF資料(十島村作成)は必見です。この資料は本当に素晴らしい。
190
191
194
195
196
197
198
199
200