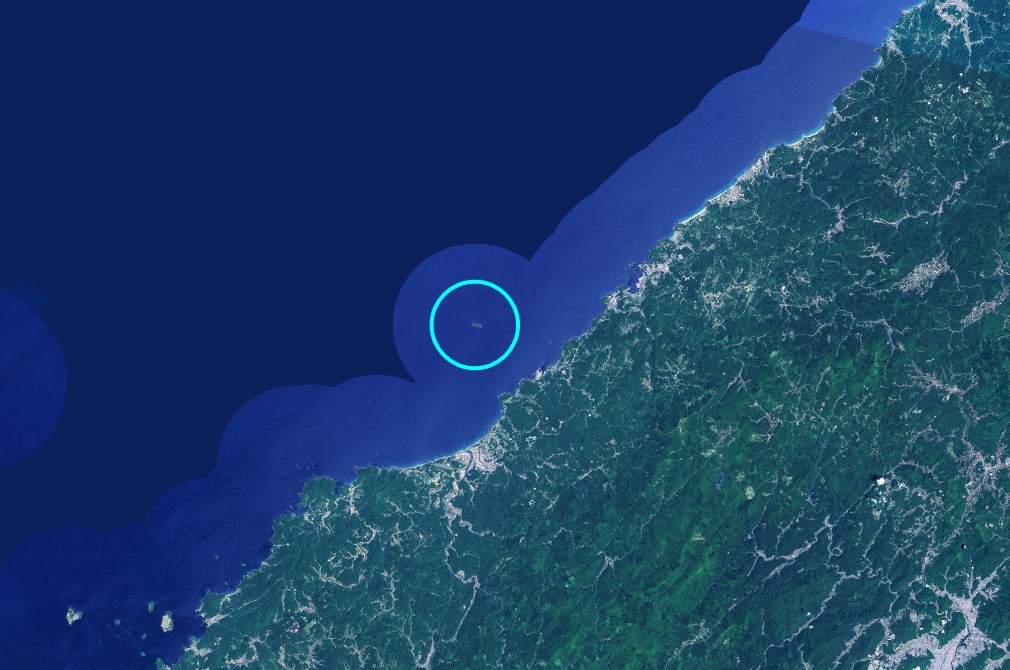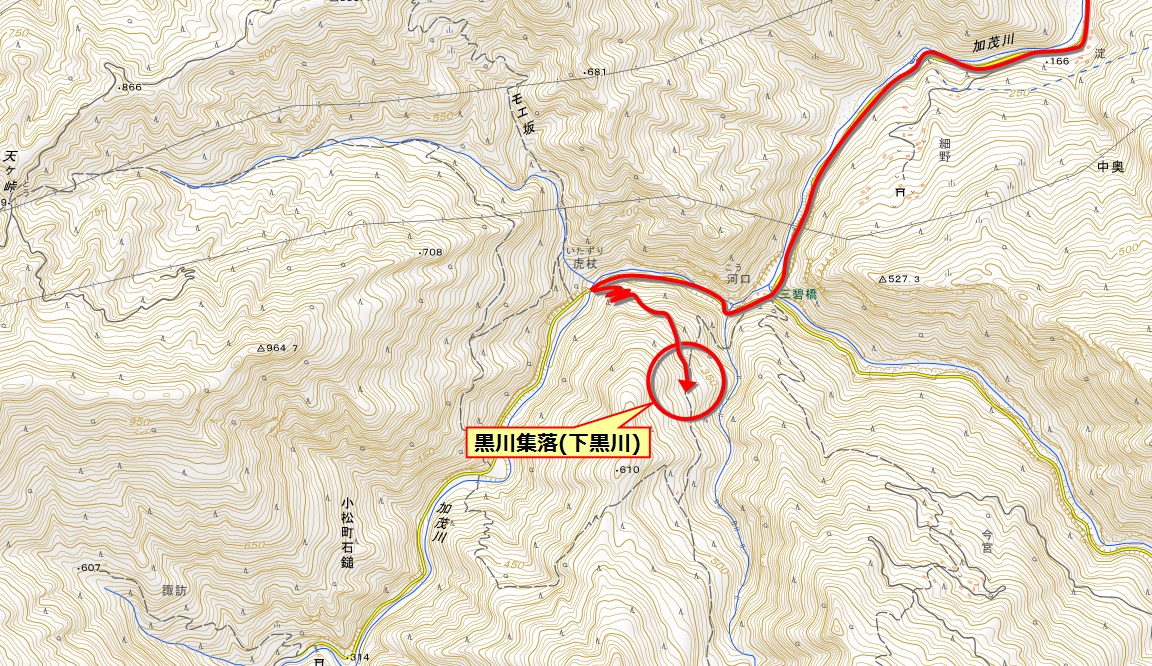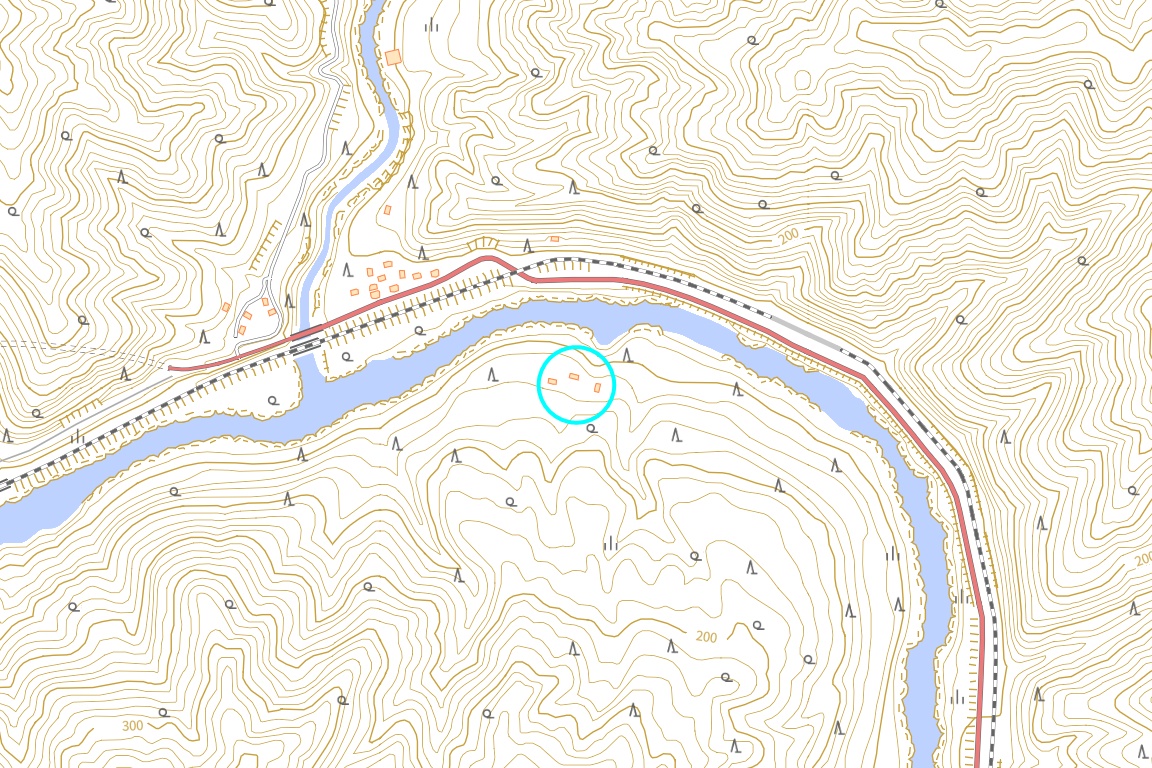151
152
153
154
155
156
158
159
160
161
162
164
165
166
167
168
169
170
172
173