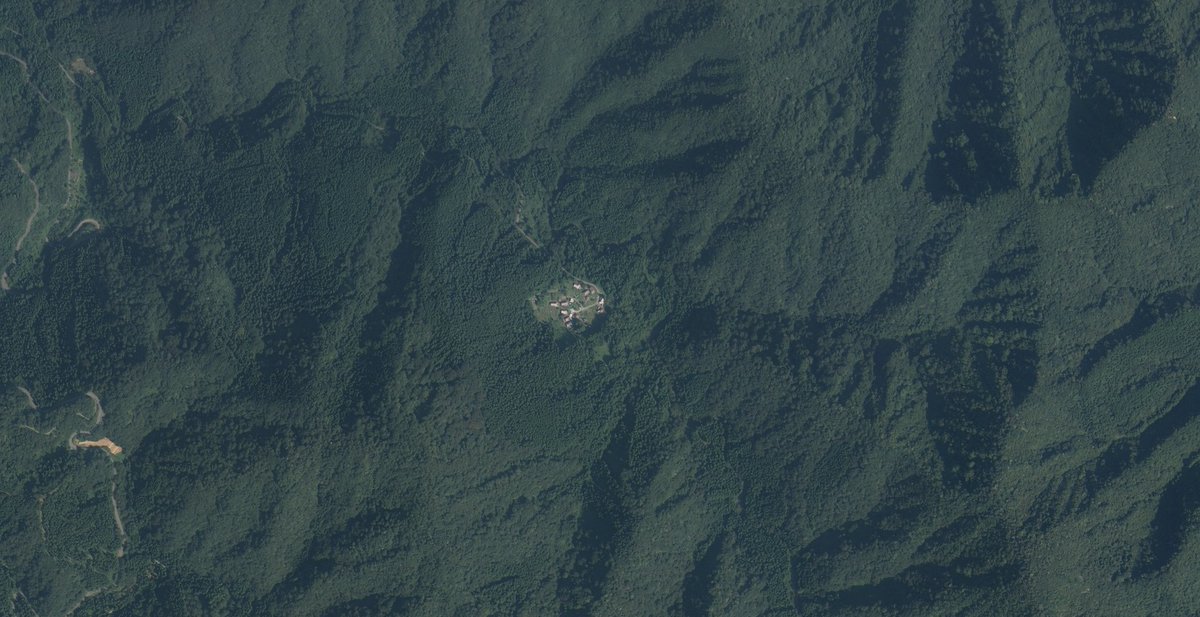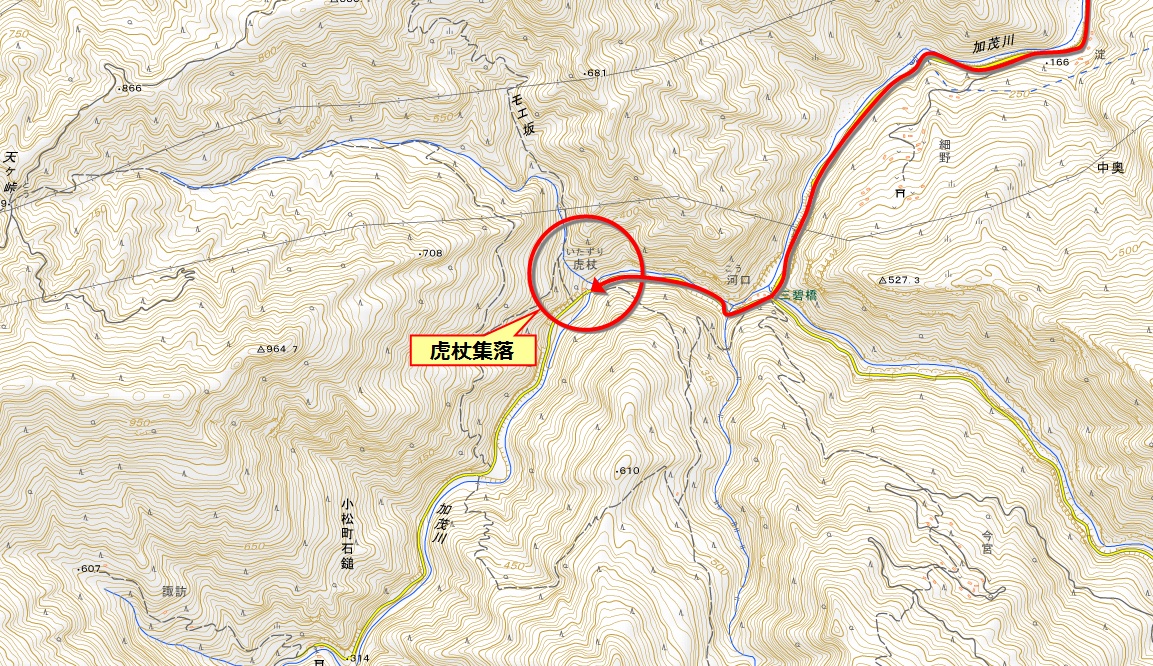126
127
128
130
131
133
134
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
147