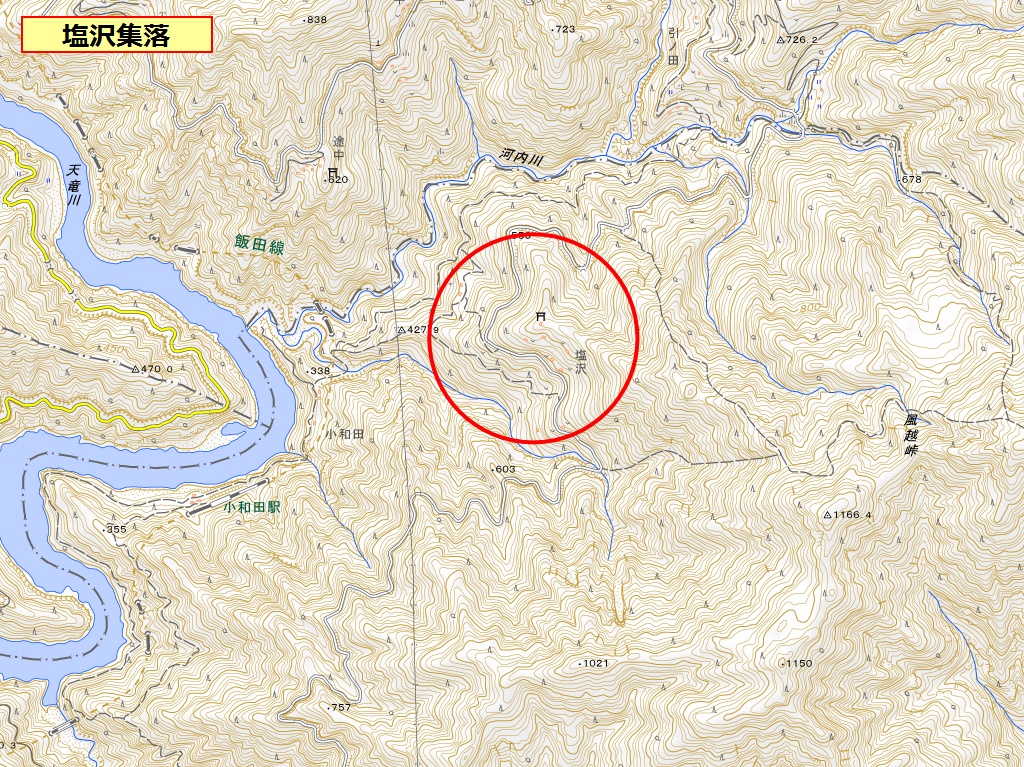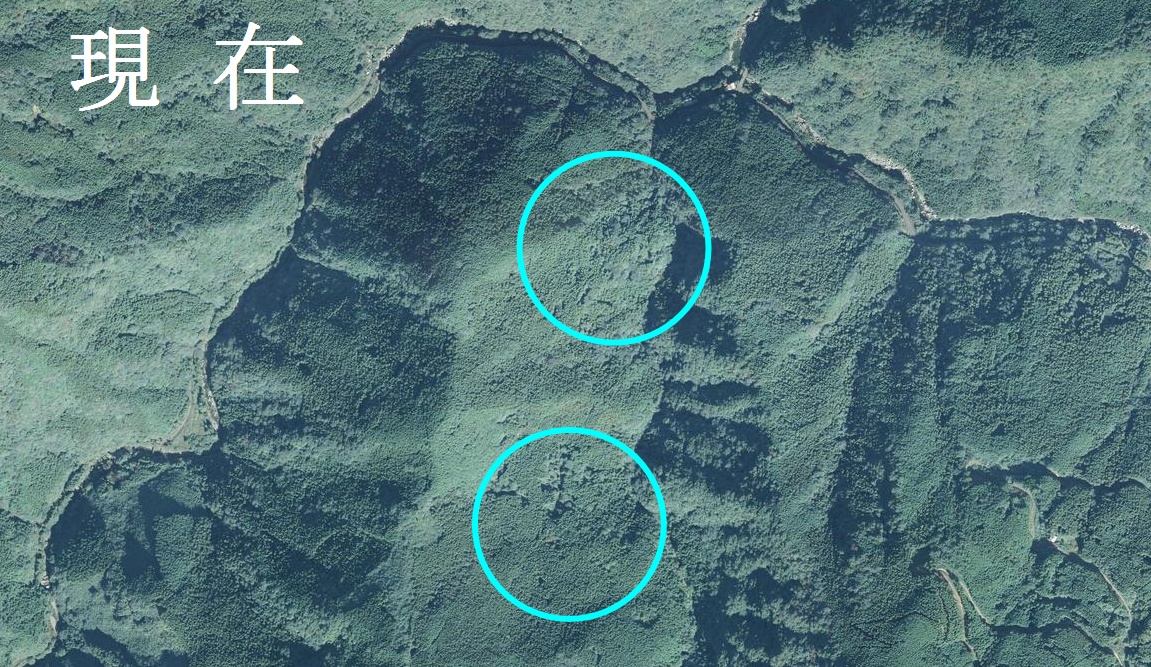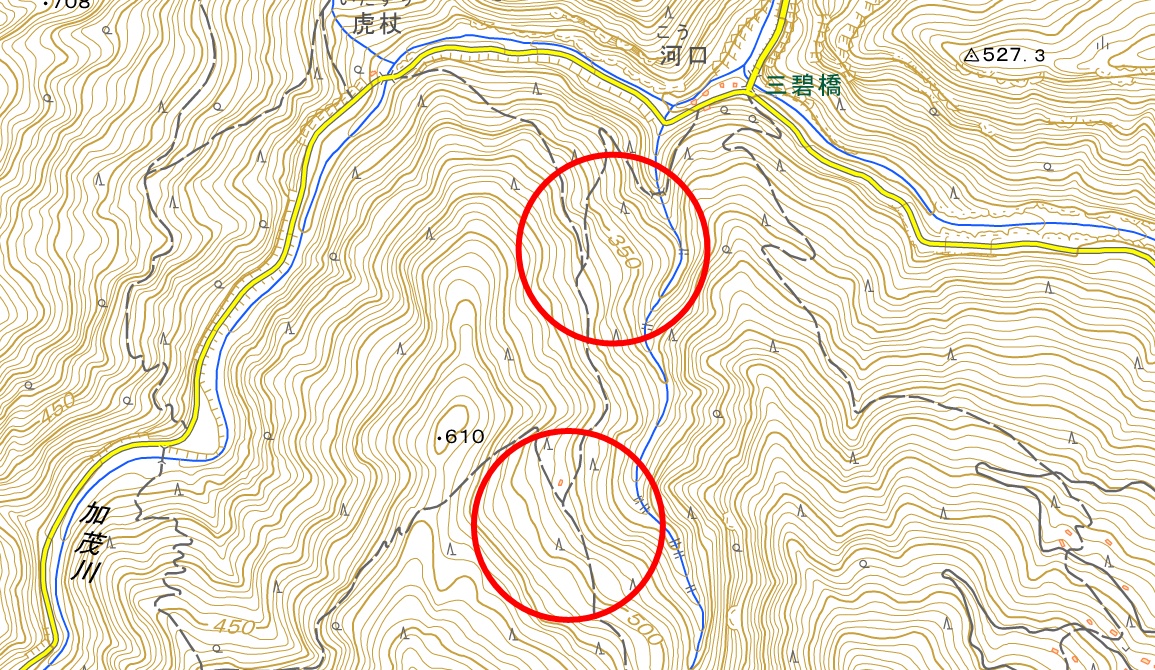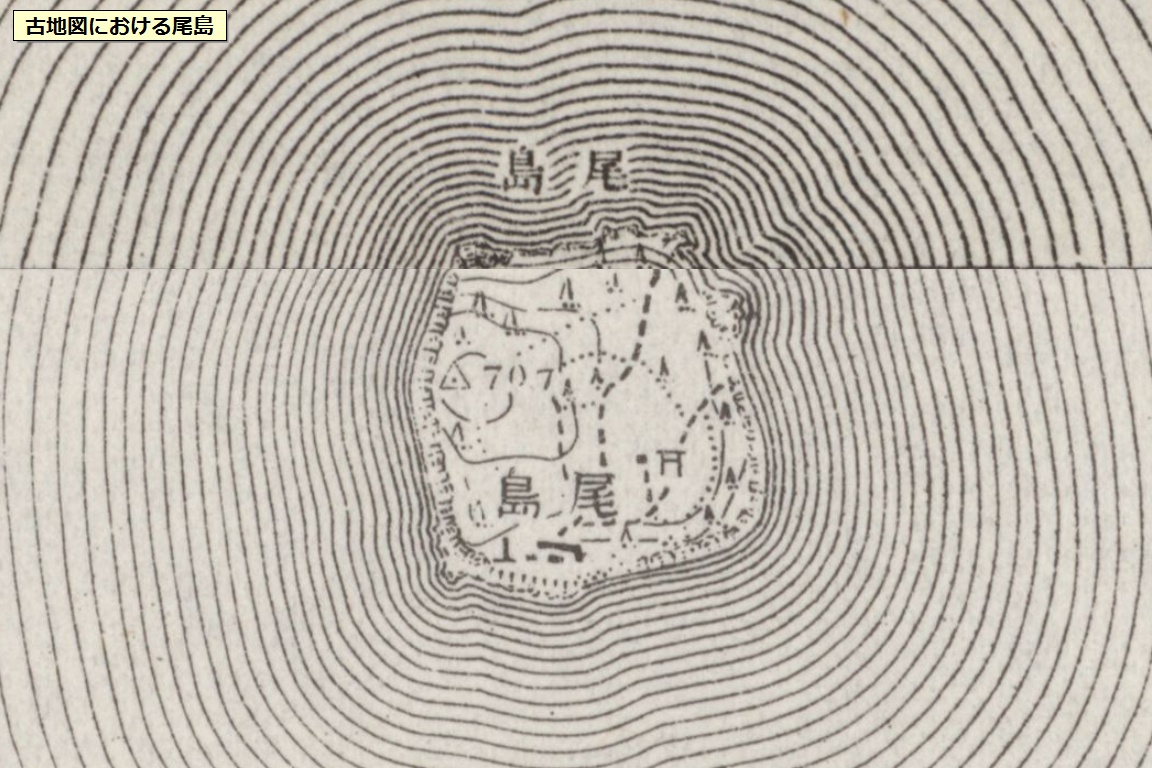76
77
78
田丸集落への訪問は困難だと思っていた。しかし、半年前、"とある方"にコンタクトを取らせていただいてから話は進んだ。"とある方"とは、御主人が田丸出身のRさんである。今回Rさんから伺った内容、更に後日、西祖谷山村の方々から伺った内容について、リンク先に纏めます。
drive.google.com/file/d/1WNHEHs…
79
80
81
82
83
84
85
86
88
90
91
92
93
94
95
97
98
100