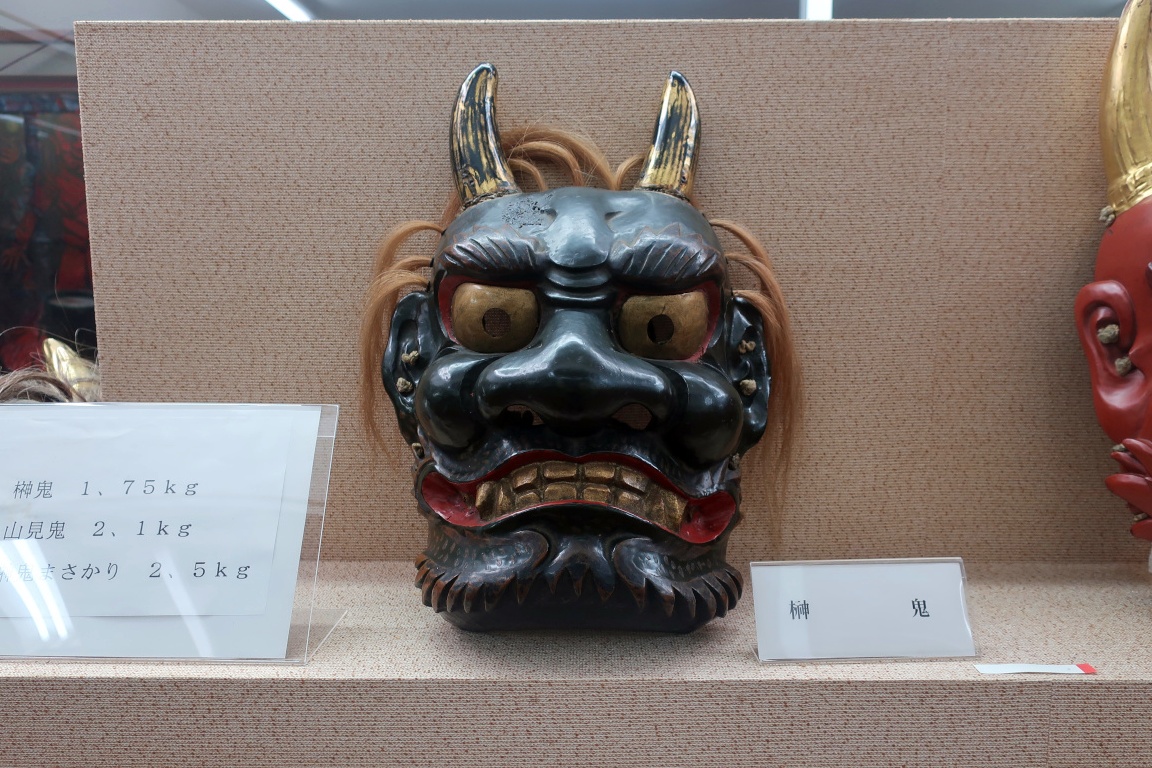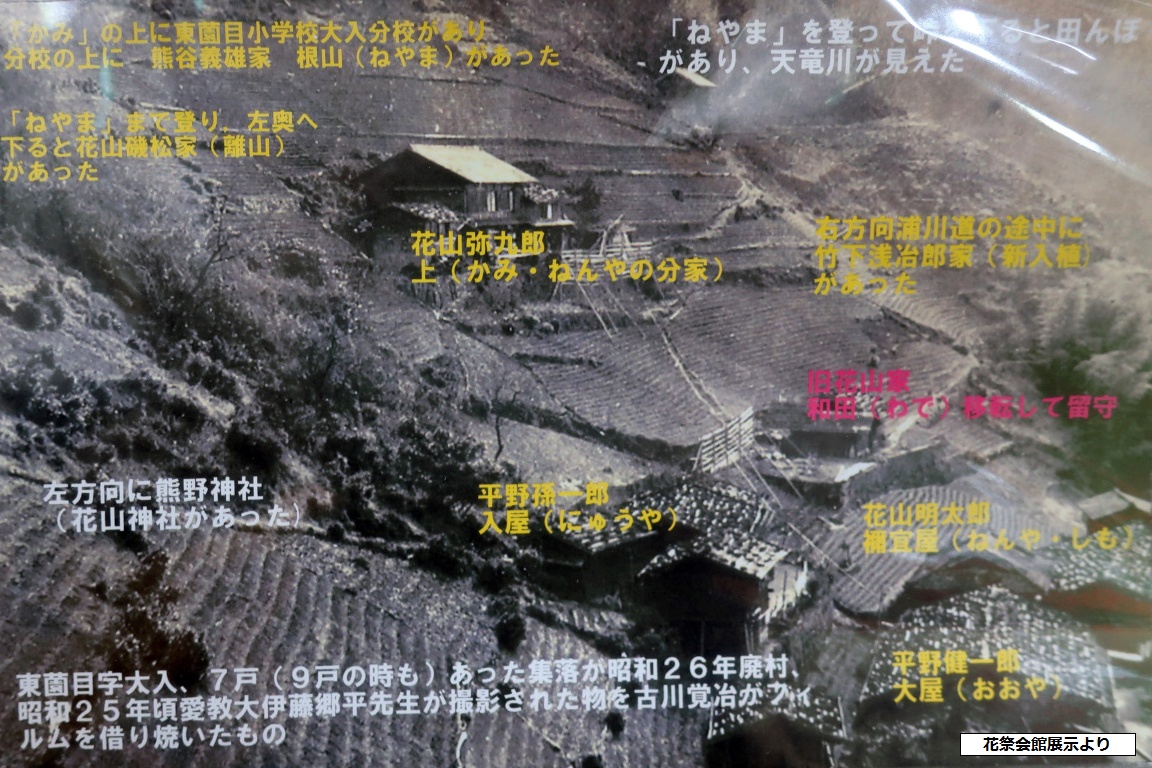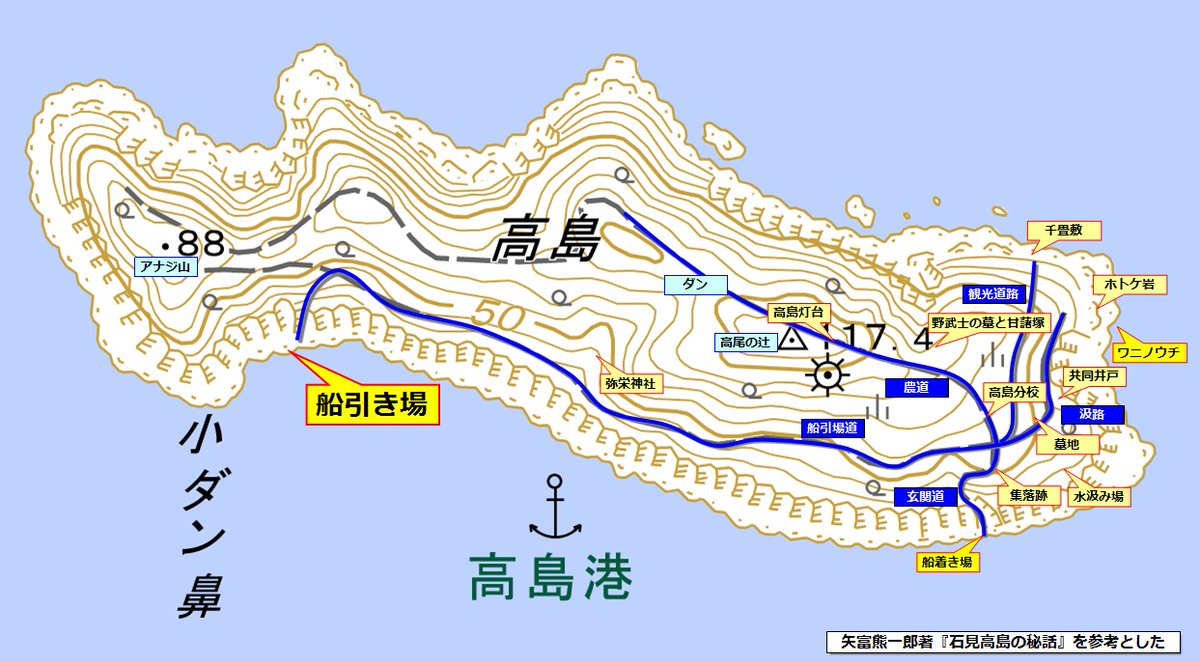276
277
279
280
281
282
283
284
285
286
288
289
290
291
293
294
296
297
298
299
300