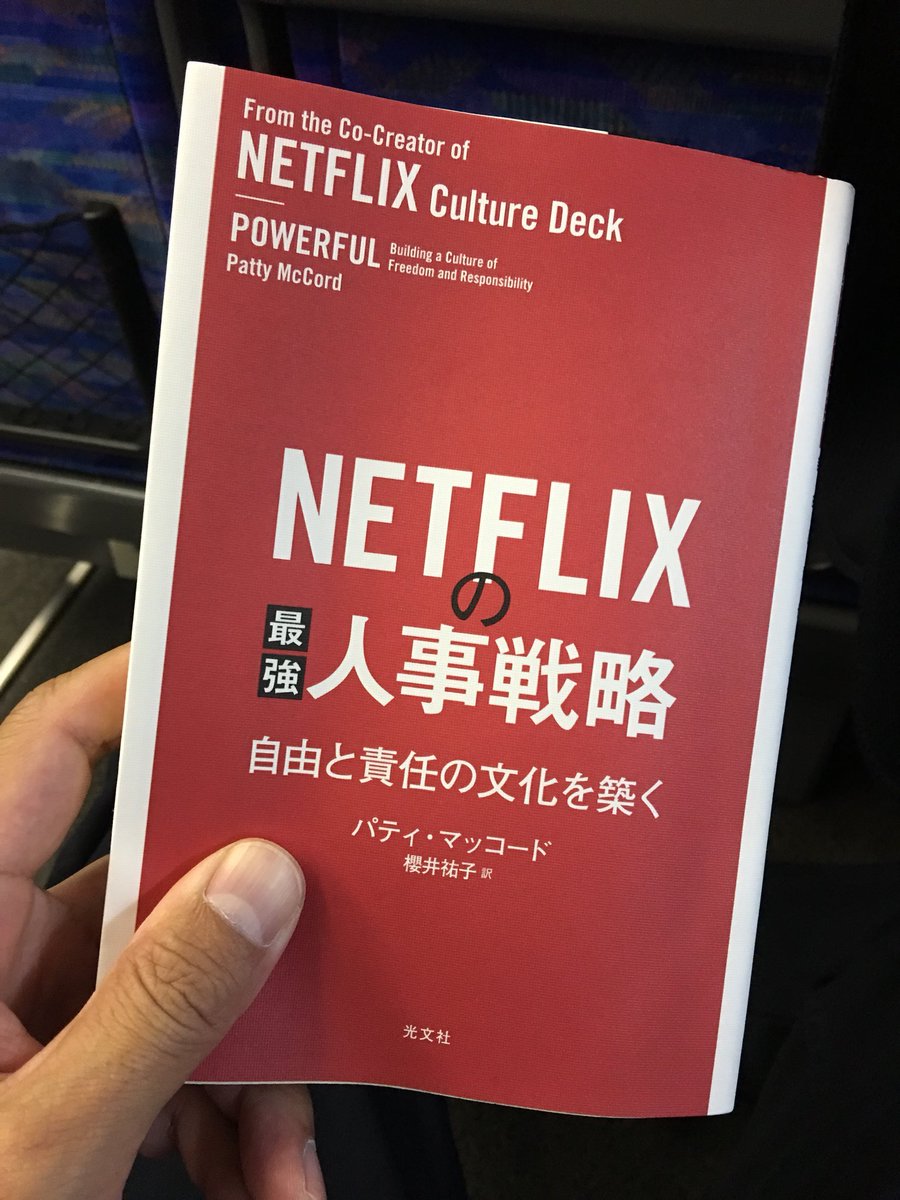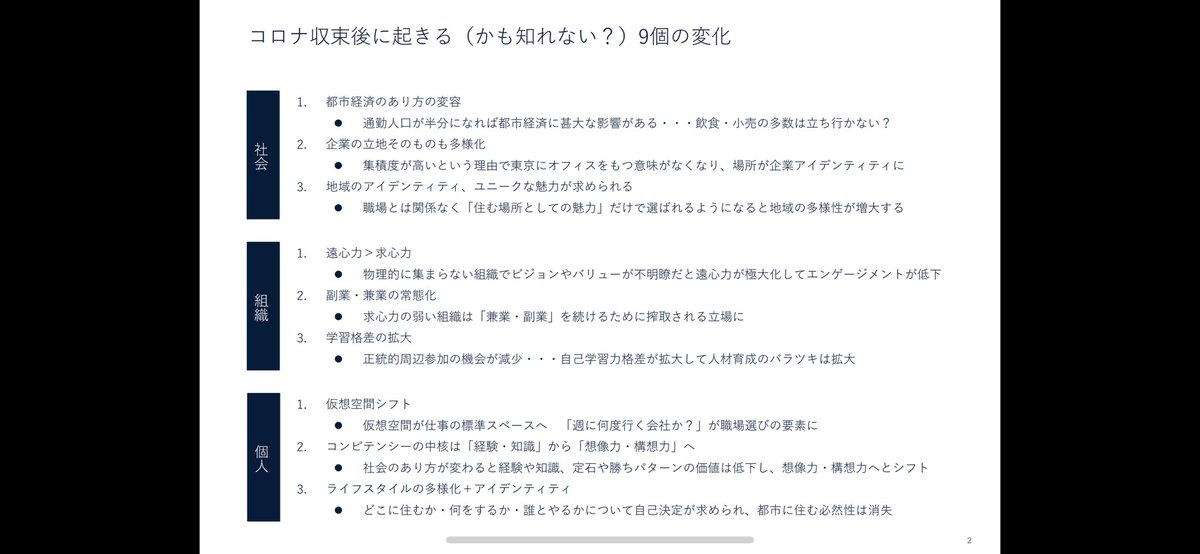177
天才と努力型。よく「天才は努力型に比べて努力してない」と思ってるヒトがいますがそれは誤解です。努力の量は同じか、むしろ天才の方が多い。ただ天才はそれを努力と思ってやってない、遊びだと思って楽しんでるんですね。そう考えれば「努力型が天才に負ける」のは当たり前です。
178
「一見、優しいが実は冷たい」という人や組織が多い。実際は「一見、厳しいが実は温かい」の方が良いんですけどね。日本の大企業は多くが前者ですね。表面的な優しさに騙されないようにしたいものです。
179
SNSの影響でこれからは「家の中のモノ」が承認欲求を満たすための商材になります。クルマや腕時計やバッグは「家の外のモノ」なので、みんな高いモノを欲しがってブランドが成立したわけですが、これからは家具・内装・アートなどの「家の中のモノ」も同じになる。リノベブームってまさにそうです。
180
偏差値というのは頭の良さを測るものではなく「どれだけ意味のないことに長時間集中できるか」という忍耐力を測るものです。どうしても「意味」を考えてしまう人は偏差値を上げられない。意味が枯渇している世界にあって「意味を問わない」高偏差値の人々が社会のリーダーになっているという滑稽さW
181
最近よく思うのですけど、日本では「おそらく大丈夫」という人がアホ扱いされる一方で、能弁に「できない理由、やることのリスク」を指摘できる人がカシコイと評価される風潮がありますね。知的には後者の「具体化」より前者の「抽象化」の方が遥かに難しいんですけどね。
182
好き嫌いをハッキリ明言するようになって一番良かったのは、趣味の合わない人は自然と遠ざかり、趣味の合う人が向こうから来てくれるようになったこと。経営では往々にして短期と長期の利益が相反しますが、これは個人においても同じです。好き嫌いをハッキリさせると長期的にはすごくラクになります。
184
何か話さなきゃ、というプレッシャーに負けて失言を繰り返してきた人生なのですが、最近、シンプルに「その言葉を発することで、世界は少しでも良くなるだろうか?」と一呼吸のあいだ考えてみると、かなりの場合、静かで和かにいられると気づきました。これツイッターでもそうなんですけどね。
185
ビジョンが大事、というけどビジョンのない人っていないんですよね。大事なのは解像度で、ビジョンがぼんやりあるけど動けない、という人はビジョンの解像度が低いんです。「幸せになりたい」というのと「自然に囲まれた海辺の街で好きな物書きの仕事をしてマイペースで暮らしたい」とでは大違いです。
186
野村監督はよくメモを取れと言ってましたけど、その理由が鋭くって、メモを取る習慣がつくと「感じる力」が増すからたいうんですね。感じる力のない選手は絶対に成長しない、感じる力をつけるためにメモを取れ、という。これも「頭の良さ」における「入力」の話ですね。
187
「何をしたいのか?」がはっきりしないなら問いを変えて「どこにいるべきか?」を考えるのも手です。アンディ・ウォーホルは成功の秘訣を聞かれて「然るべき時に、然るべき場所にいること」と言ってますけど、この年になるとこのアドバイスの重みがよくわかります。とにかく「居場所」が大事です。
188
リベラルアーツを学ぶための三つの手法は「人と話す」「旅に出る」「本を読む」。このうち「旅に出る」だけが持っている特徴ってなんだかわかりますか?それは一次情報、つまり「ナマの情報に触れる」ということ。旅が制限される世界では人間の「自由に考える力」も衰えることになります。
189
基本的なことがちゃんとできずに問題を抱えている人ほど「高度なこと」を身につけてショートカットしようとする。テレビと同じで「必殺技」で挽回しようとするんですね。で結果はどうなるかというと、ほとんどは状況を悪化させるだけのようです。
190
40代を過ごして改めて感じたのは、周りのエネルギーレベルを高めるような言葉を発してる人にはますます人もお金も集まる一方で、人のエネルギーレベルを下げるような言葉ばかり発してる人からは人もお金も離れていく、ということ。Twitterでネガテイブなことばかり発してる人は気をつけた方がいい。
191
狼と犬を個体として戦わせたら犬は瞬殺されます。でも狼は絶滅し、犬は繁栄した。パワーをもつ存在に懐くことが生存に有利だからです。これは組織内の生き残りにも同様に働くメカニズムですが「狼みたいな人」がぜんぶ駆逐されて「犬みたいな人」ばかりになった会社なんて僕は嫌ですね。
192
よく「自分には権限がない」と言って動かない人がいますけど、根本的に考え方が間違ってて「権限がないから動けない」のではなく「動かないから権限が生まれない」んですよね。
193
よく「若手の育成が課題」という声が経営陣から出ます。さて、GAFAの創業者の創業時の年齢の平均は24歳。ハタチ過ぎの若者が世界を変える会社を作りました。一方で御社の過去十年の時価総額は殆ど伸びていませんね。こんな結果しか残せていない皆さんに若手が育成されて大丈夫なんですかね、という。
194
仏教では「足るを知る」ことを幸福へと至る成熟の条件と考えます。一方で企業や経済は飽くなき成長を求められます。会社の中で「売上はもう十分です」と言ったら確実に出世できませんよね。この点からして企業や経済というのは決して成熟へと至ることのない、破綻を運命づけられたシステムと言えます。
195
人が質問をする時、本当に質問してることは稀なんです。大体は1=私は貴方が嫌いだ、2=私はとても不安だ、3=私は怒っている、のどれかを伝えようとしているので、質問に答えても事態は収拾しない。僕はいつもジュニアコンサルタントに「質問に応えちゃダメ、真意を測りなさい」と言ってました。
196
骨董屋で小僧が修行する時、ホンモノとニセモノの見分け方を教えず、ひたすらホンモノだけを見せますね。そうするとニセモノが来た時にすぐわかるという。芸術も文学も同じでホンモノにずっと接してるとニセモノに接した時に、それがヒトであれモノであれ見抜けるようになります。なんか薄いんだよね。
197
外国にできるだけ出たほうが良い。それはもちろん外国を知るためでもあるんですが、なによりも日本という国がいかにたくさんの素晴らしい面を持っているか、それが貴重なことなのかというのを実感するためです。
198
社会人大学院という言葉は海外には存在しません。こういう言葉が存在するということは「社会に出たら学ばない」というのが基本前提になってるからですが、これは逆に言えば、学び続ける人にとって相対的にラクに成功できる社会だとも言えます。
199
好き嫌いでモノを言うな、と言う人がいますけどね、好き嫌いでモノを言わないから、世の中がおかしなことになってるわけですよね。「通勤嫌い、したくない」って皆が言ってれば今の状況なんて10年前には成立してますよ。
200
勉強のための時間が作れない、という悩みを聞くのですが、テレビありますか?と聞くと、ありますと。だったらまずテレビを捨てると、軽くて1日数時間の勉強時間はできますよ、と。これにSNSの禁止を加えれば、五年後には知識人として働く素地はできます。あとはやるかやらないか、それだけですね。