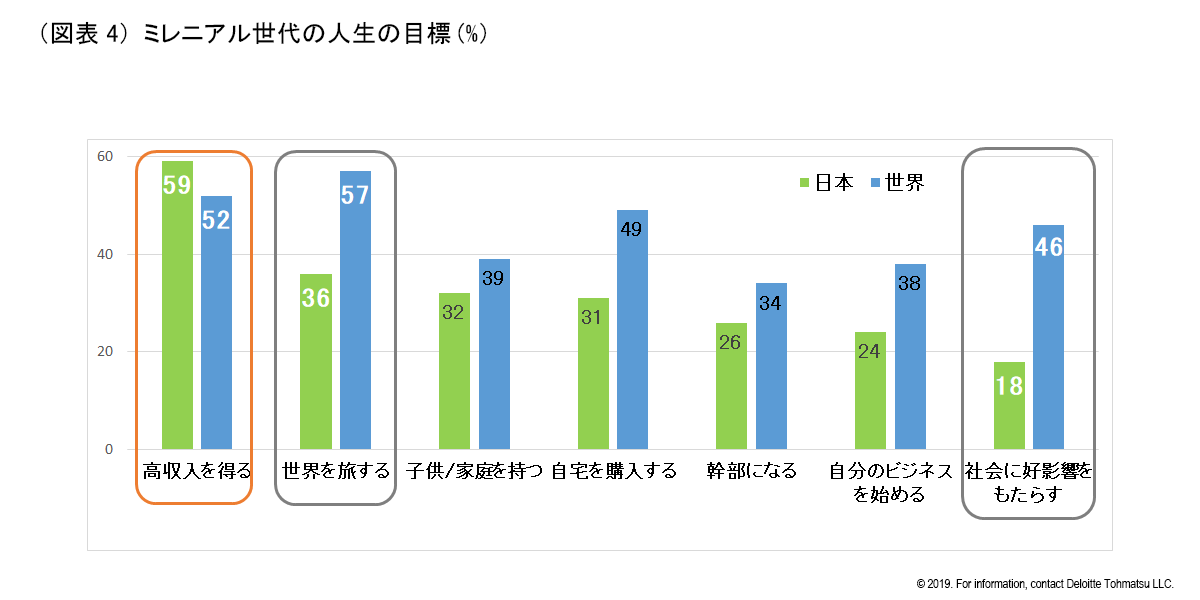226
どうやったらこんな愚策を次々と考えつくのだろうか?ただでさえ子供たちは過酷な受験戦争で疲弊してるのに更に精神的に追い込むような施策は絶対に止めるべきです。僕は強く反対します。tokyo-sports.co.jp/entame/news/25…
227
内容を読むと完全にサディストの異常者ですね。殺された少年には本当に気の毒です。スポーツ指導の資格すら取ってないシロウトが強圧的に指導することが許されている「部活」という異常な世界。この状況を放っておいてる教育委員会他の責任は非常に重いと思っています。
number.bunshun.jp/articles/-/849…
228
つくづく「経済成長」というのは一種の宗教なんだと思いますね。望ましい水準と言われる4%の成長を続ければ経済の規模は100年後には現在の49倍、300年後には12万9千倍、1000年後には10京3826兆倍となります。科学的にあり得ないことを信じる、つまり「信仰」であり「宗教」だということです。
229
イノベーションの停滞を教育の失敗と紐づけて語る人がいますが、全く逆で教育が大成功しているからイノベーションは停滞しているんです。システムの規定に従順でルールに従う素直な子を育てるという教育がうまくいけば、イノベーションが停滞するのは当たり前のことです。
230
ドラッカーが言ってることですけど、歴史上、最も成功したトランスフォーメーションは日本の明治維新であると。で、その成功要因は何かというと江戸時代の教育制度による「多様な人材」だというんですね。考えみれば坂本龍馬も西郷隆盛も、今の日本の偏差値教育では早期にドロップアウトしただろうと。
231
いわゆる「ムーアの法則」は人にも当てはまります。毎年少しずつでも良くしていけば、年数の複利で効くのでやがて大きな変化になります。語学とか楽器が典型ですね。一年やっても大して成長実感は得られないけど地道に十年続けてるととんでもない高度に至る。「手っ取り早さ」は谷底への道です。
232
人文科学系学部を廃止して社会で役に立つ学問に片寄せ寄せするよう文科省が指導してますが、最大の問題は「社会に最適化した人材」ばかりになってしまうと「社会そのもののあり方」を批判的に考え、新しい社会のあり方を提案できる人材が居なくなってしまう、ということです。
233
自分の頭で考える習慣のない人の特徴は「すぐに事例を聞きたがる」ことですね。このような人が指導的立場にいると永遠に先行者になれません。
234
お金を払わずに利用できる、という時は100%、自分が逆に利用されてるということですね。
235
よく「全員経営」みたいな理念を掲げている会社がありますね。不思議なのは、こういう理念を掲げているくせに経営情報を現場には開示していない、ということです。「全員経営」なのに、なぜ現場担当者に全情報を開示しないのか?理由は単純で「本気ではそう思ってないから」ですよね。
236
そもそも「頭がよくなる」というのはどういうことか。情報処理プロセスに当てれば「入力→処理→出力」でスループットが向上するということでしょう。昨今はこのうち「処理」だけが議論されがちですが「入力」を司るのは五感なので、結局「感じる力」が高まらないと頭も良くならない、という単純な話。
237
家事は視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚を全て扱う総合芸術で、これを楽しまずに煩事と捉えるのは勿体ない。統計を見ると「家で料理を作る理由」について、日本では「経済的理由」が一位なのに対して、イタリアでは「自己実現」や「料理への関心」が上位に来る。成熟した社会なんだなあと思います。
238
「マジメに働いてるのに給料が安い」と言いますけど、むしろ「マジメに働いてるから給料が安い」わけですよね。これは「昭和的価値観」の典型です。求められてるのは「マジメに働く」ことではなく「カシコク働く」ことでしょう。
239
「成長」というウサンくさい言葉に注意したい。人が「成長」という時、その背後には必ず自分が大事にしてる価値観やモノサシを他人に押し付けるという欲求がありますね。でも本当の成長…というか成熟っていうのはモノサシが変わることであり、さらにはモノサシが要らなくなることですよね。
240
ニュータイプは「答え=Answer」ではなく「問い=Question」を探す。「Questionには「Quest=冒険の旅」という言葉が入っています。Never stop questioning!
241
久しぶりにブログ書きました。教育改革が失敗し続ける本当の理由は「個性的な人材などホンネでは誰も望んでいないから」という考察です。artsandscience-kipling.blogspot.com/2020/08/blog-p…
242
鈍感力みたいなことが言われてますけど鈍感な人は共感力がないのでイノベーションも起こせないしリーダーシップも発揮できないでしょう。ジョアン・ハリファクスが「コンパッション」で指摘してる通りで「敏感だけど感情に圧倒されない強度」が大事なんだと思います。ただ鈍感になるだけじゃ、ねえ。
243
目標の与え方で組織の能力は豹変します。ソ連に勝て!と叱咤するアイゼンハワーの元で失敗に終始したメンバーが「ソ連に勝つ?そんなことどうでもいいよ、月に行きたくねえか?」と言ったケネディの元で大活躍する。目標の与え方が上手な人は「錬金術師」なんです。ゼロから価値を生み出してしまう。
244
欧州でトヨタへの風当たりが強まってる。日本社会が火力発電に依存しているのでトヨタの工場も火力発電で動いている。従ってトヨタ車を買うことは火力発電を容認することになる、という論理です。日本におけるエネルギー政策のあり方がグローバル企業の競争劣位に繋がってる。
245
「最初」にあまり拘らない方がいいと思ってます。「もうやってる人がいる」「もう言ってる人がいる」と批判する人が居ますけど、その「やり方」「言い方」がショボいのであればいくらでもハックすれば良い。電球の発明者はエジソンではないし検索エンジンの創始者はグーグルではありません。
247
コロナ後は職場の学習のあり方も大きく変わる可能性があります。なんとなく先輩の仕事を見て覚えるという、いわゆる「正統的周辺参加」は職場が仮想化すると非常に難しくなります。コロナ前後では身体的な学習機会が大幅に減少するので人材育成、特に新人の育成に大きな格差が生まれると思います。
248
日本では企業に雇用を守ってもらうというのが政府の考え方なので企業を守ることで雇用を守るという考え方が通用しますが、これからの時代においてそのような考え方が通用するのか。個人的には「企業は守らないけど個人は守る」というセキュリティの考え方にシフトするべき時期に来ていると思います。
249
LGBTは生産性が低いとかほざいて叩かれてるマヌケな人がいるみたいですけど、結局、教養の問題なんだと思います。ソクラテス、レオナルド、カラバッジオ、ワイルド、ウィトゲンシュタイン、チューリング、ソンタグなど、人文科学の巨人の多くがLGBTでした。あんたの生産性と比較してどうなのよ、と。
250
一番重要な「どの船に乗るか」「どちらへ漕ぎ出すか」という論点には無頓着なまま、沈みつつある船の中で一生懸命、上司や同僚にアピールするためのスキル学習に余念のない人々。あの、沈んでますよ、その船。