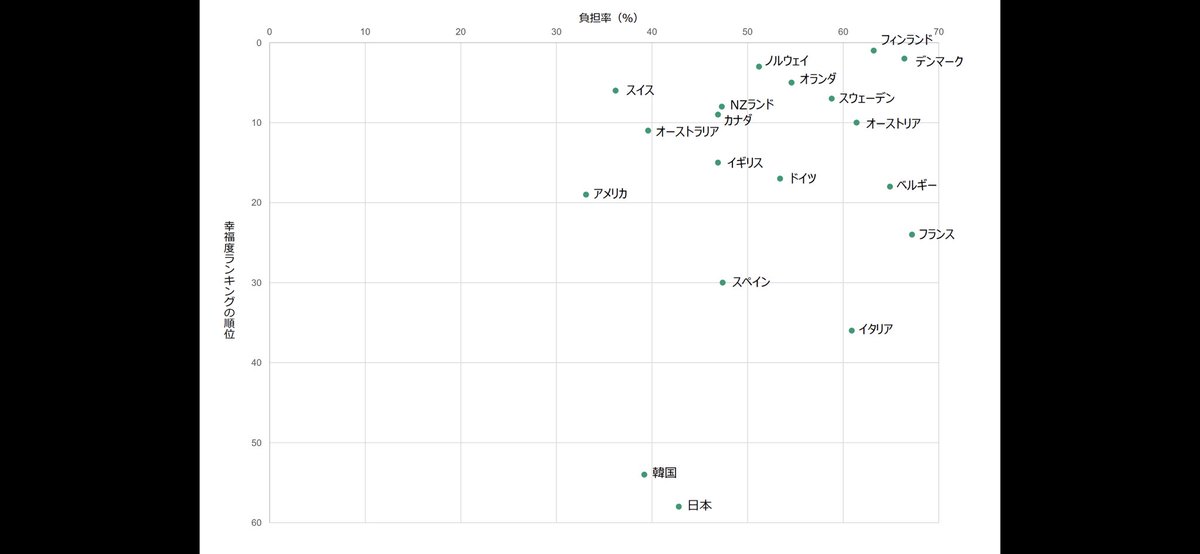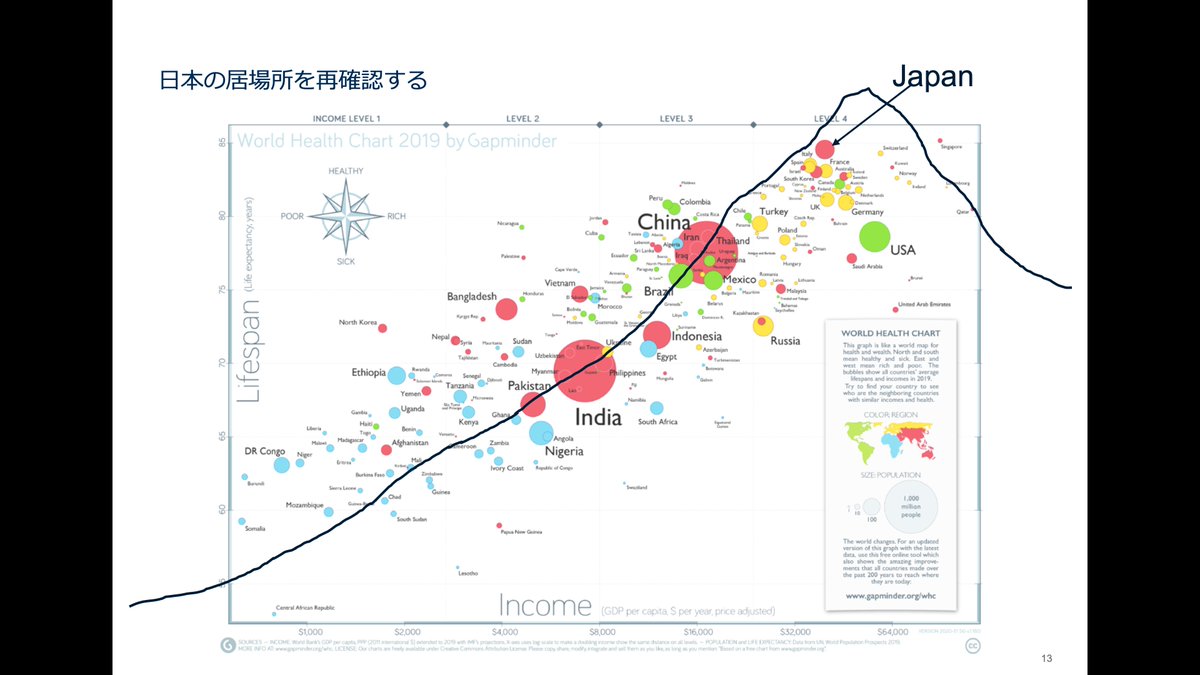726
これ、とても良い本でした。「給料がその人の価値を決める」という考えがいかにに間違っているかをさまざまな研究データから明らかにしています。著者の提案する「最低賃金の引き上げ」と「富裕層への大幅な増税」に強く賛同します。
amazon.co.jp/%E7%B5%A6%E6%9…
728
オルテガの定義によれば、貴族=対価を求めずに何らかの役割を自ら背負い、果たそうとする人で、大衆=何らかの役割を背負うことなく対価を求める人となる。そして「貴族なしに社会は成立し得ない」と指摘する。一種のアマチュアリズムなんですね。プロって対価が前提ですから。
729
大衆の欲求や不満をスキャンして政策に反映させるビッグデータ民主主義のような仕組みを唱える人がいますが、そんなことをしたら政策の水準が民放テレビ局の番組レベルに落ちるだけだろうと思います。民放テレビ番組の悲惨さは「民意を精密に拾うと何が起きるか」の先行事例です。
730
20世期半ばまで、先進国の生産性の伸び率は恒常的に5-7%を記録したけど、この数値は21世紀に入って1%近くにまで落ち込んでいる。ビジネスは歴史的な役割を終えつつある、と考えた方が良いのかもしれない。
731
ファイナンスのファイはファイナルのファイと同じ「終わり」という意味です。日本の地方都市の中心がシャッター通りになっているのはコミュニティ形成を「商店=お金をやり取りする場」に頼ろうとしたからでしょう。欧州の活気ある地方都市の特徴はコミュニティの中心部が商業と紐付いてないことです。
732
ありとあらゆるモノが溢れている状態で「ハングリーになれない人」が多くなってくると、モチベーションが最も重要な「競争優位を左右する経営資源」になります。モチベーションはビジョンが与えられて初めて高まるのでここでもやはりビジョンが重要という。
733
リモートワークによってコミュニケーション不足が発生してるのなら、それはもともと「記号化できない情報」に依存して組織を回していたということでしょう。それは例えば「空気」のようなものだということです。
734
「昭和的優秀さの終わり」について書きました。「ニュータイプ」本日から発売です。diamond.jp/articles/-/206…
735
哲学は役にたつのか?という問いへの答えは、その問いを発する人の考え方次第というところがあります。哲学というのは「自分が所属しているシステムを批判的に考察する技術」ですから、そのシステムの中で年収や地位を上げることしか考えてない人にとってはなんの役にも立たない技術なんです。
736
一緒にいることでかえって人生の質が悪くなる「逆切磋琢磨」の人間関係に気をつけたい。
737
反論を気にされる人が多いですけど、反論があるということは「痛いところを突いた」ということで主張に力があった、鋭さがあったという証拠なんです。反論のない主張なんて、ねえ。
738
教育で個性を育てる、という言説の概念矛盾。教育の力を否定する積もりはないのですが、教育で個性を伸ばせると無批判に考えることの危険性は大に指摘しておきたい。マルクス、ダーウィン、アインシュタイン、ウィトゲンシュタイン、ライト兄弟、ジョブズ・・・イノベーターの多くはなぜ独学者なのか?
739
不確実性ってネガテイブに言われますけど一番の贅沢でもあるんですよね。ヨット、ハンティング、カジノ、ヴィンテージカーなんかの「お金持ちの趣味」の共通項は「不確実性」です。
740
「働き方改革」の問題は「長時間労働は嫌なものだ」という通念を前提にしてることです。僕もそうですが、世の中には「仕事を取り上げられたら鬱病になってしまう」という人もたくさん居ますからね。もっと多様性を前提にしてもらわないと。
741
金利がゼロになると時間も消失すると書きましたけど、これは「勤勉」の終焉にも繋がります。「今の時間」と「未来の時間」で後者に価値があるから「今」を手段化するわけです。「永遠の今」が循環するだけなら、この瞬間を踊り、歌い、描き、愛することに使った方が良いとなりますよね。祝祭の高原。
742
自分自身の必然性から出ていないことを「他人もやってる」「みんなやってる」ということでついやってしまう悪い癖。本当に自分に必要なことは何か、それを地に足をつけて考える。
743
自分にとって大事なのに賛同する人が現時点では少ない、そういうものに「自分のアジェンダ」がある。これは伝説的起業家、ピーター・ティールの言葉ですが、僕にとってそれは論理と生産性が席巻する世の中において蔑ろにされている美意識と人間性でした。
744
変革を目指す人にとって、なかなか変化の予兆が見えてこない状況は辛いものです。しかし複雑なシステムというのはある一線を超えると急激に変化する…物理の用語でいう相転移を起こすことを忘れてはなりません。「あと一押し」で変化したかもしれないのに諦めてしまうことのないように。
745
746
こういう時こそ「役に立たない」ことの価値を再認識したい。いまアートはあまりにもその功利的な側面ばかりが語られていますが、そもそも「功利的」であることがそんなに重要なのかという。rockinon.com/news/detail/13…
747
大バカ者のパレード。こういう人たちが子供にどういう教育をしているのかを考えると恐ろしい。
www3.nhk.or.jp/news/html/2020…
748
英科学誌ネイチャーに続いて仏高級紙ル・モンドも日本学術会議の任官拒否を批判。私たち日本人がボンヤリしてる中、世界が日本政府の「知に対する姿勢」を厳しく問うています。キチンと声を上げましょう。
lemonde.fr/international/…
749
自分の人生を思い返してみると、失言というのは「ウケを狙った」ことでやっている気がします。不適切な場所で、ウケなくていい時にウケようとして、スベって転んで大怪我してる。緊張に耐えられないからなのでしょうか・・・「ウケたいと思う気持ち」に負けない自分になりたいと思います。
750
情報は多いほど良いと考えている人がいますが「多すぎる情報」は「少なすぎる情報」よりタチが悪い。葛藤を常に抱えて迷っている組織や人の特徴は「多すぎる情報に翻弄されて右往左往してる」という点です。よくある予測はそういった情報の最たるものですね。